※本記事にはプロモーションが含まれています
「なんでうちの子は、こんなに落ち着かないんだろう…」
食事中もソワソワ、座っていられない。公園でも走り回って目が離せない。
そんな悩みを抱える保護者の方は、とても多いんです。
でも実は、3歳児が落ち着かないのには理由があります。

この記事では、現役保育士がその原因と家庭でできるサポート方法をやさしく解説します。
目次
3歳児が落ち着かないのは「発達の途中」|脳と体の仕組みを解説
少し専門的なお話になりますが、まずは3歳児の落ち着きのなさについて知っておきましょう。
脳の発達からみる「落ち着きのなさ」
3歳児の脳はまだ発達途上にあります。特に前頭前野(自己制御や注意力を司る部分)が未熟なため、以下のような特徴が見られるのは自然なことです。
- 衝動を抑える力が未発達で、じっと座っているのが生理的に難しい
- 注意の持続力が短いため、すぐに気が散りやすい
- 考える前に行動に移してしまう傾向がある
3歳頃は神経ネットワークの整理が進む大切な時期。脳の情報処理システムがまだ完成していないため、「落ち着きがない」と感じる行動が目立つと言われています。
自律神経の発達も関係している
3歳児は自律神経の調整機能も発達途上にあります。
- 興奮状態からリラックス状態への切り替えが苦手
- 一度動き始めると、自分で「ストップ」をかけるのが難しい
- 身体的なエネルギーが高く、常に動いていたい欲求がある
これらは全て正常な発達過程であり、成長とともに徐々に落ち着いていくものです。

3歳ごろ落ち着きがないと感じる背景には、このような理由があるんですよ。
要注意!一般的な落ち着きのなさと区別すべきサイン
多くの場合、3歳児の落ち着きのなさは発達の一過程ですが、以下のような様子が顕著に見られる場合は、専門家への相談を検討してもよいでしょう。
- 極端な多動性:常に走り回り、ほとんど静止することがない
- 危険な行動への認識不足:何度注意しても高いところに登る、道路に飛び出すなど
- 集団活動への不参加:どんな集団活動にもほとんど参加できない
- コミュニケーションの困難:指示がほとんど伝わらない、視線が合わない
- 感情コントロールの困難:頻繁にかんしゃくを起こし、なかなか落ち着かない
このような行動が日常的に続き、生活に支障をきたしている場合は、早めに小児科や発達支援センターなどに相談することをおすすめします。
家でできる対処法①|環境を整える

発達上仕方のないことなのか!と感じても、落ち着きのなさは気になりますよね。そこで現役保育士である【mozせんせい】が現場で心掛けている環境設定について紹介していきます。
物理的環境の整備
落ち着きのない3歳児への環境設定は非常に重要です。
環境によって落ち着きのなさを軽減させることもできます。
刺激を適切に管理する
- 視覚的な刺激を減らす
- 活動スペースの壁面装飾をシンプルにする
- おもちゃや教材は使用するもののみを出し、他はしまっておく
- 食事の時間は余計な玩具や絵本を片付け、食事に集中できる環境を作る
- 空間の区切りを明確にする
- カラーテープやマットで活動スペースを視覚的に区切る
- 「ここは読書コーナー」「ここは製作コーナー」など、場所と活動を一致させる
- 個別スペースを用意し、刺激が多い時に落ち着ける場所を確保する

視界に気になる物がたくさんあると、それに気を取られて席を立ったり、遊び始めてしまったりするので、まずは目の前のことに集中できる環境設定を心掛けてみましょう。
動きたい欲求を満たす工夫
- 計画的な運動時間の確保
- 一日の中で十分な運動時間を確保する(朝の時間、活動の合間など)
- 天候が悪い日でも室内でできる運動遊びを用意する(障害物コース、簡易トランポリンなど)
- リズム遊びやダンスなど、全身を使った活動を取り入れる
- 静と動のバランス
- 活発な活動の後には、静かな活動を入れる
- 「動の活動」の後に「静の活動」へスムーズに移行できるよう、クールダウンの時間を設ける

静と動の時間を作ってあげることで、動きたい欲求を抑えることができることもあります。どうしても集中してほしい出来事の前は、思い切り外で体を動かしメリハリのある時間の使い方を心掛けてください。
家でできる対処法②|言葉かけと関わり方の工夫

具体的で効果的な声かけ術
落ち着きのない子どもへの声かけは、具体的でわかりやすいことが重要です。
短い言葉で、短的に伝えること。肯定的で、してほしい行動を伝えることを心掛けてください。
効果的な指示の出し方
- 短く、具体的に伝える
- NG「ちゃんとしなさい」「落ち着いて」
↓
- OK「椅子に座ってお話を聞こう」「両手をひざの上に置いてみよう」
- NG「ちゃんとしなさい」「落ち着いて」
- 肯定的な表現を使う
- NG「走り回らないで!」「大声を出さないで!」
↓
- OK「お部屋の中では歩こうね」「お友達に聞こえる声で話そう」
- NG「走り回らないで!」「大声を出さないで!」
- 視覚的サポートを活用する
- 言葉だけでなく、絵カードや実物を見せながら伝える
- 「まず○○、次に△△」と順序を示す写真やイラストを用意する
- タイマーを使って「この時間まで座ります」と視覚的に示す
効果的な褒め方・認め方
実際に私が心掛けている声かけや関わり方の一例も紹介します。
- 小さな成功をすぐに認める
- 「歌の間、椅子に座れたね!すごい!」
- 「お友達と順番に遊べたね。がんばったね」
- 努力のプロセスを具体的に褒める
- 「走りたかったけど、歩こうと頑張ったね」
- 「待ちたくなかったけど、順番を守ろうとしたね」
- 非言語的な承認も活用
- 目を見てうなずく、ハイタッチをする、抱きしめる
- 言葉以外での承認も効果的
気になる行動に対して注意ばかりして、良い行動があったときにはスルーしていませんか?小さなことでもまずは「褒める」ことが大切です。

返事ができたね。最後まで座っていられたね。など、どんなことでも褒める習慣を大人も心掛けてくださいね。
家でできる対処法③|遊びや活動で落ち着く力を育てる

集中力を高める活動の導入
環境設定や、その時々の声かけで、落ち着きのなさが改善することもあります。しかし、長期的な目で見た場合、根本的に改善されていることも理想ですよね。
そこで毎日コツコツと関わりを取り入れていくという活動面でも対応法もお伝えします。
段階的な集中力を高めていく
- 短時間から始める
- 「今日は絵本の時間は座っていられたね」など決められた時間だけでも座っていられるようにする
- 時計の針が1まで待っていてね、その後遊ぼうねなど、短時間の目標を決め見通しが持てるようにする
- 興味を引く教材の活用
- 視覚的に魅力的な大型絵本や仕掛け絵本を使う
- 人形や小道具を使った劇的な読み聞かせで注目を集める
- 子どもの好きなキャラクターや興味のあるテーマを取り入れる

子どもの興味を引くような活動内容、教材を検討してみることも落ち着きのなさに働きかけることができますよ。
感覚統合を促す遊び
- 前庭感覚(バランス感覚)を刺激する遊び
- バランスボード、トランポリン、ブランコなどの遊具を活用
- くるくる回る、高低差のある場所を歩くなどの遊び
- 固有感覚(体の位置感覚)を育てる遊び
- 重い物を運ぶ、引っ張る遊び
- クッションやマットに勢いよく体を投げ出す遊び
- トンネルをくぐる、狭い場所を通り抜ける遊び
「前庭感覚」=体のバランスを感じるセンサー
「固有覚」=体の位置や動きを感じる力
これらの感覚遊びは、脳の発達を促し、結果的に「落ち着き」にもつながります。
感覚統合というと少し難しく感じるかもしれませんが、考え方としては、「いろいろな動きをする活動を取り入れる」ということ。

その子が普段使わないような動きを取り入れることで、体の発達を促すことができ、落ちつきのなさが根本的に改善されていきます。
※子どもの行動が気になるという場合は、「気になる子どもの行動の意味」について解説している記事もあるので、そちらも参考にしてください。
生活習慣からアプローチする方法
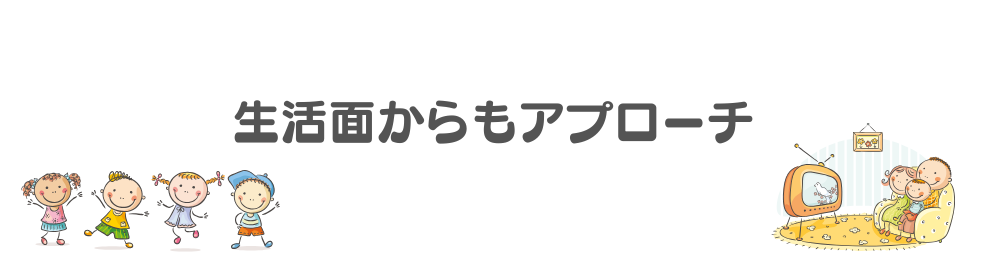
この部分は保育士さんの場合は知識として頭に入れておき、月のおたよりや保護者対応の会話などに取り入れてもらえればと思います。
睡眠・食事・メディアとの関係
落ち着きのなさは、基本的な生活習慣とも深い関係があります。近年はメディアの普及により子供たちのメディア使用率がどんどん増えている傾向にあるためそういった視点で考えてみる必要もあります。
質の良い睡眠の確保
- 十分な睡眠時間:3歳児は10〜13時間の睡眠が理想的
- 規則正しい就寝・起床時間:体内時計を整えることが重要
- 就寝前のルーティン:入浴→絵本の読み聞かせ→就寝など、毎日同じ流れを作る
睡眠不足は注意力低下や多動性の増加に直結します。特に寝る前2時間は強い光(特にブルーライト)を避けましょう。
忙しい毎日かもしれませんが、生活を共にする大人が、子どもの生活スタイルに合わせた生活にしてあげるということも、とても大切な工夫の一つです。
バランスの良い食事
- 砂糖や添加物の摂取を控える:過剰な糖分は興奮状態を引き起こすことも
- タンパク質と良質な脂質を含む朝食:脳の働きを安定させる効果があります
- 規則正しい食事時間:血糖値の急激な変動を防いだり、生活のリズムを整えることも大切です
メディア接触の管理
- スクリーンタイムの制限:WHOは3〜4歳児で1日1時間以内を推奨されています
- コンテンツの選択:早い場面転換や刺激の強い映像は避けるようにしましょう
- 受動的視聴ではなく対話型の活用:大人と一緒に見て、対話しながら楽しむ
メディアの時間が長くなればなるほど、それ以外の活動への集中力が低下していくとも言われています。‟脳が未発達な子どもにはメディアは刺激の多いもの”という認識をもち、できる限る減らしていけるといいですね。

これは過去の経験上の話ですが、落ち着きのない子、集中力の乏しい子はメディアを多くみている傾向にあり、その時間を減らすことで、集中力の持続が長くなったお子さんもいらっしゃいましたよ。
以上のような内容は、保護者への負担が大きくなる傾向にあり、なかなか改善することは難しいことだと思います。なので、「必ず取り入れる」のではなく、できることから、少しずつ生活に取り入れていけるようにするといいですよ。

3歳であれば、少しずつ言われていることも理解できるようになってくるので、園では「テレビやゲームではなく、絵本を読んだりする時間を増やすといいよ」など、子ども本人に伝えていくことを意識してみてください。
保護者・園との連携

一番忘れてはいけないのは、大人間の連携です。困っていることの共有、園での関わり方、おうちでの過ごし方などを日々の会話で取り入れていくようにしましょう。
子供を取りまく大人が一貫した関わりをすることは、落ち着きのなさだけではなく、子どもへの混乱も減り、過ごしやすさがupすることにつながっていきます。
保護者対応が苦手な方はコチラも参考に↓↓
 現役保育士直伝!!保護者対応がしんどい!疲れた!対応の8つのコツを大公開
現役保育士直伝!!保護者対応がしんどい!疲れた!対応の8つのコツを大公開
効果的な情報共有の方法
子どもの落ち着きのなさに対応するには、保護者と保育園・幼稚園の連携が不可欠です。
家庭と園での情報共有
- 具体的なエピソードの共有:「今日は10分間集中して製作活動に取り組めました」など
- 効果的だった対応方法の共有:「タイマーを使うと、時間の見通しが立ちやすいようです」
- 一貫した対応:家庭と園で同じ声かけや対応を心がける
このように、家庭と園とで情報を共有し、どの環境でも同じ関わりができるようにすることも必要です。
どちらか一方だけの対応よりも、双方からの働きかけがあればより効果を感じることができるようになることも覚えておいてくださいね。
まとめ:3歳児の落ち着きのなさは成長の証ということも
3歳児の落ち着きのなさは、多くの場合、脳の発達過程における自然な姿です。適切な環境設定と関わり方の工夫により、徐々に自己コントロール力を身につけていきます。
- 環境を整える
刺激の調整、空間の区切り、動と静のバランス - 効果的な声かけ
具体的で肯定的な言葉、視覚サポートの活用 - 活動の工夫
集中力を高める、感覚統合遊び - 生活習慣の見直し
睡眠、食事、メディア接触の管理 - 連携の強化
家庭と園での情報共有、必要に応じた専門家への相談
子どもの特性を理解し、その子に合った支援を行うことで、「落ち着きのなさ」は徐々に改善していくこともあります。一人ひとりの発達のペースを尊重し、焦らずに温かく見守る姿勢が最も大切です。
あなたのお子さんや担当しているお子さんの成長を、ぜひ温かい目で見守ってください。そして、この記事の対処法をぜひ試してみてください。きっと、少しずつ変化が見えてくるはずです。
今は落ち着かないように見えても、成長とともに「集中できる時間」は少しずつ増えていきます。子どもは、自分のペースで「落ち着ける力」を育てている途中なんです。
今日からできることを、ひとつずつ。その積み重ねが、きっと明日の笑顔につながります🌱
子どもの発達について、周りの人よりちょっと詳しくなれるチャンス!
今、人気急上昇中の資格を知っていますか?
それは、 「子ども発達障がい支援アドバイザー」という資格。この資格は資格サイト最大級のユーキャンが手掛ける、子どもの発達支援に関する資格です。
発達に課題のある子どもへの適切な関わり方を学ぶことができるので、保育士さんはもちろん、子育て中にパパママにもピッタリ!と受講者が年々増加傾向にあるんです。
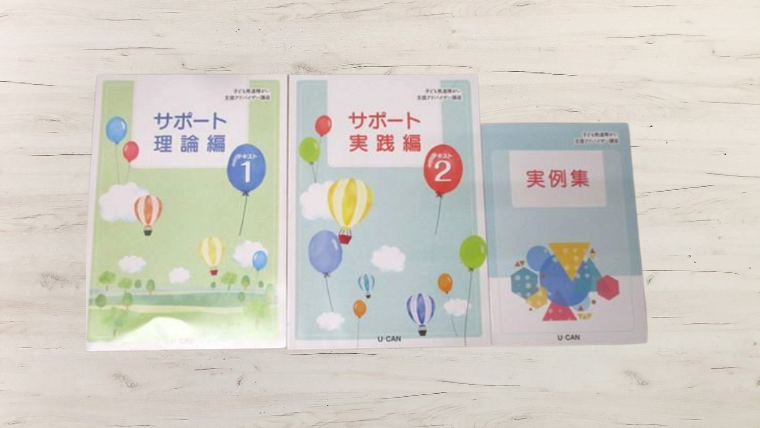
子どもの発達支援についての資格業界は、今後どんどん需要が高まっていくことが考えらます。
他の保護者や、保育士さんと差を付けたいなら今がチャンス!
ユーキャンの「子ども発達障がい支援アドバイザー」とは?仕事に生かせる?
子どもの発達や関わり方について、他にも知りたいことがあれば、コメント欄でお気軽にご質問ください。保育のプロとして、できる限りお答えします。
関連記事も人気です
 3歳の発達障害チェックリスト|気になる行動と対応策
3歳の発達障害チェックリスト|気になる行動と対応策
 保育現場における「気になる子」の特徴は?わかりやすく言うとどんな子?
保育現場における「気になる子」の特徴は?わかりやすく言うとどんな子? 
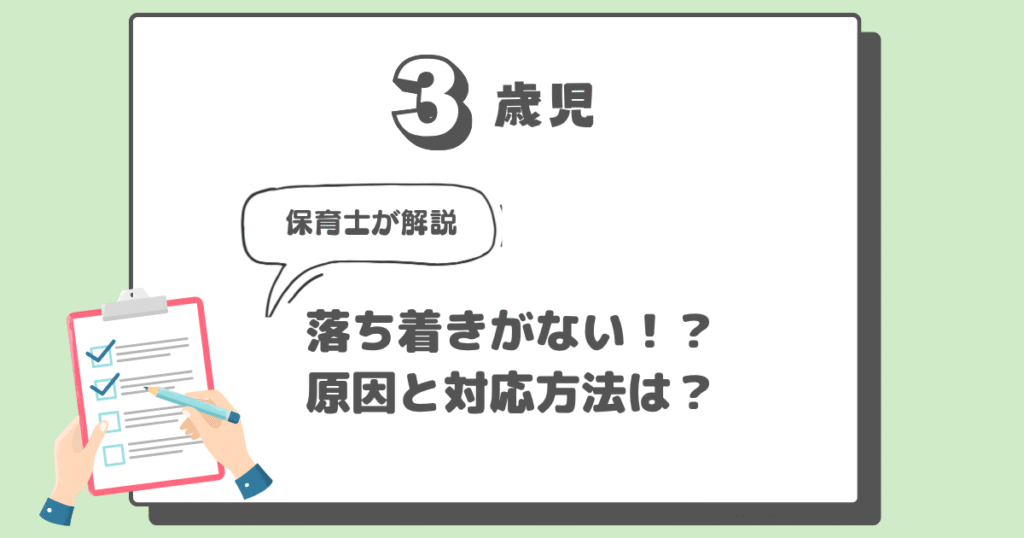

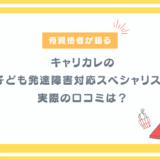
I have been absent for some time, but now I remember why I used to love this website. Thanks , I’ll try and check back more often. How frequently you update your web site?
You actually make it appear really easy together with your presentation but I to find this matter to be actually one thing which I believe I’d never understand. It kind of feels too complex and very vast for me. I’m taking a look ahead for your subsequent publish, I will try to get the hold of it!