🎉 6月2日までの期間限定キャンペーン 🎉
\最短3ヶ月で資格取得!/
資格サイト大手のユーキャン
※無料資料請求あり(6月2日まで)
「加配保育士」という言葉、初めて聞く方も多いのではないでしょうか?
発達支援や個別配慮の必要性が高まる現代の保育現場で、「加配」という役割が注目されています。
医療の進歩や発達障害への理解が深まるにつれ、様々な特性を持つ子どもたちが共に育つ環境づくりが求められるようになりました。
保育士として新たなキャリアパスを探している方や、発達支援に興味がある方に向けて、加配保育士の仕事を徹底解説します。
「どんな仕事なの?」「普通の担任と何が違うの?」「自分に向いている?」そんな疑問にお答えします!
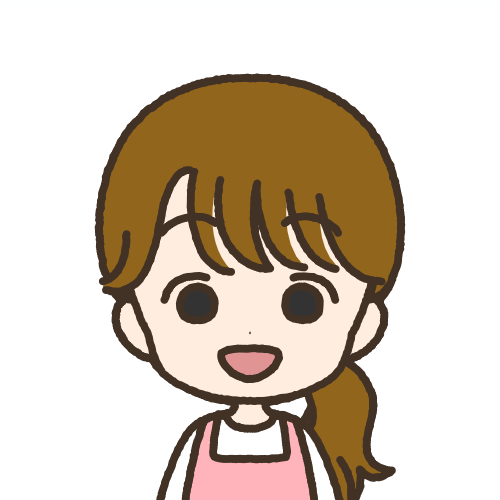
この記事を読めば、加配保育士という専門性の高い仕事の全体像がつかめるでしょう。
目次
加配保育士とは?基本を知ろう
「加配」の意味と役割をわかりやすく解説
「加配」とは、支援が必要な子どもに対して追加で保育士を配置することです。通常の保育士配置基準に「加えて」配置されるため「加配」と呼ばれています。
たとえば、3歳児クラスでは保育士1人に対して子ども20人までという配置基準がありますが、特別な支援が必要な子どもがいる場合、その子どものために追加で保育士を配置することがあります。これが「加配保育士」です。
加配保育士の主な役割は、子どもの特性に合わせた個別支援です。その子どもが集団生活の中でうまく過ごせるよう、特性を理解した上で適切なサポートを行います。
施設種別によって加配の仕組みには違いがあります:
- 認可保育園:自治体の審査を経て加配認定が決まり、補助金が出ることが多い
- 認定こども園:保育部分は保育園と同様、教育部分は幼稚園と同様の仕組み
- 幼稚園:「特別支援教育支援員」などの名称で配置されることが多い
- 小規模保育:地域や施設によって対応が異なる
通常の担任・フリー保育士との違い
保育現場には様々な役割の保育士がいますが、それぞれの役割を整理すると
| 役割 | 主な業務 | フォーカス |
|---|---|---|
| 担任保育士 | クラス全体の保育計画と運営 | クラス全体の成長発達 |
| フリー保育士 | クラス全体のサポート、補助 | 担任のサポートとクラス運営の円滑化 |
| 加配保育士 | 特定の子どもへの個別支援 | 特定の子どもの発達支援と集団参加 |
このようになっています。
それでは、一日の業務の違いを具体的に見てみましょう。
- 朝の受け入れ(全園児対応)
- 朝の会の進行
- 活動の計画と実施
- 給食の準備と指導
- 午睡の見守り
- おやつの準備と提供
- 帰りの会の進行
- 保護者への連絡・引き渡し
- クラス全体の記録作成
- 複数クラスの朝の受け入れ補助
- 活動準備のサポート
- 給食配膳の補助
- 午睡チェックの分担
- おやつ準備の補助
- 複数クラスの帰りの対応補助
- 必要な記録の補助
- 担当児の受け入れと状態確認
- 朝の会での個別サポート
- 活動への参加支援(必要に応じて別メニュー提供)
- 給食時の個別サポート
- 午睡への入り方支援
- おやつ時の個別サポート
- 帰りの支度の個別サポート
- 担当児の記録作成と情報共有
担任保育士、フリー保育士、加配保育士それぞれの一日の過ごし方の違いは以上のようになっています。
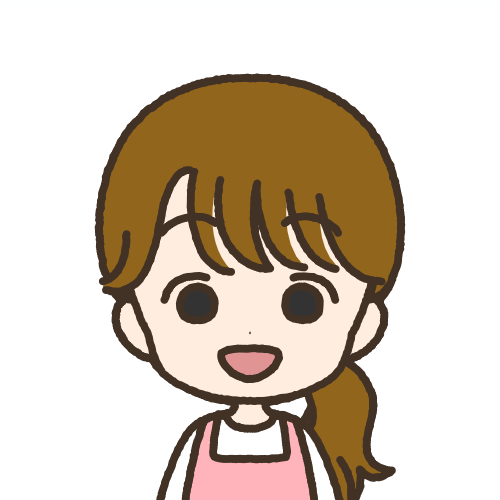
加配保育士は主に ‟個別のサポート” という役割が多いですね。
加配保育士の一日の流れを知りたい!そんな方はコチラの記事で詳細を確認できます。
▶加配保育士の一日を解説|仕事内容・役割・動き方とは?
加配保育士がつく子どもの対象は?
加配保育士がつく対象となるのは、主に以下のような子どもたちです。
- 発達障害・グレーゾーンの子ども
- 自閉スペクトラム症(コミュニケーションの難しさ、こだわりが強いなど)
- ADHD(注意散漫、多動性、衝動性がある)
- 知的障害(発達の遅れがある)
- 言語発達の遅れがある
- 感覚過敏がある(音、光、触感などに敏感)
- 医療的ケアが必要な子ども
- てんかんがあり発作の可能性がある
- 重度の食物アレルギーがある
- 喘息などの持病がある
- 身体的な障害があり移動や活動に配慮が必要
- 情緒面で配慮が必要な子ども
- 分離不安が強い
- パニックになりやすい
- 集団適応に時間がかかる
- 感情コントロールが難しい
このように、‟集団生活を送るにあたって、大人の援助をできるだけ近くで受ける必要がある子” が加配保育士が付く対象児です。
加配を付けるかどうかという点に関しても、保護者の自己判断や、園の自己判断で勝手につけることはできません。
加配認定の仕組みは自治体によって異なりますが、一般的なプロセスとしては
- 保育園・幼稚園からの相談・申請
- 巡回相談員による観察
- 専門家による審査会
- 加配認定の決定と補助金の算定
といった流れになることが大多数。ただし診断書が必須となる地域もあれば、そうでない地域もあります。
加配保育士に求められる専門性とスキル
では、加配保育士にはどのようなスキルが求められるのでしょうか?
実際の現場で必要とされる力について、もう少し具体的に見ていきましょう。
子どもの特性を理解する力
加配保育士には、担当する子どもの特性を理解し、適切な支援を行うための知識とスキルが求められます。そのためにも、
- 発達障害の基礎知識
- 行動観察のポイント
- 個別支援計画の作成と実践
といったスキルが必要になります。
加配保育士として大切なのは、一人ひとりの子どもを深く理解し、その子に合った関わり方を見つけていく力です。
たとえば、ADHD(注意欠如・多動症)の子どもは、集中が続きにくかったり、衝動的な行動をとりやすい特性があります。ASD(自閉スペクトラム症)の子どもは、急な予定変更が苦手だったり、特定の刺激に敏感なこともあります。こうした特性を知らずに関わってしまうと、意図せず子どもを追い詰めてしまうこともあるのです。
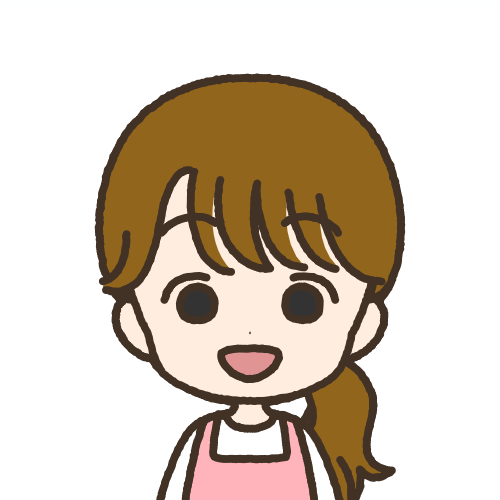
発達障害の基礎知識は、加配保育士にとって不可欠な土台ということです。こうした特性の理解を土台に、どのように支援していくかを考えることが、加配保育士の重要な役割です。
子どもが「どんな場面で困るのか」「どんな前触れがあるのか」「どうすれば落ち着けるのか」などを日々観察しながら理解を深めていく必要があります。
その上で、個別支援計画を立て、子どもに合った支援の目標や方法を具体的に考えていきます。計画は一度立てたら終わりではなく、実際の様子を見ながら柔軟に修正していくもの。担任や他の職員と連携しながら、チーム全体で子どもを支えていく姿勢も重要です。
こうした丁寧なプロセスの積み重ねが、子どもにとって安心できる環境をつくり出し、「できた!」「わかった!」という経験につながっていきます。
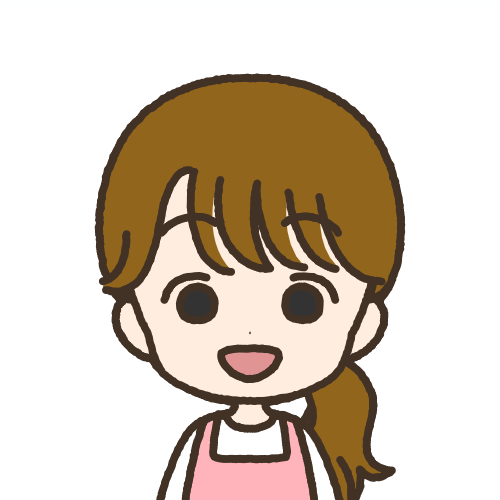
加配保育士は、子ども一人ひとりの可能性を信じて支える、専門職なのです。
連携力・コミュニケーション能力
加配保育士は、子どもと関わるだけでなく、クラス担任や保護者、専門機関など、さまざまな立場の人との「橋渡し役」としても重要な役割を担っています。
そのため、高い連携力とコミュニケーション力が求められます。
①担任保育士との情報共有と役割分担
加配はあくまでサポート役ではありますが、日々の連携がなければ子どもにとって一貫性のある支援ができません。
担任の保育方針や子どもへの接し方を尊重しつつ、必要な情報はしっかりと伝えることが大切です。
たとえば、朝や帰りのちょっとした引き継ぎ、週案や月案に加配の視点から意見を加えるなど、小さな積み重ねが信頼関係につながります。
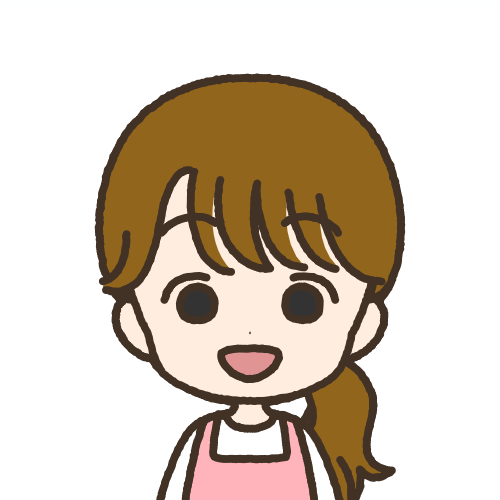
運動会や発表会などのイベント時にも、子どもの混乱を防ぐため、あらかじめ役割分担を明確にしておくなどの見通しと計画も必要です。
②保護者との信頼関係の構築方法
加配保育士は、子どもの変化を一番近くで見ている存在でもあります。
そのため、具体的なエピソードを交えて伝えたり、ポジティブな面を中心に話すことで、保護者の安心感につながります。
また、子どもの様子を一方的に伝えるのではなく、家庭での様子を聞く姿勢を持つことも大切です。
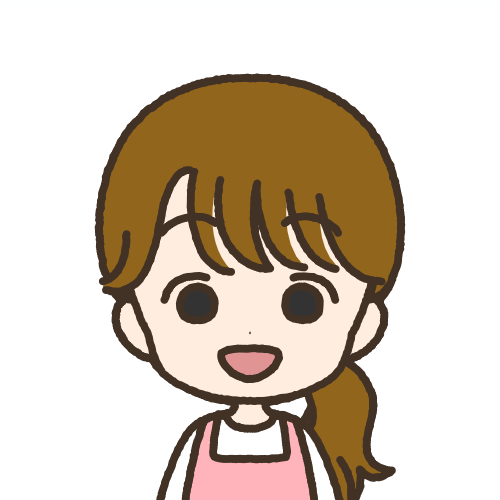
お互いの情報を共有し合うことで、子どもをより深く理解し、支援の方向性をそろえることができるので、そういったスキルも大切ですね。
③加配という立場でのコミュニケーションの難しさと工夫
加配保育士は、クラス全体を見守る担任とは立場や視点が異なります。
ときには、担任と意見が違う場面もあるかもしれません。
そんなときは、相手の立場を尊重しながら、専門的な視点をうまく伝える工夫が必要です。
また、他の保護者からの質問への対応や、チーム内での空気を読む力も問われる場面があります。
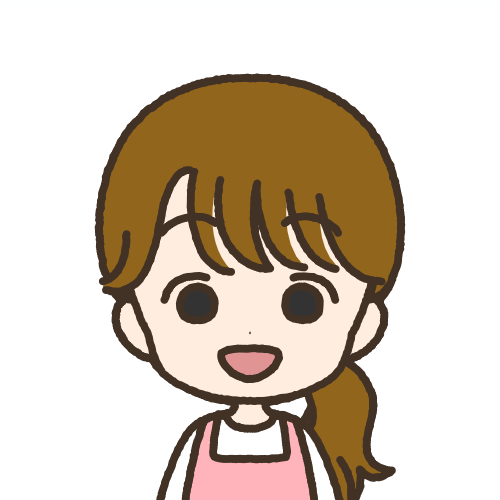
加配保育士は子どもの「代弁者」であると同時に、周囲とのバランスをとる存在でもあるのです。そのため、相手の気持ちを考えたり、配慮したりするコミュニケーション能力も必要になってきます。
④専門機関との連携
子どもの状況によっては、児童発達支援センターや療育機関、医療機関などと連携しながら支援を行うこともあります。
たとえば、巡回相談に来た専門家のアドバイスをもとに、保育の中でどんな工夫ができるかを担任や園長と相談したり、
外部からの情報をうまく現場に落とし込んでいく役割も求められます。
こうした複数の立場と丁寧に向き合いながら、子どもにとって最適な支援を整えていくのが、加配保育士に求められるもう一つの専門性です。
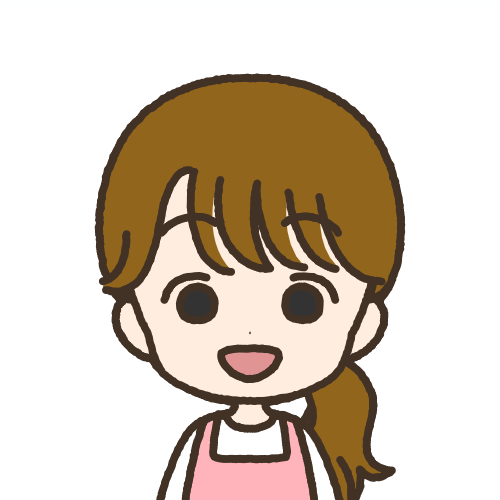
このように、加配保育士には子どもと丁寧に関わる力だけでなく、周囲との円滑な連携を築くコミュニケーション力が不可欠ということです。
柔軟な対応力と自己調整力
加配保育士は、想定通りにいかない日々の中で、瞬時に判断し、臨機応変に対応していく力が必要です。
支援のマニュアルが通用しない場面も多く、状況に応じた柔軟な発想と冷静な行動が求められます。
- 予測不能な状況への対応力
- 子どもの状態に合わせた支援方法の微調整
- 自分自身のストレスマネジメント
こうしたスキルも、加配保育士として実践していくうちに、欠かせないものになってきます。
①予測不能な状況への対応力
支援対象の子どもたちは、パニックや感情の爆発、突発的な行動をとることがあります。
例えば、突然大きな音に驚いてパニックになったとき、周囲の職員や子どもたちが混乱しないよう、落ち着いてクールダウンに導く力が必要です。
また、急な体調不良や刺激への過敏反応に対しても、いち早く気づき、適切に対応することが求められます。
②子どもの状態に合わせた支援方法の微調整
一人ひとりのその日のコンディションや気分によって、支援の方法をこまかく調整する必要があります。
たとえば、集団活動の中でうまく参加できない様子が見られたときは、無理に合わせようとせず、個別対応に切り替えたり、少し距離を置いた関わりに変更したりすることもあります。
「今日はここまで」と引くタイミングを見極めるのも重要な支援です。
子どもの中に成功体験を積み重ねてもらうためには、ハードルを調整し、「できた!」という気持ちを育てる関わりが求められます。
③自分自身のストレスマネジメント
加配保育士は、常に高い集中力と観察力を持って子どもに向き合っています。
だからこそ、心身の消耗も大きく、自己調整力=セルフケアの力が欠かせません。
子どもの小さな成長を一緒に喜べる視点を持つこと、保育チームの中で定期的に相談できる関係をつくること、
そして、自分を責めすぎずに「今日はここまで頑張った」と区切る習慣など、日々のメンタルケアが加配保育士を長く続けるためのカギになります。
こうした柔軟な判断力と自己管理の力は、子どもに安心感を与え、信頼関係を築く土台となります。
一方で、それらは加配保育士自身を守るためにも、欠かせないスキルなのです。
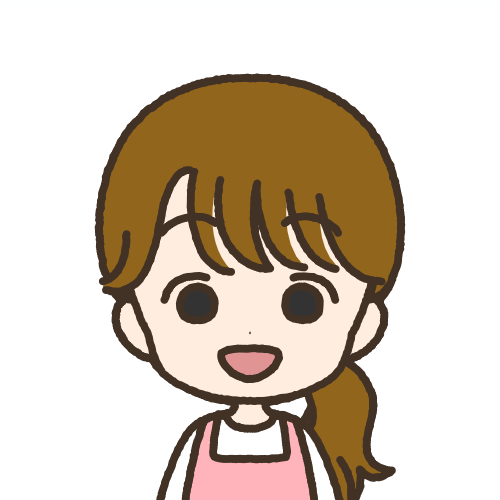
加配保育士は、日々変化する現場で冷静に対応し、自らの心も守る“しなやかさ”が求められるのです。
加配保育士に向いている人・向いていない人
加配保育士の仕事内容や必要なスキルを理解した今、「自分にもできるかな?」「向いているのかな?」と感じた方も多いかもしれません。
ここでは、加配保育士に向いている人・苦労しやすい人の特徴を具体的にご紹介します。
自分の強みや価値観と照らし合わせながら、ぜひ読み進めてみてください。
向いている人の特徴
- 一人ひとりの子どもをじっくり観察するのが好きな人
・子どもの小さな変化に気づける観察力がある
・行動の背景にある気持ちを想像できる
・じっくり関わることに喜びを感じる
・「なぜ?」を常に考える好奇心がある - 小さな成長や変化に気づき、喜べる人
・大きな成果よりもプロセスを大切にできる
・「できた!」の瞬間に共感できる
・0から1への変化を価値あるものと感じる
・長期的な視点で子どもの成長を見守れる - 臨機応変に対応できる柔軟性がある人
・計画変更を受け入れられる心の余裕がある
・「今できること」を見つける力がある
・失敗を学びに変えられる前向きさがある
・多様な方法を試せる創造性がある - チームで協力することを厭わない人
・情報共有を大切にできる
・自分の考えを伝えつつ、他者の意見も尊重できる
・「私だけ」という意識ではなく「みんなで」という意識がある
・相談することに抵抗がない
苦労するかもしれない人
- 決まったルーティンを好む人
・予定通りに進まないことにストレスを感じやすい
・変化への対応に時間がかかる
・「こうあるべき」という固定観念が強い
・想定外の事態に不安を感じやすい - すぐに結果を求めてしまう人
・短期間での成果を期待してしまう
・子どものペースを待つことが難しい
・「できない」ことにフォーカスしがちになる
・小さな変化を見逃しやすい - 複数の大人と連携するのが苦手な人
・一人で完結させたい思いが強い
・意見の相違に不安を感じる
・自分の考えを伝えることに苦手意識がある
・他者の保育観を受け入れることが難しい
この項目に当てはまる方は…
「じっくり関わる保育がしたい」「困っている子を支えたい」という思いがある方には、加配保育士という働き方はきっとやりがいに満ちた選択肢になるはずです。
一方で、「向いていないかも…」と思った方も、すぐにあきらめる必要はありません。大切なのは、自分の苦手を知り、サポートを受けながら学んでいく姿勢です。
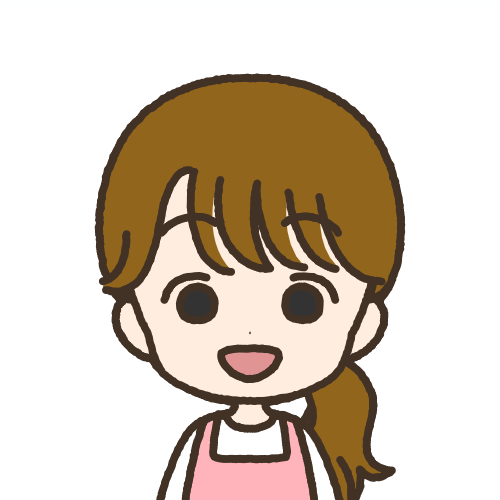
「向き不向き」よりも、「どんな保育士でいたいか」を考えるきっかけにしてみてください。
まとめ:加配保育士は、子どもに寄り添う“橋渡し役”
加配保育士は、発達や行動面に特性のある子どもたちと、その周囲をつなぐ「橋渡し役」です。
専門的な視点と、保育現場ならではのあたたかさの両方が求められます。
すぐにできるようになるものではありませんが、学びながら、子どもと共に育っていける職種でもあります。
「もっと知りたい」「やってみたいかも」と感じた方は、まずは加配保育に関する学びを始めるところから、一歩を踏み出してみてはいかがでしょうか?
もっと知りたい方へ:加配保育士に役立つ記事・学び
加配保育士として働くには、知識や視点を少しずつ深めていくことが大切です。
ここでは、加配保育に関わるうえで役立つ関連記事や、今すぐ始められる学びの方法をご紹介します。
▼加配保育士として働くうえで不安がある方は
加配保育士がしんどい理由と、続けるための対処法
→「しんどい…」と感じやすい原因と、現場で実践できる対応策をわかりやすく解説しています。
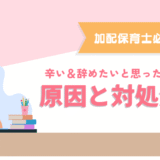 加配保育士がつらい…辞めたいと思ったときに読んでほしい「しんどい理由」とその対処法
加配保育士がつらい…辞めたいと思ったときに読んでほしい「しんどい理由」とその対処法
▼具体的にどんな支援が求められる?と思ったら
加配保育士の対応のコツ|タイプ別の支援方法と保護者対応も
→子どものタイプ別に、実践的な支援方法や保護者との関わり方を詳しくまとめています。
 子どもとの関わり方に悩む加配保育士必見!求められることとは?
子どもとの関わり方に悩む加配保育士必見!求められることとは?
学びを深めたい方へ:資格で得られる知識とは?
加配保育士としてのスキルや知識をさらに高めたい方には、発達支援に特化した資格講座もおすすめです。
子どもの発達特性や支援方法について体系的に学べるため、実践での対応力にもつながります。
【初心者にもおすすめ】
子ども発達障がい支援アドバイザー(ユーキャン)
→現場経験が少なくても学びやすいカリキュラム。加配保育士にも活かせる知識が詰まっています。
【もっと深く学びたい方向け】
子ども発達障害対応スペシャリスト(キャリカレ)
→保護者対応や支援計画の立て方まで幅広く学べ、現場の「困った!」に強くなれます。
加配保育士は、子どもたちの「できた」を一緒に見つけていく、とても尊い仕事です。
大変なこともありますが、それ以上にやりがいを感じられる瞬間もたくさんあります。
「私にもできるかもしれない」
そう思った今が、第一歩を踏み出すタイミングです。
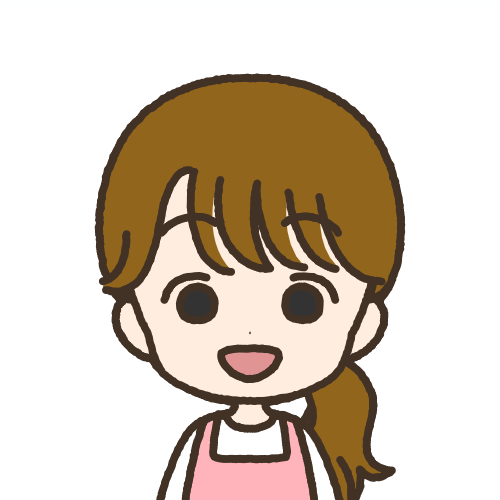
無理なく、自分らしく学びながら、子どもたちの味方になれる準備を始めてみませんか?
気になる講座があれば、まずはチェックしてみてください
資格を取りたいと思った「今」の気持ち、大切にしてほしいなと思います。
資料を見ながら、自分に合う講座を見つけてみてください。





[…] 加配保育士についてもっと知りたい方は、こちらの詳細記事を参考にしてください。▶加配保育士とは?具体的な役割の詳細 […]