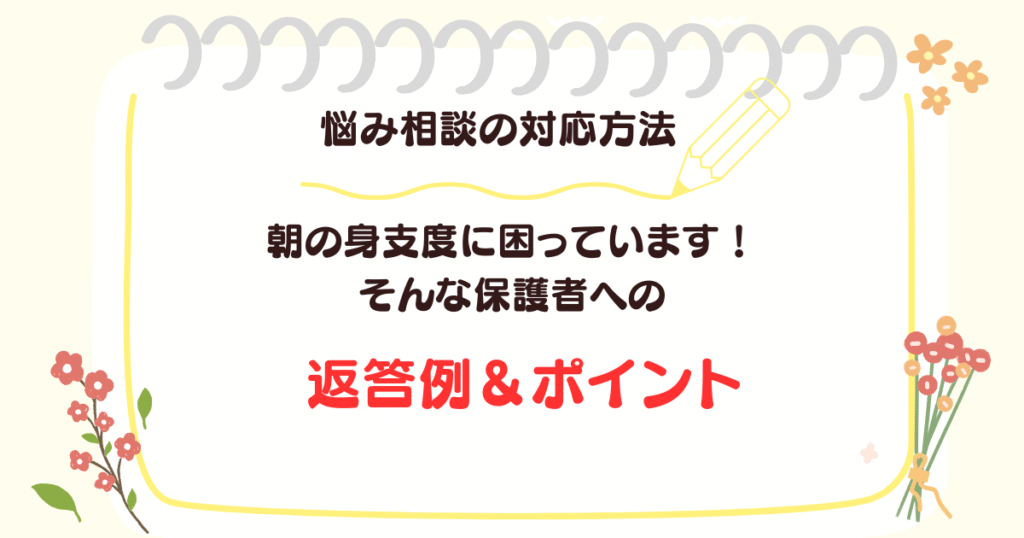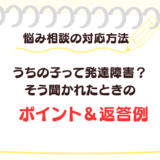※本記事にはプロモーションが含まれています
保護者に「朝の支度がスムーズにいかなくて…」と相談されたとき、どう答えていますか?
「早くしないと!」と急かしてもなかなか動いてくれない。そんなとき、どんな言葉をかければいいのか迷いますよね。
今回は、朝の支度をスムーズに進めるための効果的な声かけ例と時短のコツを年齢別に紹介します。

この記事を参考に保護者の方への悩み相談に対し、上手に答えられるようになってもらえると幸いです!
目次
朝の支度が進まない理由
子どもが朝の支度に手間取るのには、いくつかの理由があります。
- 眠くて体が思うように動かない
- 何をすればいいのか分かっていない
- 遊びに気を取られてしまう
- 自分でやりたい気持ちと、甘えたい気持ちが葛藤している
これらをふまえて、年齢ごとに適した対応をしていくことが大切です。
【年齢別】朝の支度をスムーズにする対応方法
悩み相談の対象となる子の年齢によって対応方法が変わってくるので、ここからは年齢別に解決方法についてお話していきますね。
読みながら
この方法ならおすすめできそう!
〇〇君にはこの方法がいいかも!
など、実際のお子さんを想像してみてください。
2~3歳:イヤイヤ期を考慮した関わり

2~3歳は俗にいう「イヤイヤ期」真っ只中!何を言っても「イヤ」と返されてしまうこともしばしば・・・
「着替えるよ」
→「嫌っ!!!」
「ご飯食べて」
→「嫌っ!!!!」→「ご飯をポ~イッ!!」→「ウロウロ・・・」
「保育園行くよ」
→「行かないもんっ!」
「・・・もう、いい加減にして!!」
こんな朝のやり取りが目に浮かびます。
2~3歳頃の朝の支度はまだ、「自分でやる!」という気持ちが育ち始めたばかりで、うまくいかないことも多い時期。集中が続かなかったり、できなくて怒り始めてしまったり・・・
そんなときに効果的な方法を紹介します!
選択肢を与える
そこでおすすめなのは、選択肢を用意して子どもに決めさせるという方法。
「今日はパンダさんTシャツとクマさんTシャツ、どっちにする?」
「靴下を履くのと、ズボンを履くの、どっちを先にする?」
「新幹線みたいにする?飛行機くらい速くする?」
「青いコップと黄色いコップ、どっちでお茶飲む?」
選択肢を出すことで、「やらされている感」が減り、「自分で決めたこと」という意識に変わるのでやる気が出ることもあります。
自分でやりたい!という欲求を「自分で決めた」に変換し、気持ちを満たしつつイヤイヤな気持ちを切り替えるという考え方ですね。
やる気スイッチを入れる
これは私が保育現場でも良く活用している方法です。
「どっちが速いか競争ね」
「着替えたら、お気に入りの絵本を読もう」
「10数える間にできるかな?」
「あ~どうやってやるのか、ママ分からないや~」
こんな風に、子どもが「自分でやりたい」と思えるような関わりをしてみてください。
競争したり、ゲーム感覚で楽しく取り組んだりするとこで、「イヤイヤ」の感情が少なくなり、朝の身支度がスムーズにできるようになりますよ。
どうしても難しい日
まだまだ2~3歳は、ママに甘えたいばかりの時期です。もし、いろいろ試してみてもどうしても難しい日は、
「ママと一緒にやろうね」
「やりたくない時もあるよね」
と、子どものペースに合わせ、嫌な気持ちを受け入れてあげるといいですね。
忙しい朝に「イヤ~」となってしまうと、ママもイライラしてしまうこともよく分かります。
そんなママの気持ちを十分にくみ取りつつ、子どもの成長を一緒に見守っていけるようサポートしていきたいですね。
4~5歳:「〇〇できたね!」で成功体験を積ませる

4~5歳は身辺のことは徐々に「自分でできる」ようになってきますが、気が散って準備が進まないことも。 この時期には、できたことを言葉にして褒めるのが効果的です。
出来たら褒める(スモールステップで)
まずはその日にできたことを、どんな些細なことでもいいので褒めてあげましょう。
「シャツを自分で着られたね!あとズボンを履いたら準備完了だよ」
「靴を履くの、昨日より早くなったね!」
「カバンにお弁当を入れられたね!すごいね!」
「時計の針が7のところに来る前に靴を履けたね!」
「ちゃんとやって!」と指示するより、「できたこと」を認めてあげることで、次も頑張ろうという気持ちが育ちます。
またできたことを褒めてあげることで、成功体験を積み重ねていく関わりが効果的。
やる気スイッチを入れる声かけ
2~3歳の頃と違って、「できないからやらない」ということは、もうほとんどない時期。つまり「できるけど、やりたくない」ということ。
そんな時はいかにやる気スイッチを入れてあげられるかがポイントです。
「時計の針が6になるまでに水筒の用意できるかな?」
「ママとどっちが速いか競争ね!」
「(大人がわざと間違えたことをやりながら)これであってるっけ~?」
「あれ~ハンカチの畳み方忘れちゃったな~」
「大変!時間だ!用意しなきゃ、よーいドンッ!」
「靴下って5秒で履ける?数えてみよう、1、2・・・」
紹介した声掛けの後半は、「もうママってばそんなことも分からないの!?」「私はできるよ!」と自分でできることを誇らしげにアピールしてきてくれるように仕向けてあげる方法。
これは先生たちが保育園でよく使っている声かけなので、効果抜群です!
保護者に伝えたい!朝の支度を時短するコツ
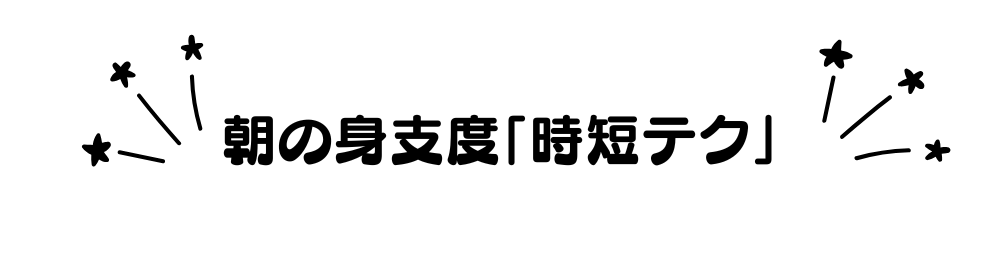
声かけ以外にも、環境を整えることで朝の支度をスムーズにできます。私が自分の子どもを育てるにあたって使っていた方法でもあります。
事前に準備をしておく
- 服を前日に用意しておく(朝バタバタしない)
- カバンの中身をチェックしておく(忘れ物防止)
- 朝ごはんのメニューを決めておく(悩む時間を減らす)
この方法はどの年齢になっても身に付けておいて損はない行動スタイルだと思っています。朝はどうしてもドタバタしがち。
「今日はパンが食べたかった~!」
「このふりかけ嫌だった~」
なんて毎朝言われたらそれはママたち大変です!
カバンの中身、着ていく服、朝ごはんのメニュー決めは夜の間にやっておくことことで、朝のドタバタがいとも簡単に改善でできます。
これは、子どもに限らず、大人も日常に取り入れることで心に余裕が持てるようになるかもしれませんね。
今日から早速取り入れていきましょう!
支度の流れを「見える化」する
それでもなお、なかなか身支度がスムーズにいかない原因は「何からやるといいのか分かっていない」というところにあるのかも・・・
そこで、やることを見える化していきましょう。
- 朝の準備リストを作る(絵カードやホワイトボードを活用)
- 動線を工夫する(着替え→トイレ→朝食の順にスムーズに動けるように)
- 時計を活用する(「長い針が6になったら着替えようね」)
字が読める年齢なのであれば、やることをホワイトボードなどに書き理解しやすいように工夫してみてください。次は何をやるといいのか、いつまでにやるといいのか・・を具体的に示してあげることで、行動の見通しが持てるようになります。
楽しく取り組む
- 「準備競争」する(「ママとどっちが早くできるかな?」)
- お気に入りの音楽をかける(リズムに乗せて着替える)
- 支度ができたらご褒美を用意する(シールを貼る・好きな絵本を読む時間を作る)
怒ってばかりいると、「朝の身支度=嫌なこと」と子どもの中にインプットされてしまいます。そこでおすすめなのが楽しく取り組める工夫をすること。
朝の忙しい時間に、そんな暇はない!という保護者の方も多いかもしれませんが、一瞬でいいので子どもの気持が盛り上がるような雰囲気にしてあげてください。
「ママできたよ!」「〇〇ちゃんの勝ちだね!」など、きっと誇らしげに準備をしてくれることでしょう。
「明日はママ負けないよ!」など次の日も競争する約束をしておくのもいいですね。
保護者へ伝えたいこと:「焦らず、できたことを認めてあげましょう」
いかがだったでしょうか?
保護者の方も、朝の時間は余裕がなくなりがちです。 ですが、「早くして!」と焦ると、子どもは逆に動けなくなることも。
「うまくいかない日もある」「全部完璧にやらなくてもOK」と思えると、心に余裕ができます。 まずは、少しずつ子どもが「できる」環境を整え、声かけを工夫することから始めてみてもらえるよう、アドバイスをしてあげてくださいね。
保護者から相談されたときは?
「朝の支度に時間がかかって…」

「お子さんは今、何に手間取ることが多いですか?イヤイヤ期の子には選択肢を出してみるといいですよ。例えば…(具体例)」
こんなふうに、年齢や状況に応じた対応を伝えられると、保護者も安心できます。
もし保護者の方から相談を受けたら、まずは悩んでいる保護者の気持をくみ取り、ねぎらい、その後保育士としての悩み相談へのアドバイスをする、という流れを基本としてくださいね。

朝の支度は、「環境+声かけ+余裕」でいとも簡単に変わります。 ぜひ、できることから試してみてくださいね。
伝える力を育もう
保護者対応に悩んだときにおすすめの本を紹介しますね。
保護者の気持ち寄り添った声掛けの仕方、対応方法などの具体例もいくつか紹介されており、一度は目を通して欲しい一冊です。
それ以外にも保護者対応のコツを本ブログでも紹介していますので、参考にしてみてください。
それでももし困っている!という先生がいましたら、コメントでもSNSでもいつでも相談受け付けています!
お気軽に【もず先生】を頼ってくださいね♪