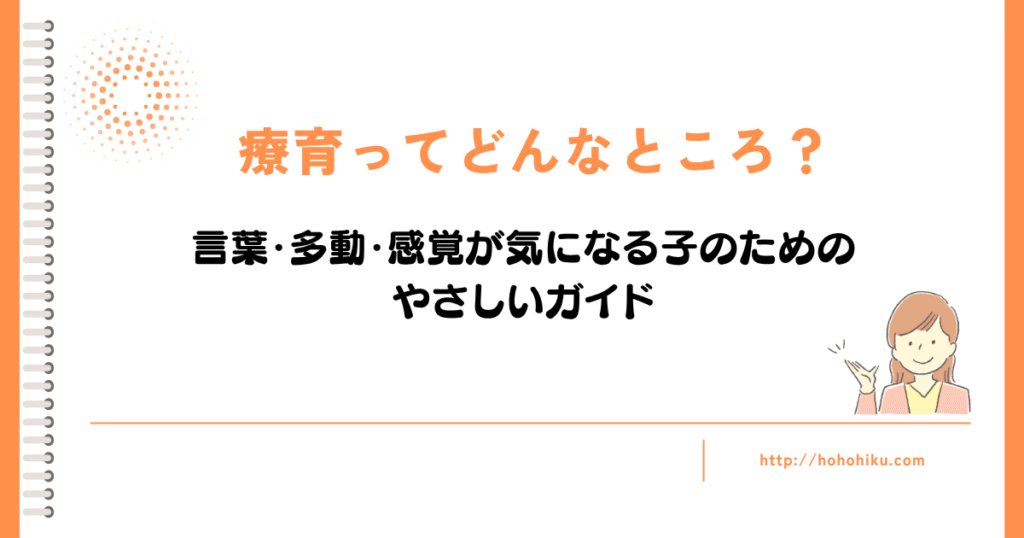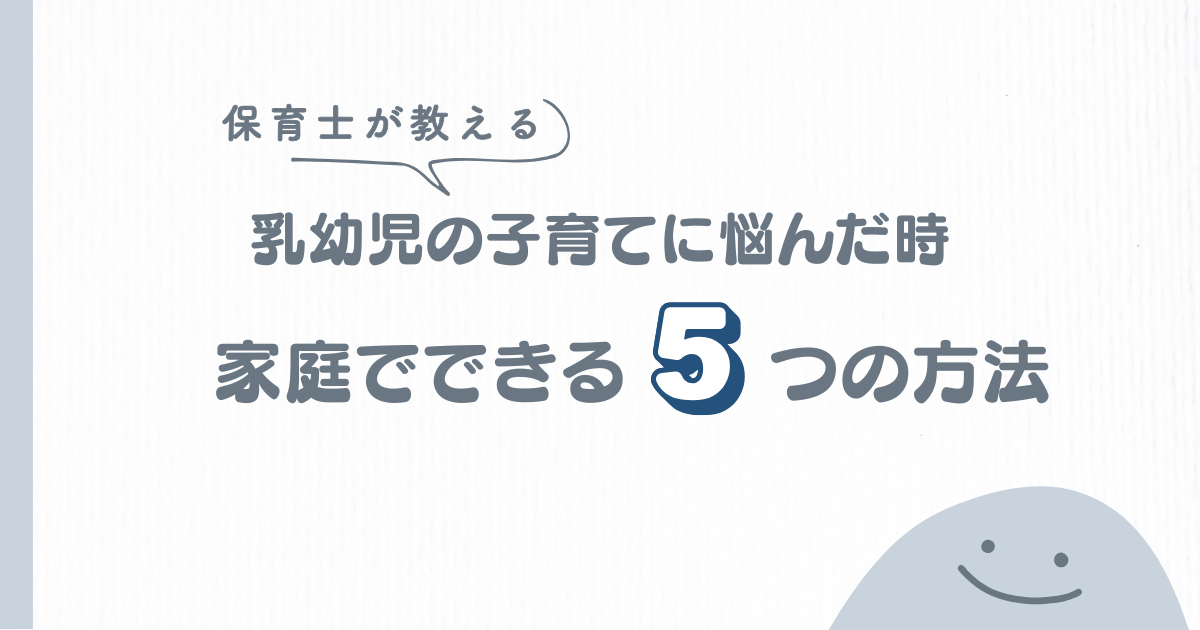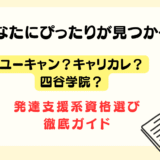※本記事にはプロモーションが含まれています
目次
はじめに:療育って何?よく聞くけど、実際はよく知らない
「療育」という言葉、最近よく耳にするようになりましたよね。保育園や健診で「療育を検討してみては?」と勧められたけれど、具体的にどんなことをするのかわからず不安に感じている方も多いのではないでしょうか。
「うちの子に本当に必要なの?」
「行ったら何をするの?」
「子どもにレッテルを貼ることになるのでは?」
「周りの目が気になる…」
「発達障害と診断されるのでは?」
そんな疑問や不安を持つのは当然のことです。

この記事を読めば、そうした不安が解消され、お子さんにとって最善の選択ができるようになります。正しい知識を持つことで、療育に対する見方が大きく変わりますよ。
この記事で分かること
- 療育で実際に行われる活動内容
- どんな子どもが通うのか、適切な年齢や通う頻度
- 療育を受けた後の変化や効果
- 家庭でできるサポート方法や、さらに学びたい方向けの情報

一つひとつ丁寧に解説していきますので、ぜひ最後まで読んでいってくださいね。
1. 療育とは?わかりやすく言うと「発達を支えるサポート」
療育とは、簡単に言うと「子どもの発達を支援する福祉的なサービス」です。
病院での治療(医療)ではなく、子どもの成長や発達をサポートする場所と考えるとわかりやすいでしょう。
対象となる子ども
以下のような子どもが「療育」の対象となる子です。
- 言葉の発達がゆっくりな子
- 落ち着きがなく、じっとしていることが難しい子
- 特定の音や触感に敏感な子(感覚過敏)
- コミュニケーションに難しさを感じる子
- こだわりが強い子
- 診断はついていないけれど、発達に凸凹がある子
- 集団生活で「ちょっと困ること」がある子
日常生活や集団生活において、「気になるな」と思われる行動が多く表れている子が主に通っています。
療育の内容
- 遊びを通した発達支援
- 運動能力を高める活動
- 言語発達を促す取り組み
- 日常生活のスキルを身につける練習
- 集団活動を通したコミュニケーションの練習

家庭や保育園では提供しにくい、専門的な視点からの支援を、一人ひとりの特性に合わせて行うのが療育の特徴です。
2. どんな子が通うの?いつから始められる?
通い始める年齢
多くの場合、1歳半健診から年少くらいの間に療育を勧められることが多いですが、気になることがあれば何歳からでも始めることができます。
近年では早期からの適切な支援が効果的だとされています。
よくある特徴
先ほど、対象となる子どもについては少しお話しましたが、具体的にどのような特徴のある子が多いのかということも知っておくといいでしょう。
これは私自身が今までに見てきた子の一例です。
- 言葉の発達がゆっくり(2歳頃になっても単語が出ない、など)
- 目が合いにくい、名前を呼んでも振り向かない
- 落ち着きがなく、常に動き回っている
- 特定の物事へのこだわりが強い
- 感覚の過敏さがある(特定の音、触感、味などに強く反応する)
同じような症状があるから絶対に療育が必要というわけではありませんが、園内で「気になる子」とされている子が割と多く通っている傾向があります。
療育を検討するきっかけ
療育に通うきっかけは日常的には訪れません。
では今現在療育に通っている子が、どのようにして通うようになったのかもお話しておきましょう。
- 親御さん自身の「何となく気になる」という直感
- 保育園や幼稚園の先生からのアドバイス
- 1歳半健診や3歳児健診での指摘
- かかりつけ医からの紹介
親御さんの「なんとなく気になる」という感覚は案外正確です。1歳半検診や3歳児検診で相談したことがきっかけという子も少なくありません。
また現在園に通っているお子さんなのであれば、保育士さんからのアドバイスで通うようになった子もたくさんいます。
もしまだ入園していない段階なのであれば、市区町村の保健センターや児童発達支援センターに。入園しているのであれば園の先生に相談してみることをおすすめします。
3. 療育って実際に何をするの?支援内容をケース別で紹介
療育では、子どもの特性や発達段階に合わせたさまざまな活動が行われます。ここでは代表的なケース別に具体的な支援内容をご紹介します。
① 言葉がゆっくりな子への支援
言葉がなかなかでなくて心配。という親御さんは私の園にも多くいらっしゃり、案外たったそれだけで?という理由で療育に通っている子もいます。そんな、言葉がゆっくりなお子さんに対しては、
- 絵カードを使ったコミュニケーション練習
- 模倣遊びを通した言葉の獲得サポート
- 音への反応や聞く力を育てる活動
- 親子での対話を促す遊びの提案
- 口の筋力を高めるトレーニング
言葉に直接働きかけたり、口周りの筋肉の未発達に働きかけたりして療育に取り組んでいきます。
② 落ち着きがない・多動傾向のある子への支援
椅子に長く座っていられない。常に動き回っている。そんなお子さんに対しては、
- 体を使ったサーキット遊び
- ルールのある遊びを通した自己コントロールの練習
- 見通しを持たせる活動(「次は〇〇をします」と事前に伝える)
- 集中できる環境づくり(刺激を減らす、座る位置の工夫など)
- 自分の身体を知るボディバランスのトレーニング
- 視野を広くするビジョントレーニング
このようなトレーニングを取り入れています。

通う療育施設によって、取り入れている方法は全く違うかもしれませんが、遊びや運動を通して、気になる行動への根本的な部分へのアプローチが一般的になっています。
③ 感覚過敏・偏食のある子への支援
ザワザワとした空間になると、落ち着きがなくなってしまう子、砂の感覚が苦手で手で触れない子、特定の食べ物を好み偏食のひどい子などには、気になる症状に合った働きかけをします。
- 感覚統合を促す遊び(ブランコ、トランポリン、砂・粘土遊びなど)
- 少しずつ慣れる練習(苦手な感覚への段階的な接触)
- 選択肢の中から自分で選ぶ経験を増やす活動
- 成功体験を重ねる工夫
このような働きかけで少しずつ苦手が減っていくようにしていきます。
実際には、療育を受けたからといって必ずしも診断がつくわけではなく、「発達を支えるための早めの環境づくり」として活用されているケースが多くあります。

療育では「できないことをできるようにする」だけでなく、子どもが「できた!」「楽しい!」と感じられる工夫がたくさんされています。遊びの中で自然と成長を促すアプローチが特徴です。
4. 費用・頻度・親の負担感ってどうなの?
通う頻度
一般的には週1〜2回程度の通所が多いですが、子どもの状況や施設によって異なります。
費用について
児童発達支援として福祉サービスの一環で行われる療育は、障害児通所支援の制度を利用できます。
自治体による助成もあり、多くの場合、月数千円程度の自己負担での利用が一般的です(世帯収入により大幅な変動あり)。また、自治体によっては無料で提供されるサービスもあります。
保護者の関わり
親のやる事は何があるの?という疑問も出てきますよね。
通う療育施設によってさまざまなのですが、
- 送迎(施設による)
- セッションの見学(施設によって参加型や見学型がある)
- 家庭での取り組みについてのアドバイスを受ける
- 定期的な面談や報告書の確認
このような役割が出てくることでしょう。送迎に関しては、学校や園まで迎えに来てくれることが多い印象です。
「平日の通所が仕事と両立しづらい」「きょうだい児の対応と重なって大変」という声もあるので、無理なく続けられる方法を施設のスタッフと相談し進めていくことができます。
5. 「通ってよかった!療育で見えた子どもの変化」
実際に療育に通われた保護者の方々の声をご紹介します。
療育を始める前と後でどのような変化があったのか、具体的な体験談から見ていきましょう。
実際の変化と良かった点
Aさんの場合:

最初は『療育』という言葉に抵抗がありましたが、実際に通ってみると、子どもが毎回楽しそうに参加していて安心しました。言葉が増え、少しずつ会話ができるようになってきています

パニックを起こすことが多かった子どもが、感情の表現方法を学び、イライラしても『今、怒ってる』と言えるようになりました。家族全体のストレスが減りました

こだわりが強く、予定変更で大泣きしていた子どもが、視覚支援カードを使うことで、少しずつ変化にも対応できるようになってきました。

子どもの特性を理解できるようになり、イライラせずに接することができるようになりました。『できないこと』ではなく『得意なこと』に目を向けられるようになったのが大きな変化です
このように子どもの姿が目に見えて変化したり、保護者が子どもの特性を理解した関わり方ができるようになったりというプラスの意見が多く出ています。
気をつけたい点・乗り越えた課題
もちろんいいことばかりではないので、こんな風に感じたよ。という保護者の意見も参考にしてください。
- 「通所の時間が限られていて、効果を感じるまで時間がかかりました。焦らず続けることが大切だと実感しています」
- 「施設によって方針や内容に差があるので、複数見学して比較することをお勧めします」
- 「仕事との両立が難しかったですが、職場に事情を話し、時短勤務を活用することで継続できました」
今までの生活にプラスαで療育施設への通所という行動が増えることは事実。
通所のための予定を合わせたり、時間を作ったりする必要も出てきます。
実際に保育士としていろいろな療育施設を見てきましたが、施設の内容は雰囲気は十人十色。まずは見学や体験利用から始めることで、具体的なイメージがつきます。一つの施設だけでなく、複数の場所を見学することで、お子さんと相性の良い場所が見つかりやすくなります。
6. 家庭でもできる!関わり方のヒント+もっと学びたい方へ
療育施設に通う前に、自宅で何かできることがないかな?と思う方には家庭でできる関わり方の記事もおすすめです。
まとめ:「うちの子、療育が必要かも…」と思ったら
療育は「特別な子のための場所」ではありません。
その子の発達に合わせて、無理なく、楽しく成長を支えていく場所です。
不安から行動へ:小さな一歩が未来を変える
「療育ってなんだか特別な感じがして不安…」
そんな気持ちになるのは当然です。でも、知ること・動くことが子どもと向き合う第一歩になります。
まずはできることから:行動プラン4つ
- まずは相談してみる
市区町村の保健センター、子育て支援センター、児童発達支援センターなどに、電話一本で相談可能です。 - 見学に行ってみる
実際の療育の様子を見ることで、イメージがぐっと具体的になります。 - 体験利用をしてみる
多くの施設では、無料または低価格でお試し利用ができます。 - 同じ経験を持つ人の声を聞く
地域の親の会やSNSのコミュニティなどで、リアルな体験談を知ることができます。

もし療育が必要ないと言われても、子どもの特性を理解するきっかけになります。
相談すること自体に、大きな意味があることを覚えておいてください。
「もっと知りたい」と思った方へ:家庭でもできる学びもあります
相談や体験を通して、「もっと子どもへの関わり方を深く知りたい」と思う方も多いでしょう。
そんな方には、家庭で学べる通信講座という選択肢もあります。
たとえば、
ユーキャンの「子ども発達障がい支援アドバイザー」講座は、
- 子どもの発達や特性への理解
- 日常の関わり方のヒント
- 保護者・保育士どちらにもわかりやすい内容
などが詰まった、自宅で無理なく学べる人気講座です。
▶ 詳しくはこちら|ユーキャン「子ども発達障がい支援アドバイザー」講座を見る
▶ ユーキャン「子ども発達障がい支援アドバイザー」講座を見る
最後に:子どもの笑顔のために、できることから始めよう
不安な気持ちを抱えたままでは、なかなか前に進めません。
でも、小さな行動ひとつが、子どもにとっての大きな支えになります。
この記事が、あなたの「次の一歩」を後押しできたなら幸いです。
子どもの「できた!」「楽しい!」という笑顔のために、一緒に考え、動いていきましょう。
市区町村の保健センター(母子保健担当)
子育て世代包括支援センター
児童発達支援センター
発達障害者支援センター(都道府県に設置)
まずは「子どもの発達について相談したい」と電話で伝えるだけで大丈夫です。
※ご注意
記事は一般的な情報提供を目的としており、お子さまの状況に応じた判断は医療機関や専門の相談窓口にご相談ください。