※本記事にはプロモーションが含まれています
「この子、もう少し支援があれば変わると思うのに…」 「保護者の方がもっと理解してくれたら…」
そんな気持ちを抱えながらも、なかなか保護者に伝えられずにいる保育士さんは多いのではないでしょうか。特に、既にどこかで発達障害の可能性を指摘されているにも関わらず、それを受け入れられずにいる保護者への対応は、保育現場でも頭を悩ませる問題の一つです。
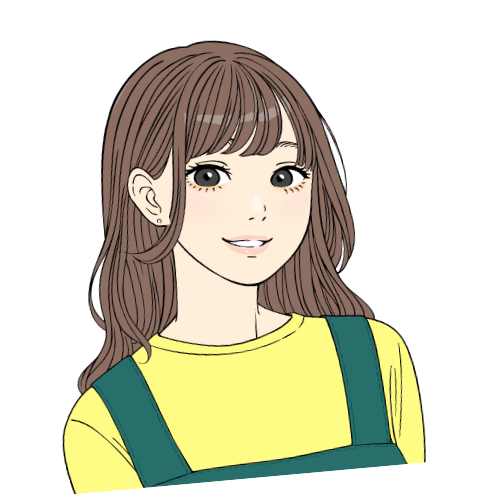
今回は、そんな「認めない保護者」との向き合い方について、保育士としてできることとできないことを整理しながら、現場のリアルな感情と共にお話ししていきます。ご自身の今の状況に照らし合わせて、考えてみてください。
目次
保育園が発達障害を指摘できない?
まず大前提として理解しておきたいのは、園が保護者に対して「お子さんは発達障害かもしれません」と直接指摘することは、絶対にありません。
もし今、「あの保護者、発達障害の可能性があるって伝えたのに、全然認めようとしないよね。」と考えているのであれば、それはNGです!
今回お話を深めていく状況は以下の通り。
- 乳幼児健診での指摘された経験がある
- 療育機関や児科医からの助言経験あり
- 周囲の人からの指摘
保護者は既に「どこかで ‟気になる行動がある” 等、言われた経験」を持っている状態で園に来ている、という状況かと思います。
発達障害を認めたくない保護者の心理とは?
保護者が発達障害を認めたくない理由は様々ですが、多くの場合以下のような感情が背景にあります。
否認の段階にいる
- 「うちの子に限って…」という気持ち
- 現実を受け入れることへの恐怖
- 将来への不安
- 年齢的なものだからいずれ良くなる
確かに気になる行動があると感じてはいるものの、今はただ小さいから、イヤイヤ期だから、大きくなったら落ち着くと思うから・・
そんな風に、今の現状は年齢のせい。環境のせい。と、目を逸らしている段階なのかもしれません。
周囲の目を気にしている
- 「発達障害」というレッテルへの抵抗
- 世間体や偏見への心配
- 他の子と比較されることへの恐れ
今ここで「発達障害」「グレーな子」と認めてしまうと、この子の将来に関わってくるのでは・・
健常児なのに、周囲から「障がい者」と見られてしまうのは耐えられない。
そんな状況にあるのかもしれませんね。
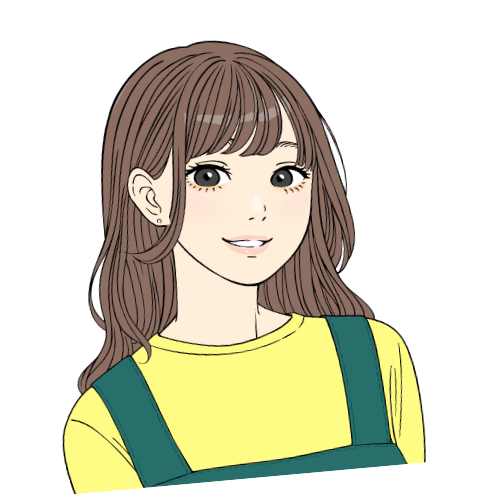
私の経験上、案外この「周囲からの目」「世間体」という部分を気にされる保護者が多いように感じています。
過去の指摘にショックを受けている
- 医療機関で言われたことが受け入れられない
- 複数の場所で同じことを言われ続けている疲れ
- 「何度も同じことを言われる」ことへの反発
園でも、保健師さんにも同じようなことを言われ、もしかしたらもう疲れてしまい現実から目を背けたい!と思っているのかも・・・
など、まずは、こうした保護者の複雑な感情を理解することがスタートラインです。
保護者に発達障害を認めてもらえない時の保育士の心構え
正直なところ、職員間では「あの保護者、あんまり認めてないよね」「もっと目を向けてあげたら、何か変わるかもしれないのに」といった話が出ることもあるでしょう。
しかし、これだけは絶対に肝に銘じてください!保育士として「保護者に認めてもらいたい」という気持ちは、一度脇に置くことが大切です。
なぜなら
- 保護者の考え方を変えることは、保育士の役割ではない
- 「認めてもらいたい」という気持ちが強すぎると、関係性を悪化させる可能性がある
- 最終的な判断は保護者が行うものである
つまり、保育士は「寄り添うことしかできない」 という現実を受け入れることが最優先で、決して「認めさせよう」なんて思わないでくださいね。
発達障害の可能性を保護者に伝えるときの言い方・例文
それでも、子どものために何かできることがあるなら伝えたい。きっとそんな時もあるでしょう。そんな時は、以下のような伝え方を心がけてみてください。
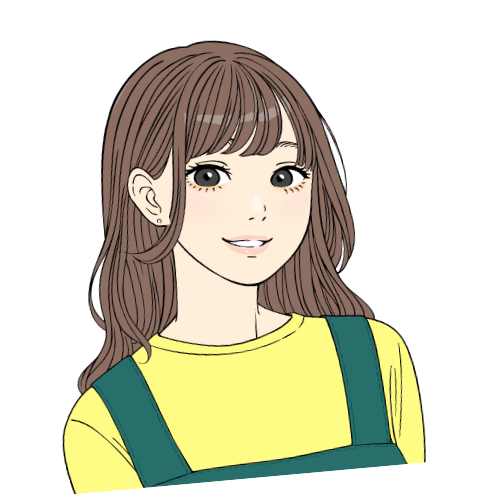
私の園でも取り入れている方法ですが、その子にとっての困りごとは最大のチャンスです。
困り感に焦点を当てる
❌「パニックになってしまう特性があるように見えます」
↓
⭕「お片付けの場面で困っているように見受けられます」
具体的な場面を共有する
❌「集中力がないですね」
↓
⭕「最近朝の会の時間、途中で立ち歩くことが多くて・・・M君は周りが気になって落ち着かないのかな?と感じています」
支援の提案として伝える
❌「検査を受けてください」
↓
⭕「園で絵カードを使って次の活動の指示をしているとうまくいくのですが、ご家庭ではいかがですか?」
認めたくない!と感じている保護者に対しての言葉選びはより慎重になりますよね。どうしても保護者に何か伝えたいと思った時は、
- 困りごとがあったその日に、「今日こんなことがあったんです」「こんな風に困っていたんです」と事実を伝える
- おうちではどうですか?と判断をおうちの人にゆだねる
この2つを意識してお話すると、関係を悪くすることなく対応ができると思います。
保護者が発達障害を受け入れない時の限界と割り切り方
どんなに努力しても、保護者の考え方や態度が変わらない場合があります。そんな時は、保育士としての限界を認める潔さも必要です。
無理に相手に伝えようとするのではなく、園でできることを取り組んでいこうというスタンスに切り替えていきましょう。
園でできることとできないこと
できること
- 園での生活を充実させる
- 子どもが困らないような環境づくり
- 可能な範囲での個別支援
- 保護者との関係性維持
できないこと
- 保護者の考え方を変えること
- 家庭での療育を強制すること
- 医療機関への受診を強要すること
- 保護者の代わりに判断すること
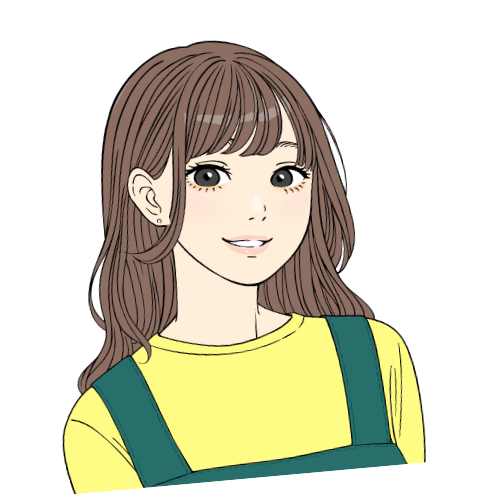
できることと、できないことへの線引きをリストアップすることで、気持ちに区切りをつけるようにしてください。いつまでも尾を引くのはNGですよ。
「他人の子」と割り切る潔さ
これは極論。
冷たく聞こえるかもしれませんが、「他人の子」という割り切りも時に必要なんです。こういった線引きも、専門職としてのバランス感覚として重要です。
- 「この子のことを最終的に決めるのは保護者」
- 「保育士は全てを背負わなくていい」
- 「ここまでやった」と思える関わりで十分
- 「できる限りのことは園でしてあげる、それ以上は無理」
私も長年保育現場に携わり、療育施設の先生方のお話も伺ってきましたが、「どれだけ工夫しても、認めない親はいる」というのは紛れもない事実。
後から、「あの時もっと言ってくれたら!」とお叱りを受けないように、できる限りの努力を記録に残し、割り切る心の技術も身に付けていく必要があります。
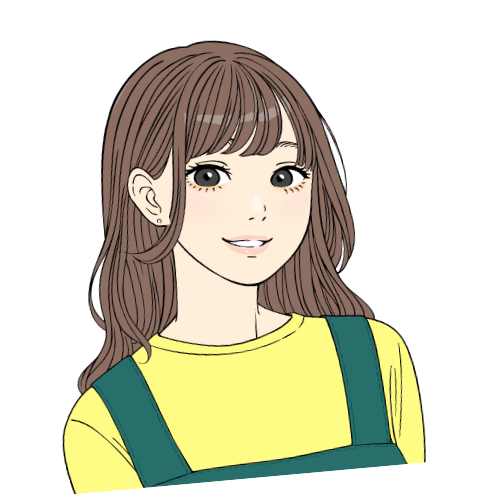
この割り切りは、優しい保育士さんには難しいかもしれませんが、保育士自身のメンタルヘルスを守るためにも必要なんです。
【具体的な対応方法】日々の関わりで大切にしたいこと
最後に、「認めない保護者」に対しても、そうでない保護者に対しても、日々の関わりで心掛けてほしいポイントをまとめました。
保護者とのコミュニケーション
- 子どもの成長や良い面を積極的に伝える
- 困り事があっても、責めるような言い方は避ける
- 「一緒に考えていきましょう」という姿勢を示す
- 保護者の頑張りを認めて労う
どんな時でも、保護者との信頼関係が一番大切。日々の会話の基本は『良い事9・気になる事1』と覚えておいてくださいね。
子どもへの関わり
- 園にいる間は、最大限の支援を提供する
- 他の子どもとの関係も大切にする
- 小さな成長も見逃さず、記録に残す
- 子ども自身が困らないような環境調整
「あ~、またあの子・・・」「もう何回も言ってるのに!」
と言ってもどうしよもないんです。考え方を変えて、人的・物理的環境設定に取り組んでいきましょう。そしてその結果もしっかりと記録に残していきましょう。
職員間での情報共有
- 客観的な記録を残す
- 感情的にならず、事実ベースで共有
- チーム全体で一貫した対応を心がける
保育はチームです。
勝手に一人で行うのではなく、職員間の連携をしっかりと図り、園全体としてサポートしていけるようにしましょう!
まとめ:保育士は「今できることを続ける」存在
発達障害を認めない保護者への対応に正解はありません。しかし、以下のことを心に留めておくことで、少し楽になるかもしれません。
大切にしたい考え方
- 認めてもらえなくても、寄り添い続けることに意味がある
- 保護者に伝わらない=失敗ではない
- 子どもにとっての「今」にベストを尽くす
- 保育士同士で支え合いながら進むことが大切
- 「他人の子」という割り切りも、時には必要
最後に。
保育士は魔法使いではありません。できることにも限界があります。しかし、その限られた範囲の中で、子どもたちに寄り添い続けることは、確実に意味のあることです。
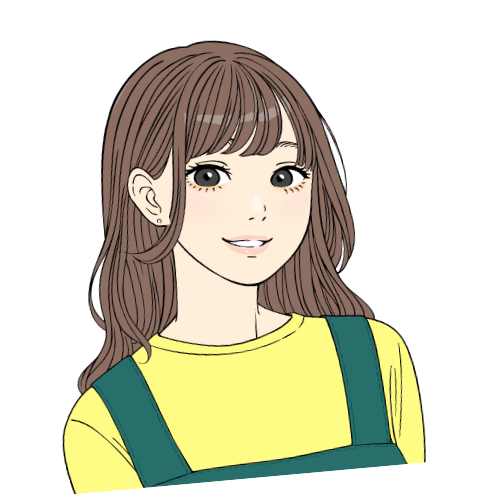
保護者が今すぐ理解してくれなくても、先生が子どもに向けた愛情と専門性は、必ずその子の力になっています。完璧を求めず、「今日もできることをやった」と思える日々を積み重ねていきましょう。
保護者対応に困ったときの解決の糸口に
保護者対応の言いかえ図鑑
ちょっとした言いかえで、保護者対応は劇的に変わる!
「連絡」「参観日・保護者会」「懇談会」「いじめ・ケンカ・不登校」「クレーム」「トラブル」
6つの観点ですぐに使える60のフレーズが紹介されているので、一度目を通す価値あり!
発達障害の子の保育
発達障害の基本的な知識に加え、子どもが発達障害の可能性があると告知を受けるなどした保護者がたどる心理的変化について、ドローターの5段階説にそって解説。
保護者の心理的フェーズに沿ったプロとしての対応方法
保護者の言動・行動を受け止める心構えなども、具体的に解説しています。
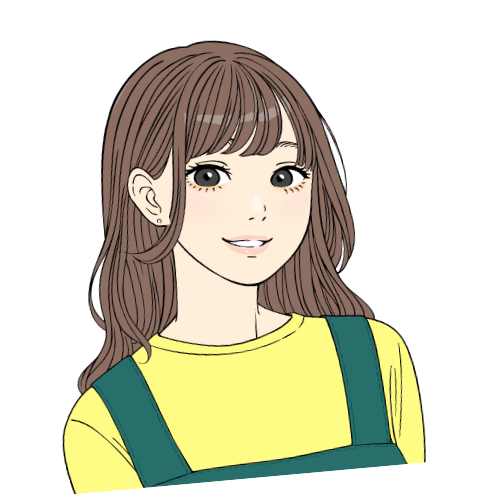
もっと保護者対応について深く学んでいきたい、知ってみたい!と前向きな先生にはこの2冊をおすすめしています♡



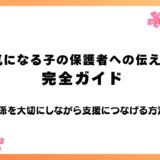

I believe this web site has some really superb information for everyone : D.
I am typically to running a blog and i really appreciate your content. The article has actually peaks my interest. I am going to bookmark your web site and preserve checking for brand spanking new information.