※本記事にはプロモーションが含まれています
目次
あなたも経験ありませんか?こんな場面…
「一回の声かけで、みんなと同じことができなくて困る」
「あの子は行事の練習になると、全く心がこちらに向かなくなってしまう」
「集団遊びの時間になると、いつも一人で別のことをしている」
「お友達とトラブルが起きやすくて、どう声をかけたらいいか分からない」
保育士として働いていると、クラスに必ず一人は「ちょっと気になる子」がいますよね。他の子と少し違う様子を見せる子への対応に、日々悩んでいる保育士さんも多いのではないでしょうか。
「この関わり方で合っているのかな?」
「もっといい対応方法があるのでは?」
「この対応は他の子を犠牲にしてしまっているのではないだろうか」
そんな不安を抱えながら、毎日の保育に向き合っている先生たちの気持ち、本当によく分かります。保育の現場に長年勤めてきましたが、私が一年目の頃に比べて「個別の関わりが必要」という子が本当に増えているようにも感じます。
では、そんな保育現場の悩みをどう解決していったらいいのでしょうか。
一番の頼りは現場にいる先輩先生
やはり、一番に頼りになるのは、経験を積んでいる先生からのアドバイス。いろいろな子どもたちを見てきた先生の対応方法は、唯一無二。
でもそれは理想論。現実にはそれだけで解決できないことがたくさん・・・
なぜかというと、発達支援に関する知識は必ずしも全員が持っているわけではないから。むしろ年配の先生ほど「昔はそんな子いなかった」と受け止めが薄いケースも多いんです。
・・・じゃあどうしますか?
園の研修だけでは限界がある現実
そこで次に頼りにされるのが、園内や自治体で行われる研修です。
発達障害系の内容は「障害児保育」というジャンルでの研修に含まれています。ただ、この「障害児保育」も幅がとても広く、知的障害など医療的ケアを要する子から、発達障害を持っている子までジャンルが様々。
更に言えば、発達支援に特化した内容を学べる研修が本当に少ない。
発達障害に関する基本的な知識は学べても、「実際にこの子にはどう関わればいいの?」という具体的な悩みに応えるには不十分なこともあります。

「理論と実践のギャップ」があってどうしたらいいのか分からなくなってしまう。こういった声もたくさん聴いてきました。
そうなんです。目の前の子どもたちの姿は、必ずしも教科書通りにはいかないんです。
例えば、こんな経験はありませんか?
- 集団活動に参加したがらない子への声かけに迷う
- 言葉の発達がゆっくりな子の保護者に、どう伝えればいいか悩む
- 他害行動がある子への対応で、同僚と意見が分かれる
- 感覚過敏がありそうな子に、どう環境を整えればいいか分からない

こうした場面で「もっと知識があれば…」「保育のコツが分かれば・・・」と感じるのは、あなただけではありません。
なぜ発達支援の学びが必要なのか
発達支援に関する情報は近年ネット上でもたくさん出回るようになり、知識がある先生が増えてきているのが現状です。それでもなお、対応に追われている園が大多数。
ということは、学びの内容をもっと具体的にし、どの先生にとっても当たり前の知識として持っておく必要があるということです。

学ぶことで得られるメリットについてもお話しておきますね。
1. 子どもに安心を届けられる
困った子と思われている子は、裏を返せば「困っている子」なんです。その困ったを解決して過ごしやすくしてくれる先生がいたら、その子は安心して園生活を送ることができます。
「分かってもらえている」と感じる環境は、自己肯定感の土台になります。
例えば、音に敏感な子に静かな場所を準備してあげることは、ただの配慮ではなく「理解されている」という安心感につながります。
それは子どもの自己肯定感を支え、挑戦する気持ちを引き出すきっかけにもなります。
2. 保護者との信頼関係が深まる
相談を受けたとき、知識を持って答えられる保育士は保護者にとって心強い存在です。
「この先生なら大丈夫」と思ってもらえれば、園と家庭の連携もスムーズになります。
3. 自分自身の不安も減る
知識が増えれば「どうしたらいいか分からない」という不安は確実に減ります。
対応の選択肢が増えることで心に余裕ができ、毎日の保育にも前向きに取り組めるようになるんです。

多くの先生にとって一番のメリットは「自分が少しでも楽になれること」だと思います。毎日の保育の中で「どう関わればいいか分からない」と悩み続けるのは大きなストレスですよね。知識があることで不安が和らぎ、対応の選択肢も増えます。その安心感が先生自身を支え、結果的に子どもにとっても過ごしやすい環境づくりにつながっていくのだと思います。
発達支援を学ぶ方法
私もまだまだ勉強中の身ですが、「どうやって学びを続けるか」というのは多くの保育士さんにとって共通の悩みですよね。そこで、私が実際に取り入れている学びの方法を紹介します。
日常の中でできることから
本や雑誌を読む
事例が分かりやすく紹介されている本は、隙間時間の学びにぴったりです。今私が特に愛読しているのが「PriPriパレット」という月刊雑誌。

保育士さんなら99%知っているであろう「PriPri」の発達支援バージョン。この雑誌が発売されたことは、私にとっては衝撃的でした!まさに痒いところに手が届く雑誌なので、一度目を向けてみることをおすすめします。
同僚や専門家に相談する
リアルな経験談や視点の違いは、自分の対応を見直すヒントになります。もし近くに気軽に聞ける人がいなくても大丈夫。
今の時代がSNSでもたくさんの専門家さんとつながる事ができます。

私もSNSを通して、療育施設の先生やベテランの保育士さんとDMでやり取りをしたりし、常に学び続けています。
園外研修に参加する
もし可能であれば積極的に園外の研修にも参加しましょう。
園の外に出ると、普段気づけない視点や具体的な工夫を得ることができます。
また直接話を聞くことで、お互いの刺激になり、発達支援についての熱量がグッと上がるはずです。
体系的に学ぶなら「資格」も選択肢に
もう一つ視野に入れてほしいのが、「資格を通した学び」。
本を買っても、なんとなく目を通しただけで実践できずに終わっている・・・
園外の研修は時間が無くて行けない
SNSで誰かに相談するなんて無理・・・
という保育士さん、案外多いんです。その気持ちすごく分かります!
そんな方には、自宅でこっそりコツコツと学べる「発達支援系の資格」をおすすめします。
「資格が欲しい」というよりも、学び続けられる環境に自分を置くことが大切です。
通信講座や資格取得の仕組みには、教材やスケジュール、添削課題などが整っていて、忙しい保育士さんでも自然と学びを進めることができます。

資格そのものが目的ではなくても、「学びを続ける仕組み」があるかどうかという点を意識してほしいと思います。
まずは本や研修など小さな一歩から始めて、続けられそうだと感じたら資格という環境に身を置いてもいいかもしれませんね。
資格ってたくさんあるけど…どれを選べばいい?
資格って何?という方向けに私がどんな方法で学び続けているかもお伝えしておきます。
実は、発達支援に関する資格はたくさんあります。
- 児童発達支援士
- 発達障害児支援士
- 子ども発達障がい支援アドバイザー
名前も似ているので「どれを選べばいいの?」と迷ってしまう方も多いはず。
私も同じように悩んだ経験があるので、きっと役立つと思います。
👉 発達支援の資格、どれを選べばいいの?ユーキャン・キャリカレ・四谷学院を本気で比較して分かったこと
記事ではこんな疑問に答えています。
- 現場で役立つのはどの資格?
- 費用や学習期間は?
- 働きながらでも続けられる?
まとめ:学びの一歩で、子どもも自分も楽になる
発達支援の学びは、特別な人だけのものではありません。
「子どもをもっと理解したい」という気持ちがあれば、誰でも始められる一歩です。
学びの形はいろいろ。
- 本を読む
- 研修に参加する
- 資格で体系的に学ぶ
どんな形でも、その一歩が子どもの安心につながり、あなた自身の自信になります。

「この子にはこうしてみよう」「保護者にはこう伝えよう」そう思えるようになると、毎日の保育がぐっと楽しくなりますよ。
もっと詳しく知りたい方へ
「体系的に学べる資格に興味はあるけど、たくさんあって選べない…」
そんな方のために、人気の発達支援資格を比較してまとめました。
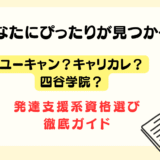 発達支援の資格、どれを選べばいいの?ユーキャン・キャリカレ・四谷学院を本気で比較して分かったこと
発達支援の資格、どれを選べばいいの?ユーキャン・キャリカレ・四谷学院を本気で比較して分かったこと
👉 【2025年最新】保育士におすすめ発達支援資格3選を徹底比較!ユーキャン・キャリカレ・四谷学院どれがおすすめ?

費用・学習内容・続けやすさを保育士目線で解説しているので、ぜひ参考にしてくださいね。

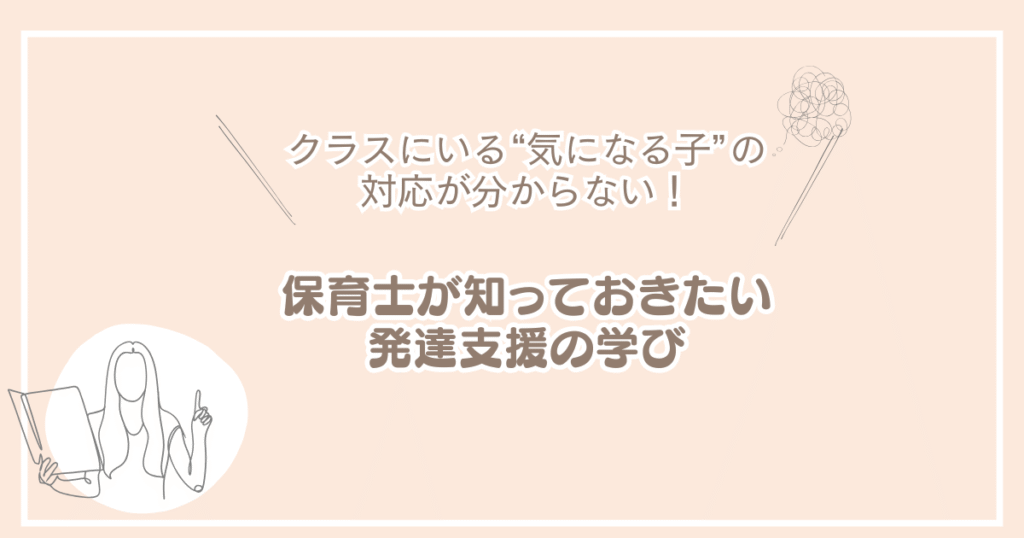

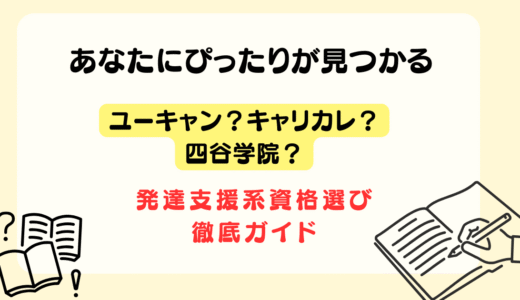
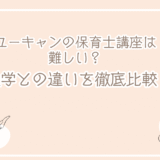
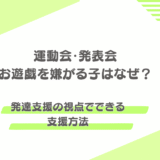
Hello, you used to write wonderful, but the last few posts have been kinda boring?K I miss your tremendous writings. Past few posts are just a little out of track! come on!
Utterly composed written content, Really enjoyed studying.
Wonderful goods from you, man. I’ve understand your stuff previous to and you’re just extremely fantastic. I really like what you have acquired here, really like what you are saying and the way in which you say it. You make it entertaining and you still care for to keep it smart. I can’t wait to read far more from you. This is actually a great web site.