※本記事にはプロモーションが含まれています
「〇〇ちゃんのことで、ちょっとお話があるんですが…」
この一言を言おうとして、心臓がドキドキして言葉に詰まってしまった経験はありませんか?
実は、90%以上の保育士が「気になる子の保護者への伝え方」に悩んでいます。
「傷つけてしまうかもしれない…」 「関係が悪くなったらどうしよう…」
「何て言えばいいのかわからない…」「専門的な知識が足りない気がする…」
でも大丈夫です。正しい伝え方を知れば、保護者との関係を壊すことなく、むしろ信頼関係を深めながらお子さんの成長を支援できるようになります。
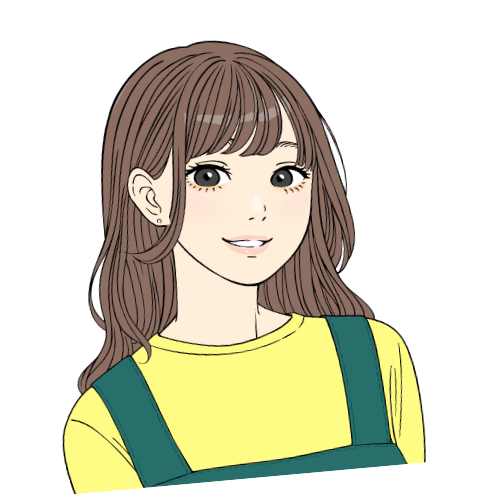
この記事を読み終える頃には、明日から自信を持って保護者の方とお話しできるようになりますよ。
目次
なぜ保護者への伝え方が難しいのか
保育士が抱える不安
どうして保護者に伝えることが難しいのか。保育士さんが感じている悩みをピックアップしました。
- 保護者を傷つけてしまうのではないか
- 関係が悪化して、お子さんに影響が出るのではないか
- 専門知識が不十分で、適切に伝えられないのではないか
- 保護者に受け入れてもらえないのではないか
やはり一番心配なのは、「保護者を傷つけてしまうのではないか」という点。
子育てを一生懸命頑張っている保護者に対して、これは伝えてもいいのだろうか・・・。多分この話をしたら傷ついてしまうかもしれないから、やめておこう。
と私もよく心の中で葛藤しています。
保護者の心境への配慮
保護者の方も、我が子のことを指摘されることに対して複雑な感情を抱くのは当たり前。
- 愛するわが子を否定されたように感じる
- 自分の育て方が悪いのかと自責の念を持つ
- 将来への不安が大きくなる
- 周りの目が気になる
保護者の中には、実は我が子に対して育てにくいと感じてるところもあり、悩んでいる場合も。そんな保護者に対して、発達についてのお話をすると、「私の育て方が悪いから・・すみません」と母親自身が責任を感じてしまうことも。
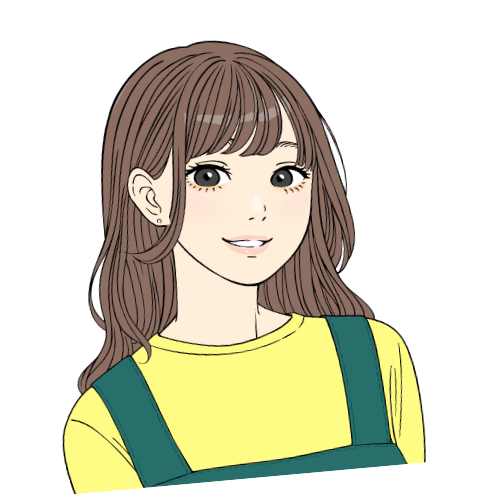
これも実際に私自身が現場で経験したことがあり、「間違った捉え方に伝わってしまった・・・」と後悔したことが何度もあります。
信頼関係を築く日頃のコミュニケーション
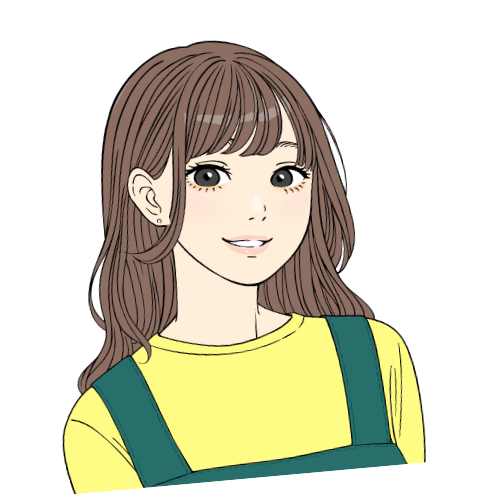
保護者に伝える前に、ちょっとSTOP!今のその保護者との信頼関係はどうですか?
普段からの関係づくりが基盤
ついつい「伝えたい」という想いが強くなると、何を伝えようか・・・と迷ってしまう先生もいるのですが、一旦スト~ップ!遠回りのように感じますが、気になることを伝える前に、日頃から保護者との良好な関係を築いておくことが重要です。
伝えづらいことは、日頃の信頼関係によって保護者の捉え方が全然違ってくるんです。「この先生なら信頼できる」「いつも我が子のことをよく見てくれている」「よく声をかけてくれる」そういった基盤は必要不可欠。
そこで、保護者との信頼関係作りのコツを少し学んでいきましょう。
※補足※具体的な関係づくりの方法
これは私の勤務している園でも、保護者支援として全職員が心掛けている内容です。
- お迎え時の何気ない会話を大切にする
- お子さんの良い面を積極的に伝える
- 保護者の子育ての頑張りを認める
- 困ったときは一緒に考える姿勢を示す
送り迎えや連絡帳でのやり取り、というちょっとした時間で、いかに何気ない会話を積み重ねていくかを大切にしてほしいと思います。
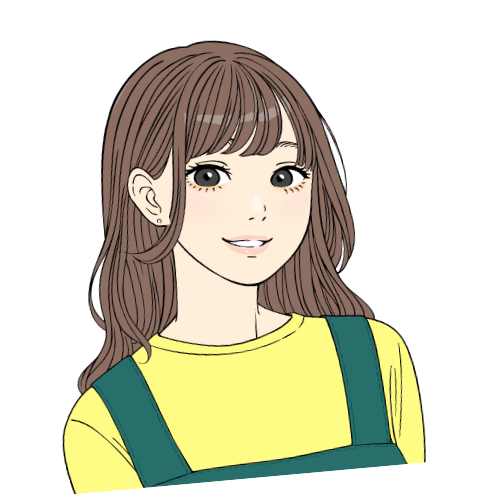
「今日、〇〇ちゃんがお休みの日のお出かけの話聞かせてくれましたよ。『水族館でイルカ見た!ばあばも一緒。イルカのぬいぐるみ買ったの』と言っていましたよ!一日中イルカ一色で、お絵かきの時間もイルカの絵を書いていたんです!」
ちょっとした会話ですが、お母さん方も、「そうなんです!めちゃくちゃ大きなイルカのぬいぐるみなんですよ~(笑)」なんて会話も弾んでいくのではないでしょうか?
お子さんの良い面を伝える習慣
「Aちゃん、今日は自分でトイレに座ることができて嬉しそうでしたよ。最近頑張っていますよ!」
「縄跳びが得意なんですね。今日も楽しそうにやっていました」
このような日常的なポジティブな情報共有が、信頼関係の土台を作ります。
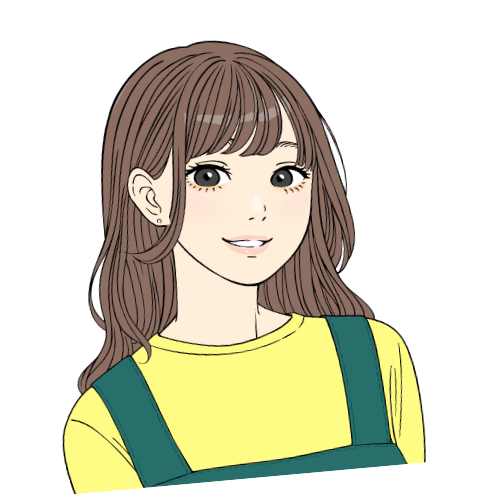
もしこれができていないと感じる場合は、まずはそこから始めることをおすすめします。
保護者に伝える前の準備
保護者との信頼関係が築けていると感じる場合には次のステップに進んでOK。
観察記録を整理する
伝える前に事前準備をします。
- いつ、どこで、どのような場面で
- どのような行動が見られたか
- その時の状況や環境要因
- お子さんの様子や表情
- 他の子どもとの関わり方
その子の行動の事実を確実に記録しておいてください。曖昧なものではなく、確かな情報があることで、先生自身が芯をもって保護者対応に当たることができます。
チーム内での情報共有
情報に関しては、複数の職員から集めましょう。担任の先生の場合 ‟大変” という感情が強く出てしまい気になる事ばかりが出てきてしまうことも。
- 複数の保育士での観察
- 主任や園長との相談
- 必要に応じて専門機関への相談
客観的に見た事実を複数の職員にピックアップしてもらい、たくさんの情報をまとめおきましょう。
伝える目的を明確にする
- お子さんの成長を支援するため
- 適切な環境を整えるため
- 保護者と一緒に考えるため
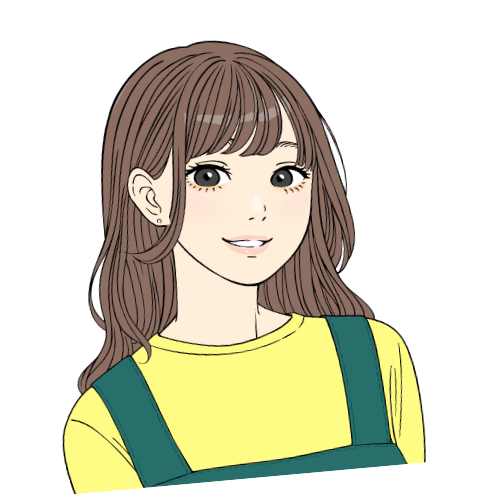
最後に、質問です。気になる子の話を保護者にする場合の目的はなんですか?発達障害ということを突きつけたいだけ?
きっと違いますよね?どうして、その事実を保護者に伝えたいのか、目的意識を明確にしておきましょう。
実践的な伝え方のテクニック
私の勤務する園で心掛けている、保護者への伝え方の方法を紹介します。
1. タイミングを見極める
適切なタイミング
- 保護者に時間的・心理的余裕があるとき
- お迎えが早い日など、ゆっくり話せるとき
- 個人面談などの正式な場
避けるべきタイミング
- 朝の忙しい時間
- 保護者が疲れているとき
- 他の保護者がいる前
2. 場所と環境を整える
- 人目につかない静かな場所
- 落ち着いて話せる環境
- お子さんが近くにいない状況
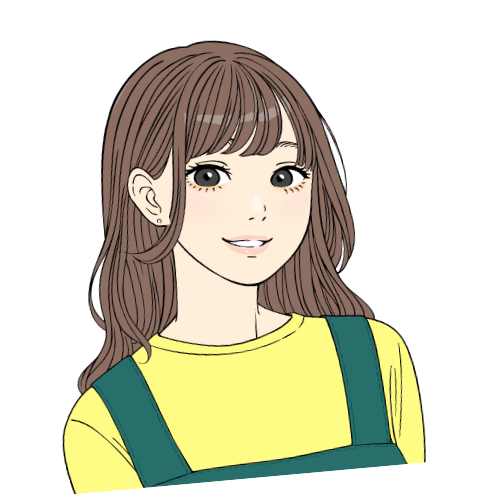
「子どもが近くにいない状況」という部分は案外大切。子どもに聞こえてしまうことも、子どもに気を取られて話が半分になってしまうことも避けてほしいと思います。
3. 話し始めの工夫
× 避けるべき話し始め
→「〇〇ちゃんのことで、ちょっと気になることがあるんですが…」 「〇〇ちゃん、発達が少し遅れているような気がして…」
○ 良い話し始めの例
→「〇〇ちゃんのことで、一緒に相談させていただきたいことがあるんです」 「〇〇ちゃんがもっと楽しく過ごせるように、ご相談があります」 「〇〇ちゃんが困ってしまわないように何かいい方法はないかと考えています。」
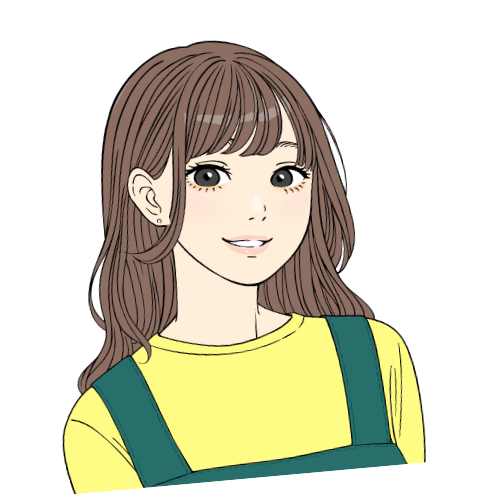
急にズバッとキツイ言葉を使うことは絶対に避けてください。その状況を作ってしまうと、保護者が壁を作ってしまいます。
4. 具体的な伝え方の例文
その子の状況によって話の内容は変わってきますが、具体的にどのように話すといいのかも紹介していきますね。
コミュニケーション面で気になる場合
「〇〇ちゃんは、一人遊びがとても集中してできて素晴らしいんですよ。この前も、黙々とブロックでお城を作っていて・・・(省略)。もうすぐ4歳になるので少しずつお友達との関わりも増えてくれるといいと思っているのですが、おうちではいかがですか?近所の子やお友達と遊んだり・・ということもありますか?」
多動傾向が気になる場合
「〇〇くんは好奇心旺盛で、いろいろなことに興味を持ちいつも楽しそうに過ごしていますよ。昨日も・・・(良いエピソードを伝える(省略))。最近作品展に向けての製作活動が始まっているのですが、途中から気持ちが途切れてしまったようで、最後まで取り組むことができずお部屋から飛び出してしまったんです・・もしかしたら、隣のクラスの歌の声や通り過ぎるトラックなどの音に気が向いてしまったかもしれないのですが、そういったことが近頃続いていて・・・おうちではそのような姿はありませんか?」
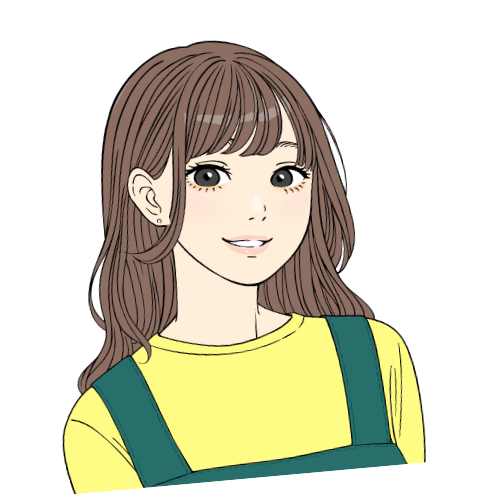
このように、園での姿の事実だけをただ伝え、おうちでの状況を聞くという形で話を勧めるようにしています。
保護者の反応別対応方法
否定的な反応を示された場合
「そんなことはありません」「家では普通です」という返答だった場合。
対応のポイント
- 否定せず、まずは保護者の気持ちを受け止める
- 「お家では違うのですね。環境によって変わることもありますよね」
- 園での様子を具体的に、感情を込めずに伝える
- 時間をかけて、継続的に伝えていく
過度に心配される場合
「やっぱりうちの子は…」「どうしたらいいかわからない」という返答だった場合。
対応のポイント
- 不安な気持ちに共感する
- 「一緒に考えていきましょう」という姿勢を示す
- 具体的な支援方法を提案する
- 専門機関への相談を提案する際は、強制ではなく選択肢として
受け入れて相談してくれる場合
「そうですね、気になっていました」「どうしたらいいですか」という返答だった場合。
対応のポイント
- 保護者の気持ちを受け止める
- 一緒に考える姿勢を大切にする
- 具体的な支援計画を相談する
- 家庭と園での連携方法を話し合う
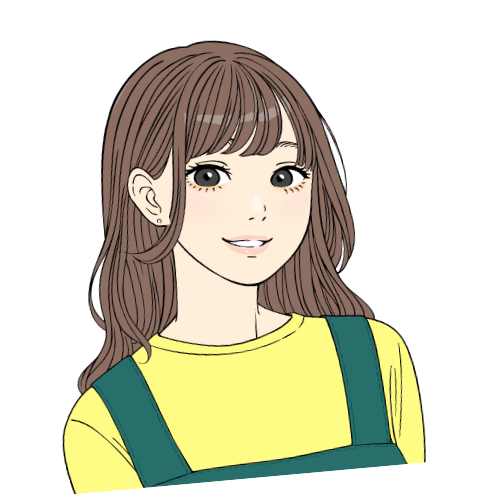
返答の仕方・口調・内容によって声をかける内容を決めておくと、いざという時に困りませんよ。私が良く使うのは「〇〇ちゃんが活動の中で困ってしまっている」という表現。私たちが困っているのではなく、その子が困っていると伝えることで、保護者への伝わり方が変わってきますよ。
専門機関への相談を勧める際の注意点
基本的にいきなり専門機関への相談を勧めるという方法はおすすめできませんが、保護者からそのような声があった場合には以下の点に気を付けて対応してください。
伝え方の工夫
「発達検査を受けてください」ではなく、 「〇〇ちゃんがより楽しく過ごせるように、専門の先生に相談してみてもいいかもしれませんね」 「〇〇ちゃんに合った関わり方のヒントが得られるかもしれませんよ」
このように、常に子どものためというスタンスで話を進めていきましょう。以下の点も参考にしてください。
- 複数の選択肢を提示する
- 保護者が主体的に選択できるようにする
- 急かさない、強制しない
- 園としてのサポートも継続することを伝える
継続的な支援のために
伝えたらすっきり!それでおしまい!とはいかないのが保護者支援。最後までしっかりケアしていきましょう。
記録の重要性
- 保護者との面談内容を記録する
- お子さんの変化を継続的に記録する
- 支援の効果を客観的に評価する
以上のような内容は、すぐに記録として残しておきましょう。可能であれば保護者とのお話中もメモ等を取るようにし、間違った情報になってしまわないようにしましょう。
チーム全体での支援
- 担任だけでなく、園全体でお子さんを支える
- 保護者との情報共有を職員間で行う
- 一貫した対応を心がける
園全体でのサポート体制は、必要不可欠!自分一人で終わりにせず、職員会議などで情報共有をしっかりと行い、園全体でサポートしていける体制を整えましょう。
長期的な視点
- すぐに結果を求めない
- 小さな変化も大切にする
- 保護者との信頼関係を継続的に築く
発達支援は長期戦です。保護者に伝えた以上、その時だけでなく継続的な支援を心がけてください。気になる行動はメモを取る。必要に応じで、その状況を保護者と情報共有する。気になる事だけでなく、こういった関わり方をしたらうまくいきましたよ。という成功体験も園と家庭で共有していくことが大切です。
まとめ:大切なのは「一緒に」という姿勢
気になる子について保護者にお伝えすることは、本当に難しいし、これでよかったのかな?と何年経験していても毎回反省が付き物。でもそれは、目の前いにるお子さんの成長を支える大切な仕事の一部でもある、と誇りをもって取り組むようにしています。
私自身もまだまだ、うまくいくことばかりではありませんが、保育士としての経験を最後にまとめておくので、もう一度読み直し、明日からの保育の参考にしてもらえると嬉しいです。
保護者対応のポイント
- 日頃からの信頼関係づくり
- お子さんの良い面を伝える習慣
- 準備を十分に行う
- 保護者の気持ちに寄り添う
- 「一緒に考える」姿勢を大切にする
- 継続的な支援を行う
保護者の方も、我が子の成長を願う気持ちは私たち保育士と同じです。その共通の思いを大切にしながら、お子さんの最善の利益を考えて進んでいけば、きっと良い方向に向かうはずです。
一人で抱え込まず、チーム全体で、そして時には専門機関とも連携しながら、お子さんと保護者の方を支えていきましょう。あなたの丁寧な関わりが、きっとお子さんの未来を明るくする力になります。
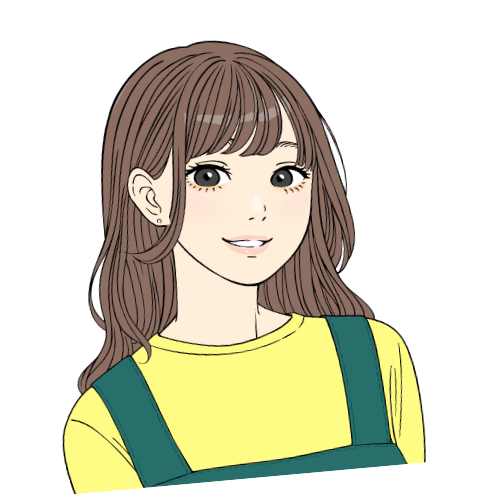
明日からの保育も一緒に頑張っていきましょうね♡
関連する人気の記事
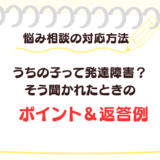 「うちの子、発達障害?」と聞かれたらどうする?保護者対応実践編
「うちの子、発達障害?」と聞かれたらどうする?保護者対応実践編
 現役保育士直伝!!保護者対応がしんどい!疲れた!対応の8つのコツを大公開
現役保育士直伝!!保護者対応がしんどい!疲れた!対応の8つのコツを大公開

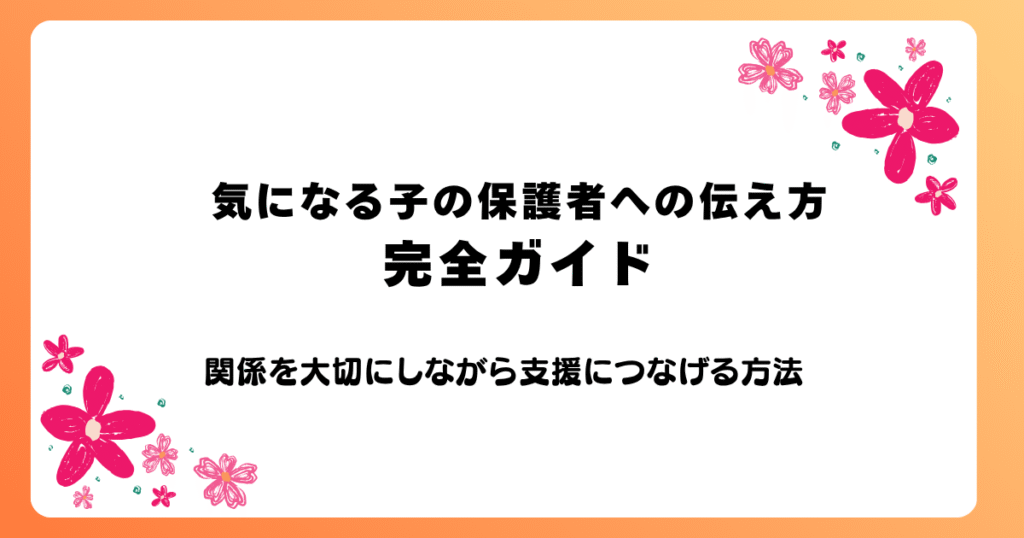

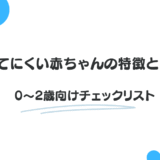
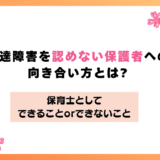
I would like to thnkx for the efforts you have put in writing this blog. I am hoping the same high-grade blog post from you in the upcoming as well. In fact your creative writing abilities has inspired me to get my own blog now. Really the blogging is spreading its wings quickly. Your write up is a good example of it.
It’s appropriate time to make some plans for the future and it’s time to be happy. I’ve read this post and if I could I want to suggest you few interesting things or advice. Maybe you could write next articles referring to this article. I want to read even more things about it!