※本記事にはプロモーションが含まれています
目次
「私、加配向いてないかも…」と思ったことありませんか?
「今日も一日中、Aくんから目が離せなかった…」 「他の子たちのケアができていない気がする…」 「保護者からの質問に、自信を持って答えられない…」
加配担当になったとき、こんな不安や悩みを抱えたことはありませんか?
- いきなり重い荷を背負わされる「加配担当」
- 「専門知識がないのに任されて不安」
- 通常の保育より関わり方が難しい
- よくわからないまま”感覚”で対応している・・・
これは加配担当になった先生が感じやすい気持ちです。
でも実は、「ちょっとした知識」が今の状況を改善するきっかけになるかも!?

この記事では「どこまでの知識があればいいのか」「どうすれば少しラクになるのか」をお伝えします。毎日奮闘している保育士さんの、少しでも力になれれば幸いです。
加配児担当ってなぜこんなにしんどいの?

「加配の担当って、しんどい…」
- 毎日がんばっているのに、「なんだか私ばかり大変かも」と感じる
- 子どもとの関わりに手応えがなくて不安になる
- 職員間で温度差があり、モヤモヤが募る
- 何が正解か分からない
- 毎日反応の違う子の対応に追われてしまう・・・
得意不得意がありますが、加配担当の保育士さんはこんな気持ちを抱えている人がたくさんいるのが現状です。
通常保育との両立が難しい
ではなぜ加配担当の保育士が辛い、しんどいと思われがちなのか考えていきましょう。
おそらく、通常の担任などを経験したことのある先生なら、クラスをまとめることの大変さを良く知っていますよね。
しかし加配保育士は、発達障害のある子など特別に個別の関わりが必要な子の対応をすることが主な任務。そのため、
- 「この子だけに付いていて、担任の〇〇先生の負担になっていないかな?」
- 「クラス運営のために担当のA君を何とか言い聞かせてクラスの輪に入れてあげなきゃ!」
など、加配保育士のやるべき任務だけに没頭することなく、クラス全体への配慮もしなくてはいけないという状態になってしまいます。
そのため、常に優先順位の判断を迫られ、精神的な負担が大きくなりがちなのです。
一人ひとり特性が違いすぎて正解が見えない
「Bちゃんには効果的だった声かけが、Cくんには全く効果がない…」
「昨日までできていたことが、今日は急にできなくなった…」
発達に特性のある子どもは、一人ひとり異なる特性を持っています。マニュアル通りにはいかないことが多く、日々試行錯誤の連続です。
この状況もまた、加配の先生を苦しませている原因となっています。
保護者との対応もプレッシャー
「子どもの様子をどう伝えればいいの?」
「専門的なアドバイスを求められても…」
保護者との信頼関係を築きながら、子どもの状況を適切に伝えることは大きな責任です。特に発達の遅れや気になる行動について話すときには、言葉選びに悩むことも多いでしょう。
難しいと言われがちな保護者対応。対象の子どもによって慎重な言葉選びが必要になり負担と感じる先生も多いようです。
支援の専門家でもないのに…と感じる葛藤
「私は発達支援の専門家じゃないのに、大丈夫かな…」
「もっと専門的な対応ができる人が担当すべきでは?」
保育士として子どもたちを見守りたい気持ちがあっても、専門的な知識がないことで自信を失ってしまうことがあります。
他担任からの理解が薄く孤独感を感じることも
「なんであの子、また走り回ってるの?」
「もっとしっかり見ていてよ」
他の先生からの何気ない一言に傷つくこともあるでしょう。
この状況に苦しんでいる先生も多いですよね。頑張っているのに、他人からは「全然できていない!」と思われて迷惑をかけているかも・・・一生懸命頑張っている保育士さんならなおさらそう感じてしまうことも多いですよね。
加配児の特性や対応の難しさを理解してもらえないと、孤独を感じることもあります。
「専門家じゃない私」に求められることって何?

では加配保育士とはどんな役割を担っていくものなのでしょうか。専門家でも何でもないのに、何を求められているの?そんな疑問を紐解いていきたいと思います。
医療的な診断や療育は不要(それは外部の専門職の領域)
まず安心してください。
あなたは医師でも、臨床心理士でも、療育の専門家である必要はありません。そういった専門的なサポートは、医療機関や療育施設が担う役割です。
加配保育士になったから!と専門家のような役割を担う必要は全くありませんよ。
保育の中でできる「気づき」「配慮」「記録」が超重要
保育士だからこそできる大切な役割があります。それは
- 子どもの日常の様子を継続的に「観察」すること
- 小さな変化や成長に「気づく」こと
- 子どもが過ごしやすいように「配慮」すること
- 具体的な様子を「記録」すること
これらは、専門機関が短時間の診察や検査では把握できない貴重な情報なのです。
「観察力」と「声かけの工夫」があれば十分役に立てる
- 「この場面で、どんな困難を感じているのだろう?」
- 「どうすれば、この子が活動に参加しやすくなるだろう?」
こうした視点で子どもを観察し、一人ひとりに合った声かけや環境調整ができれば、それだけで素晴らしい支援になります。
でも、それを身につけるには”ちょっとした学び”が必要
とはいえ、全く知識がないまま手探りで進めるのは、あなた自身も子どもにとっても負担が大きいですよね。
そのため最低限の基礎知識を身に付け、先生自身の観察の質と対応の幅は大きく広げていくことがとても大切になってきます。
現場で役立つ知識を学ぶ
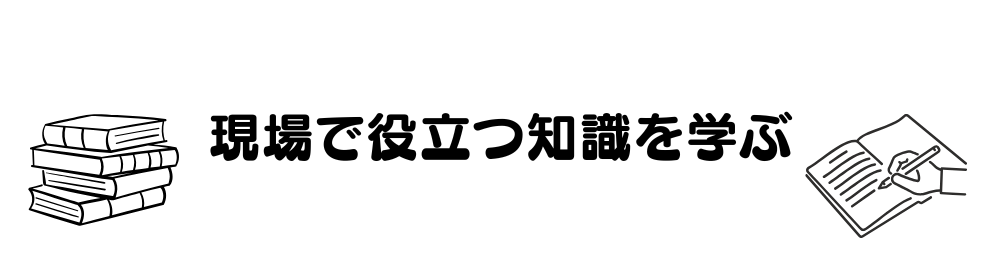
では、最低限の知識とはどんなことなのかもお話していきますね。

これは現役保育士である私が実際に学んだことでもあるので、是非参考にしてくださいね。
ADHD、ASD、LDなどの特性ごとの傾向と配慮ポイント
- ADHDの子どもは、「じっと座っていられない」のではなく「座っていたくても体が動いてしまう」という特性がある
- ASDの子どもは、「指示が理解できない」のではなく「抽象的な言葉より具体的な言葉の方が理解しやすい」
このような特性の基本を知るだけで、「困った子」ではなく「困っている子」という視点で接することができます。

その子たちの行動の「なぜ」に気が付ける知識が付くと、保育がグンと楽になります。
よくある困りごとと、その対応法(具体例)
【場面】片付けができない
- NG例:「ちゃんと片付けてね」
- OK例:「このおもちゃは、飛行機の絵の箱にしまうよ」
【場面】給食時間に席を立ってしまう
- NG例:「ちゃんと座って食べなさい!」
- OK例:「○○くん、3つ食べたら少し休憩してもいいよ。そのあとまた戻ってこれるかな?」

こうした具体的な対応例を知っておくことで、現場での即興的な対応力が高まります。
保護者への伝え方のコツ(言葉の選び方など)
- 「できないこと」より「できていること」を先に伝える
- 「問題行動」という言葉ではなく「〇〇の場面で困っている様子」と表現する
- 専門用語を避け、具体的なエピソードで伝える

できない!困っている!という感情が強すぎると、マイナスなことばかり伝えたくなってしまいますよね。でもちょっとした伝え方の工夫で、保護者との信頼関係を築きやすくなりますよ。
支援計画や記録での表現の工夫
- 「できない」→「現在取り組んでいる」
- 「パニックを起こす」→「気持ちの切り替えが難しい場面がある」
- 「多動」→「身体を動かすことで気持ちを整えている」
プラスにつながるような表現方法を学ぶことで、より前向きな支援計画を立てられるようになります。

こういった知識を効率的に学ぶことができたら、いいと思いませんか?
おすすめは資格取得を通じた学び!
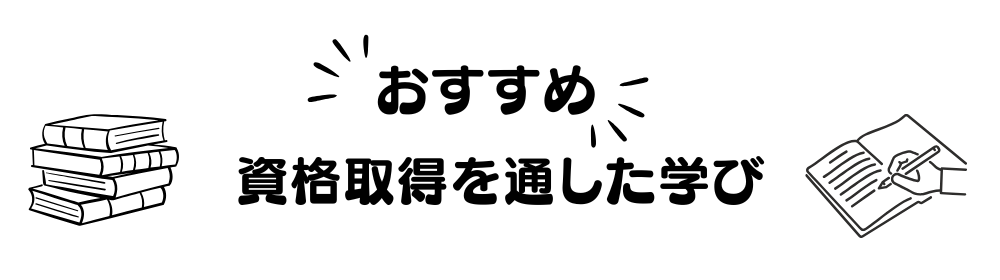
そこでおすすめしたいのが、資格取得を通した学びです。
ただ自分一人で闇雲に勉強するより何倍も効率的に知識を得ることができるので本当におすすめです。

正直、どうせ民間資格でしょ?と思っていましたが、実際に受講してみると「ここまで保育現場に即した内容って、他にないかも…」と驚くほどでした
独学よりも効率的に、必要な知識をピンポイントで学べるのが魅力。
忙しい保育士こそ、学びの近道として「資格」は強い味方になります。
保育士におすすめの発達支援系資格3選
それでは実際に、「これはよかった!」と感じた資格を3つご紹介します。
①ユーキャン【子ども発達障がい支援アドバイザー】
| 学習期間 | 学習方法 | 特徴 |
|---|---|---|
| 約3ヶ月 | テキスト学習+添削課題 | 忙しい保育士でも無理なく学べるペース配分 |
- 発達障害の基礎から保育現場で役立つ支援方法までしっかり学べる
- 保護者対応の具体例も豊富で、現場の“あるある”にもフィット
もっと詳しく知りたい方へ
▶ 子ども発達障がい支援アドバイザーのくわしい解説はこちら
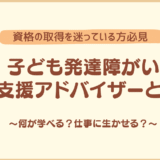 ユーキャンの「子ども発達障がい支援アドバイザー」とは?仕事に生かせる?
ユーキャンの「子ども発達障がい支援アドバイザー」とは?仕事に生かせる?
②キャリカレ【子ども発達障害対応スペシャリスト】
| 学習期間 | 学習方法 | 特徴 |
|---|---|---|
| 約4ヶ月 | テキスト+映像講義 | 実践力を高めたい人におすすめ |
- 幅広い知識をしっかり網羅
- 保護者への対応や支援記録の書き方など、保育士ならではの悩みに寄り添った構成
くわしく知りたい方へ
▶ 子ども発達障害対応スペシャリストのレビュー記事はこちら
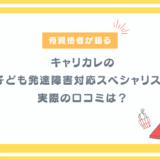 【経験者が本音レビュー】キャリカレ「子ども発達障害対応スペシャリスト」を実際に取得した口コミ
【経験者が本音レビュー】キャリカレ「子ども発達障害対応スペシャリスト」を実際に取得した口コミ
③ユーキャン【子ども発達障がい支援実務士】
| 学習期間 | 学習方法 | 特徴 |
|---|---|---|
| 約4ヶ月 | テキスト学習+課題提出 | より専門的・実務的な内容に特化 |
療育的な視点からアプローチを学びたい人にぴったり
基礎を学んだあと、もう一歩踏み込みたい方へ
【子ども発達障がい支援実務士】は、より専門的・実務的な内容となっており、すでに基礎知識がある方や、将来的に療育専門職を目指す方に適しています。
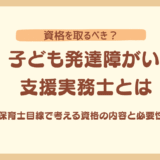 【子ども発達障がい支援実務士】とは?資格を取るべき?保育士目線で考える資格の内容と必要性
【子ども発達障がい支援実務士】とは?資格を取るべき?保育士目線で考える資格の内容と必要性

まだあまり知識がないよという先生の場合は、まずは【アドバイザー】資格から始めて、段階的にステップアップしていくのがおすすめです。
自分を責めないで|加配がしんどいのは、あなたのせいじゃない
- 知識がないのに任されることが多すぎる現場
- それでも向き合おうとしてるあなたは十分立派
- 少しずつ学べば、子どもにも自分にも優しい保育ができるようになる
多くの保育現場では、十分な研修や準備期間もないまま、加配担当を任されることがあります。もし辛いできない!と感じて売るのであれば、それは決してあなたの力不足ではなく、システムの問題です。
毎日子どもたちのために奮闘し、試行錯誤している姿勢こそ、素晴らしい保育者の証です。完璧を目指す必要はありません。

一度にすべてを学ぶ必要はありません。少しずつ知識を増やし、実践していくことで、子どもたちにとっても、あなた自身にとっても、より良い保育環境を作ることができます。
【まとめ】今こそ、「ちょっと知ること」があなたを救う
- 加配のしんどさは「スキルがない」のではなく「教えてもらえてない」だけ
- あなたの保育に、発達支援の”地図”をプラスしてみませんか?
誰もが最初から加配児支援のプロフェッショナルではありません。必要な知識を得る機会がなかっただけなのです。

子どもたちへの愛情と、基本的な発達支援の知識があれば、あなたはきっと素晴らしい加配担当になれます。今の大変さを少しでも軽減するための一歩を踏み出してみませんか?

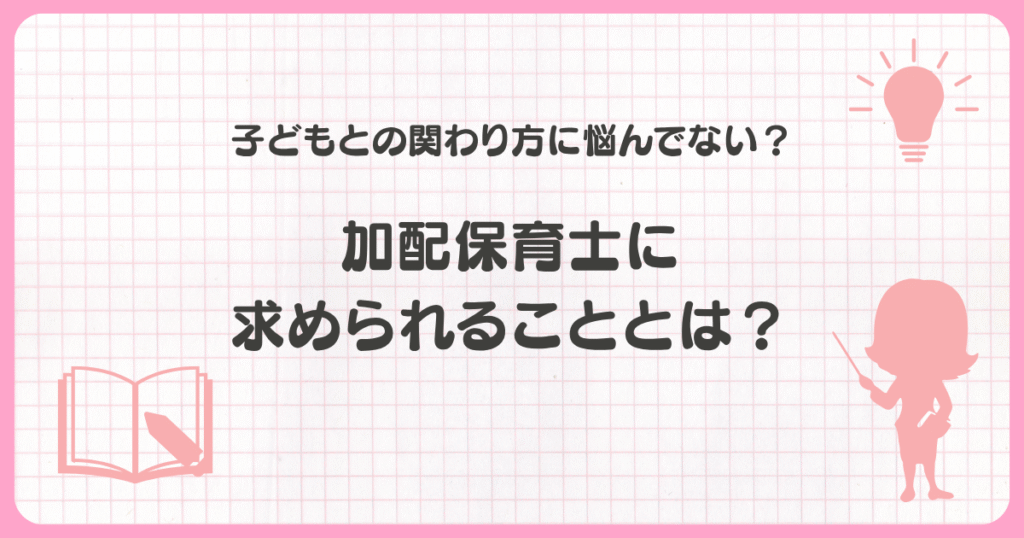

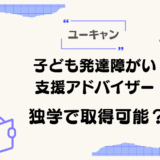
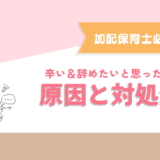
I’m not that much of a internet reader to be honest but your blogs really nice, keep it up! I’ll go ahead and bookmark your website to come back in the future. All the best