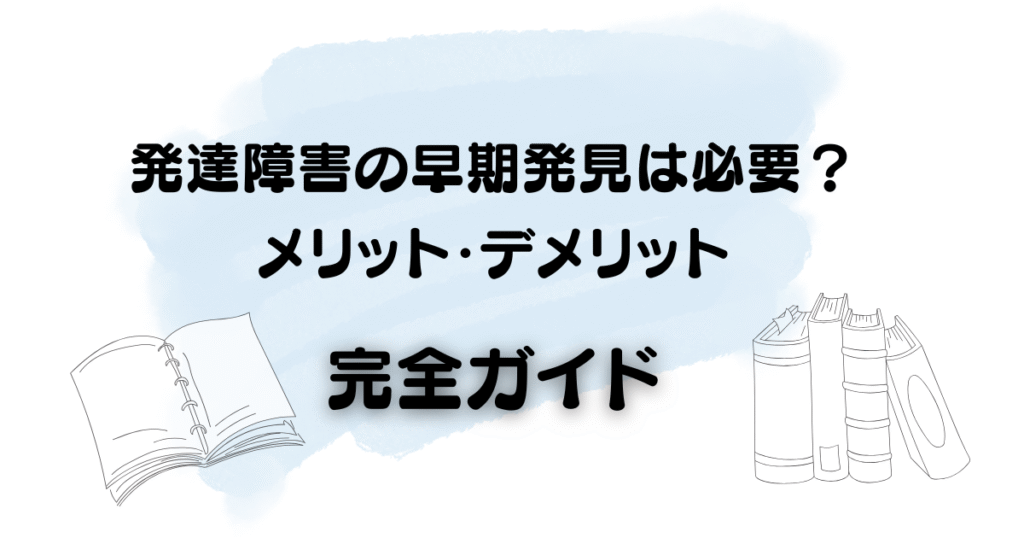※本記事にはプロモーションが含まれています
「この子、もしかして発達障害かな…」
子どもと関わる中で、このような疑問を感じたことはありませんか?言葉の発達が遅い、友達とうまく遊べない、落ち着きがないなど、気になる行動があると心配になるのは自然なことです。
発達障害の早期発見には多くのメリットがありますが、同時に考慮すべきデメリットも存在します。この記事では、保護者や保育士、子どもに関わるすべての大人が適切な判断ができるよう、両側面を詳しく解説します。
目次
発達障害の早期発見で得られる4つの大きなメリット

ではまずはじめに、発達障害の早期発見で得られるメリットについて学んでいきましょう。
- 適切な支援を早く受けられる
- 環境の調整がしやすい
- 二次障害を防げる
- 保護者・保育者が適切な関わりを学べる
以下、具体的にお話していきますね。
適切な支援を早期に受けられる
発達障害の早期発見は、子どもの可能性を最大限に引き出せるチャンスが増えると考えられます。
その理由としては、発達の特性が早く分かることで、専門的な療育や支援を受けるチャンスが広がるから。
子どもの脳がまだ発達途中で柔軟性が高い時期に、適切なサポートや教育を行うことで、その後の発達に大きな影響を与えます。
- 2歳児健診でことばの遅れを指摘された子どもが、早期に言語療法を受けた結果、4歳時には会話の遅れがほぼ解消された。
- 3歳の段階でASD(自閉スペクトラム症)の特性が見られた子どもが、療育を受けながら適切な関わり方を学び、就学時には集団生活にスムーズに適応できた。
環境調整で子どもの困りごとを減らせる
「できない」を「できる」に変える環境づくり
子どもが安心して過ごせる環境を整えることで、ストレスを減らし、自己肯定感を育むことができます。幼児期から環境調整を行うことで、「できること」を増やしやすくなります。
- 注意が散りやすい子どもには、視覚的なスケジュールを用意し、見通しを持たせることで活動の切り替えがスムーズになった。
- 音に敏感な子どもが静かな席で活動できるように環境を調整したことで、集団活動への参加意欲が高まった。
二次障害を予防できる
心の健康を守るための大切なステップ
発達障害に気づかれずに過ごすと、「どうしてみんなと同じようにできないのか」と自己肯定感が下がり、うつや不登校などの二次障害につながることがあります。
早期発見によって適切なサポートが受けられれば、こうしたリスクを減らすことができます。
- 5歳でADHDと診断され、「集中できないのは努力不足ではなく特性によるもの」と理解できたことで、自分に合った学習方法を身につけられた。
- 学習障害(LD)を早期に発見し、適した学習支援を行ったことで、小学校での授業に自信を持てるようになった。
保護者・保育士が適切な関わり方を学べる
子どもとの関わりの不安を軽減し、より良い関係を築ける
子どもの特性を理解し、適切な関わり方を学ぶことで、日々の関わりがスムーズになります。ストレスを減らし、子どもが安心して成長できる環境を作ることができます。
どのように関わったらいいのか分からない・・ということが減るのは良いことですね。
- 予定変更が苦手な子どもに対し、事前に視覚的に伝える工夫をしたことで、パニックを防げるようになった。
- 感覚過敏のある子どもが嫌がる衣類の素材を調整し、身支度のストレスが軽減された。
考慮すべき4つのデメリットと対応策

早期発見のメリットは十分に伝えわったかと思いますが、もちろんデメリッもあるということも知っておいて欲しいと思います。
- 誤診のリスクがある
- 周囲の理解が追いつかないことも
- 親が「障害ありき」で考えすぎる可能性
- 必要以上の特別扱いが自立を妨げることも
誤診のリスクがある
幼児期の発達には大きな個人差があります
特に低年齢では、発達の個人差が大きく、一時的な特性が「発達障害」と誤認されることもあります。慎重な判断が必要です。
- 一度の診断で決めつけず、複数の専門家の意見を聞く
- 定期的な経過観察を行い、成長の様子を見守る
- 「診断名」よりも「今、どんな支援が必要か」に焦点を当てる
周囲の理解が追いつかないことも
社会の認識はまだ発展途上です
発達障害への理解は進んでいますが、まだ誤解や偏見も存在します。診断を受けることで、周囲との関係に影響が出る可能性があります。
- 必要な人にだけ伝え、情報共有の範囲を考慮する
- 周囲の人への適切な説明と理解を促す
- 子ども自身には、年齢に応じた自己理解を支援する
「障害ありき」で可能性を狭めてしまう危険性
レッテルにとらわれず、個性として捉える視点を
診断を受けることで「この子はできない」と可能性を狭めてしまうリスクがあります。特性を理解しつつも、子どもの可能性を信じることが大切です。
- 「〇〇障害だからできない」ではなく「どうすればできるか」を考える
- 子どもの強みや得意なことに注目し、伸ばしていく
- 小さな成長や変化を見逃さず、認めていく姿勢を持つ
過剰な支援が自立を妨げることも
「助けすぎ」にも注意が必要です
必要な支援と過剰な支援は紙一重です。
必要以上に手をかけすぎると、依存心が強まり自立を妨げることがあります。
- 「今、本当に必要な支援は何か」を常に考える
- できることは自分でやる機会を意図的に作る
- 少しずつ難易度を上げながら、成功体験を積み重ねていく
早期発見後に大切にしたい3つの視点
① 診断は「その子の特徴の一つ」と捉える
診断名はその子の全てではありません。
「発達障害がある子ども」ではなく、「○○くん・○○ちゃん」という一人の子どもとして向き合いましょう。診断は支援のための手がかりに過ぎません。
②子どもの「今」を大切にする
将来への不安から、先回りした支援を考えがちですが、まずは「今」の子どもの姿をしっかり見つめましょう。
現在の困りごとに対する適切な支援が、結果的に将来の力になります。
③子どもと関わる大人全体のバランスを考える
子どもの支援は大切ですが、保護者自身や保育現場の負担も考慮する必要があります。
関わる大人たちが無理なく継続できる支援体制を構築することが、長期的な支援の質を保つ鍵となります。
現役保育士からのアドバイス

発達支援の専門家によると、早期発見で最も重要なのは「早期療育」ではなく「早期受容」だと言われています。
子どもの特性をまずは受け入れ、その子に合った関わり方を模索していくプロセスが、結果的に子どもの健やかな成長につながります。
バランスの取れた判断のために
大切なことなので、もう一度お伝えしておきます。
発達障害の早期発見には、明確なメリットとデメリットがありますが、大切なのは「診断名」ではなく「その子に合った関わり方」を見つけることです。
子どもを支える道のりは一人ひとり異なります。悩んだときは一人で抱え込まず、専門家や支援機関に相談してみましょう。また、同じ悩みを持つ保護者同士、保育者同士のつながりも大きな支えになります。

子どもの「違い」を個性として受け止め、その子らしく成長できる環境づくりが、発達障害の早期発見・支援の本当の目的だと思っていてくださいね。
早期発見についてのおすすめ本
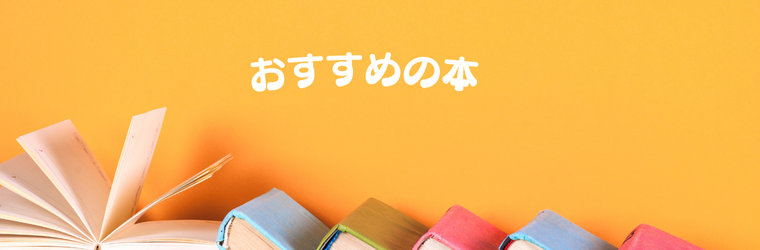
現役保育士として保育園に勤務している【もず先生】が愛読している本を2冊紹介します。
発達障害の早期発見についての本はそれほど多くはありませんが、とても参考になるので、気になる方は手に取って読んでみることをおすすめします。
赤ちゃんの発達障害に気づいて・育てる完全ガイド
発達が気になる赤ちゃんにやってあげたいこと
発達障害は3~4歳以上にならないと診断をしてもらえない、と言われていますが、個人的な意見としては気になる姿があるのであれば、できるだけ早くその子にとって最適な関わり方や環境を整えてあげることが大切だと思っています。
さらに詳しく発達支援について学びたい方へ
最近よく耳にするようになった発達障害とはそもそも何なのか・・?
気になる行動は発達障害が原因なのか・・
適切な関わり方はどんな方法があるのか・・・
そんな疑問や悩みがある方のためにおすすめの資格があります。それは資格大手サイトユーキャンの「子ども発達障がい支援アドバイザー」。

「子ども発達障がい支援アドバイザー」という資格では、発達に課題のある子どもへの適切な関わり方を学ぶことができるので、保育士さんはもちろん、子育て中にパパママにもピッタリ!
このような資格取得を通じて専門的な知識を学ぶことで、より自信を持って目の前の子どもと関わることができるようになるため、近年とても人気を集めている資格です。
「発達支援について理解を深めたい!我が子の気になる行動を少しでも落ち着きのある状態にしてあげたい」
そう感じていらっしゃる保護者の方にもピッタリの資格になっているので、ユーキャンで専門的な知識を得て、子どもとのより良い関わり方、向き合い方を学んでいきましょう。無料資料請求もおススメです!!
詳しくはこちら 子ども発達障がい支援アドバイザーの詳細をチェック