※本記事にはプロモーションが含まれています
運動会シーズンになると、
「どうして踊りの練習に参加しないの?」
「あの子は何度教えても覚えられない」
「みんなと一緒に踊れないと困る・・・」
・・・保育の現場からこんな声がたくさん届きます。そんな子どもたちの姿に悩まされること、ありますよね?
「どうしてこの子だけできないんだろう?」
「他の子はすぐ覚えるのに…」
と、ついつい焦ってしまう気持ち、本当によく分かります。

でも大丈夫!実は、お遊戯を嫌がったり覚えられなかったりするのには、ちゃんとした理由があるんです。今日は発達的な視点から、その背景と具体的な支援方法をお話しします。
目次
「運動会・発表会でお遊戯を嫌がる子の理由」~発達的な背景~
私も現役保育士として現場で働いているので、先生たちの気持ちよく分かります。
クラスをまとめたいのに・・・
個別で関わってあげたいのに・・・
体がもう一つあったらどれだけ楽だろうか・・・
なんて思いながら保育をする毎日。
お遊戯を嫌がる子に対し、どうしてお遊戯を踊ってくれないのかを考えたことはありますか?
ボディイメージの未発達が原因かも
ただ単にその日の体調が悪く踊る気分にならなかった・・・という子も中にはいるかもしれませんが、お遊戯が苦手な子の多くは、「ボディイメージ」がまだ十分に育っていない可能性があります。
ボディイメージって何?と思われるかもしれませんが、簡単に言うと「自分の体がどこにあって、どんな形で、どう動いているかを頭の中でイメージする力」のことです。
ちょっとよく分からないな・・・という方に分かりやすく例えると・・・
車の運転のような感覚。
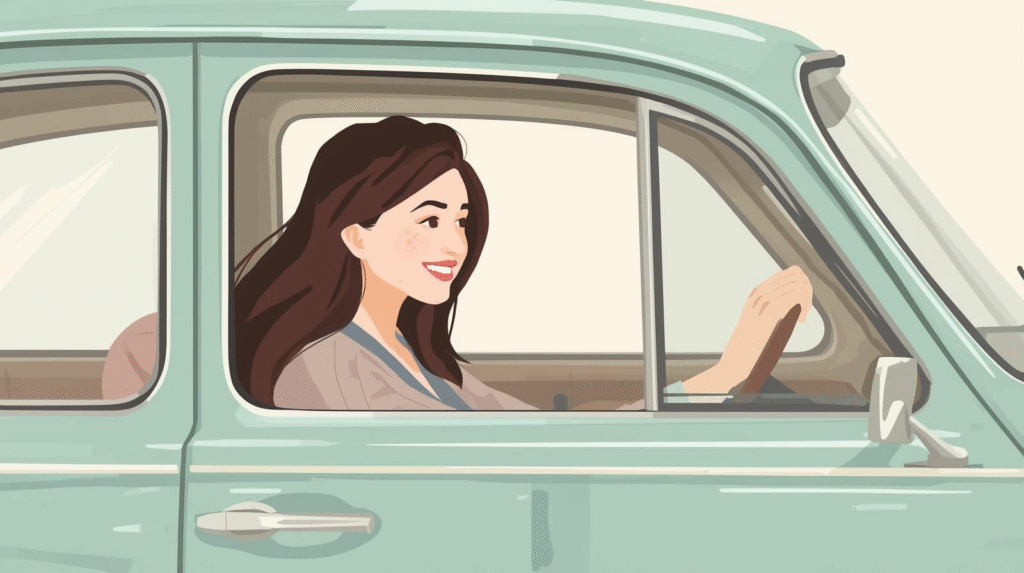
普段軽自動車に乗っている人が、急に大型車を運転することになったとき、「あれ?車幅感覚がつかめない」「バックするときにぶつけそうで怖い」って感じること、ありますよね?
これと同じことが、ボディイメージが未発達な子どもにも起こっているんです。
大人の私たちは長年の経験で自分の体の感覚をつかんでいますが、子どもたちはまだその感覚が育ち切っていない状態。だから「右手を上げて」と言われても、「右手ってどこ?今どんな位置?」と混乱してしまうのは当然なんです。
模倣が苦手だから踊りも覚えにくい

ボディイメージが未発達だと、必然的に模倣する力も育ちにくくなります。
先生のお手本を見て「同じようにやってみよう」と思っても、自分の体がどうなっているかがイメージできないので、なかなか真似ができません。それが積み重なって、「踊りは苦手」「練習したくない」という気持ちにつながってしまうんです。

「この子、やる気がないのかしら?」と思いがちですが、実は一生懸命頑張っているのに体がついてこない…そんな状況かもしれません。
日常でできるお遊戯が苦手な子の支援~ボディイメージを育てる遊び~
ボディイメージを育てるには、日常の遊びの中で自然に体を意識できる経験を積み重ねることが大切です。

特別な道具は必要ありません!園にあるもので十分できますよ。
忍者ごっこで空間認識力アップ
子どもたちが大好きな忍者ごっこは、実はボディイメージを育てるのにとても効果的なんです。
ジャングルジムを背にして立ち、後ろにある棒を手探りでつかむ遊びをやってみてください。「忍者の修行だよ!後ろの棒をつかんでみよう」と声をかけると、子どもたちも楽しんで取り組めます。
最初は「どこにあるの?」「つかめない!」と苦戦するかもしれませんが、これが大事な経験。自分の目では見えない場所にある物をイメージして手を伸ばすことで、自然と体の使い方をイメージする力が育ちます。
上下左右に棒を移動させて難易度を調整すれば、個々のレベルに合わせて遊べますよ。
クモ歩きで全身のバランス感覚を養う

床に手をついて、お腹を上に向けた状態で歩く「クモ歩き」も効果的です。
この姿勢をキープするだけでも、普段使わない筋肉を意識できますし、前進・後退・横歩きをすることで、自分の目では見えていない手足の位置をイメージする力がつきます。

「クモさんになって歩いてみよう!お尻が落ちないように気をつけて」と声をかけながら、ゲーム感覚で楽しんでもらいましょう。
ジャングルジム遊びで空間把握能力を育てる

実は、普通にジャングルジムで遊ぶだけでも、ボディイメージの発達には十分効果があります。
頭がぶつからないようにくぐったり、手足の位置を確認しながら登ったり降りたり…これらの動きすべてが、自分の体と周りの空間との関係を理解する練習になっているんです。

「危ないからやめなさい」と言いがちですが、安全に配慮しながら、できるだけ自由に遊ばせてあげたいですね。
短期的な対応~運動会まで時間がなくても大丈夫!~
「そうは言っても、運動会まであと少し…」そんな時でも大丈夫!短期間でできる工夫もたくさんあります。
個別練習を遊び感覚で取り入れる
全体練習の前後に、さりげなく個別練習の時間を作ってみましょう。
「○○ちゃん、先生と一緒に踊ってみない?」「特別レッスンしちゃおうか」など、特別感のある声かけをすると、子どもも前向きに取り組んでくれることが多いです。

一対一だと、その子のペースに合わせてゆっくり教えることができるし、小さな「できた!」を一緒に喜ぶこともできますよね。
保護者の協力で家庭でも練習を
お家の方にも協力をお願いしてみましょう。
子ども目線で分かりやすく撮影した練習動画を作って配布している園もあります。「お家でも一緒に踊ってみてくださいね」と声をかけると、親子で楽しく練習できて一石二鳥です。

ただし、「絶対に覚えさせてください」というプレッシャーを与えるのは逆効果。「楽しく体を動かせればOKです」という軽やかなスタンスで伝えることが大切です。
役割を工夫して「参加した」経験を
どうしても踊りが難しい子には、別の役割を用意してあげるのも一つの方法です。
「旗振り係」「小道具担当」「司会のお手伝い」など、その子が活躍できる場を作ってあげましょう。大切なのは、運動会という行事に「参加できた」という経験を積むことです。

踊れなくても、みんなと一緒に運動会を作り上げた一員として、達成感を味わってもらいたいですね。
絶対にやってはいけないこと
ここで気をつけたいのは、無理やり踊らせようとしないこと。
「何でできないの!」「もう一回やって!」と強く言ってしまうと、「やってもできない」「じゃあやりたくない」という負のスパイラルに陥ってしまいます。
結果として自己肯定感が下がり、運動や表現活動全般に対して苦手意識を持ってしまう可能性も。これは保育士として本当に避けたいことですね。
運動会の本来の目的を見直そう

そもそも、運動会って何のためにやるんでしょうか?
「完璧な演技を披露するため」?それとも「他の園に負けないため」?
違いますよね。運動会の本来の目的は、「頑張った自分を見てもらう喜び」や「体を動かす楽しさ」を子どもたちに経験してもらうことです。
「できる・できない」で評価するのではなく、「一生懸命取り組んだ過程」や「みんなと一緒に何かを作り上げた経験」を大切にしたいものです。

もし園全体で話し合う機会があれば、改めて運動会の意味や目的を共有しておくことも重要ですね。職員みんなが同じ方向を向いていれば、子どもたちも安心して参加できるし、保護者の方にもその思いが伝わるはずです。
まとめ~一人ひとりの「頑張り」を大切に~
運動会のお遊戯を嫌がる子、覚えられない子には、ちゃんとした理由があります。
ボディイメージの発達には個人差があって当然。その子なりのペースで、その子なりの方法で、少しずつ体を動かす楽しさを感じてもらえればそれで十分です。
長期的には日常の遊びを通してボディイメージを育て、短期的には個別の配慮や役割の工夫で「参加できた」という経験を積んでもらう。そして何より、「できた・できない」ではなく「頑張った過程」を認めて褒めてあげる。
そんな温かい関わりの中で、子どもたちは自分らしく成長していけるはずです。
運動会当日、一人ひとりが自分なりの「頑張り」を見せてくれることを楽しみに、今日からの保育を大切にしていきましょうね。
最後に:保育士なのに発達支援についてどうして詳しいの?と思ってくれた方へ
今回の記事を読んで「なるほど!」と思っていただけた方も多いと思いますが、実際に現場で対応するには、まだまだ知りたいことがたくさんありますよね。
私も昔は「発達支援って何?保育とは関係ない専門的なこと」くらいにしか思っていませんでした。でも毎日保育をして行く上で、もうなくてはならない知識なのではないか?ということに気づいたんです。
そこで、「発達支援の学び」をしようと決意し、たまたま出会ったのが、「児童発達支援士」という資格でした。
「他にも発達的な視点で解決できる困りごとはあるのかな?」
「ボディイメージ以外にも、子どもの行動の背景を理解するヒントが欲しい」
「発達支援って具体的にどんなことなの?」
そんな風に感じている先生は、保育の困ったを解決するための考え方を学ぶことをおすすめします。

ぜひ私と同じように「学び」という選択をしてほしいと思います。
ボディイメージや発達支援の考え方は、運動会以外の場面でもとても役立ちます。日常保育での「なんでこの子はこうなんだろう?」という疑問の答えが見つかるきっかけがあったら素敵だと思いませんか?
↓↓下記の記事に私の学びの体験談をまとめてあるので、保育に「困った」を感じている方はぜひ検討してみてください↓↓
もちろん資格が全てではありませんが、「学ぶ」という選択肢の一つとして、参考にしていただければと思います。

運動会当日、一人ひとりの子どもたちが自分らしい輝きを見せてくれることを心から願っています。そして、先生方の温かい関わりが、子どもたちの成長を支える力になりますように。

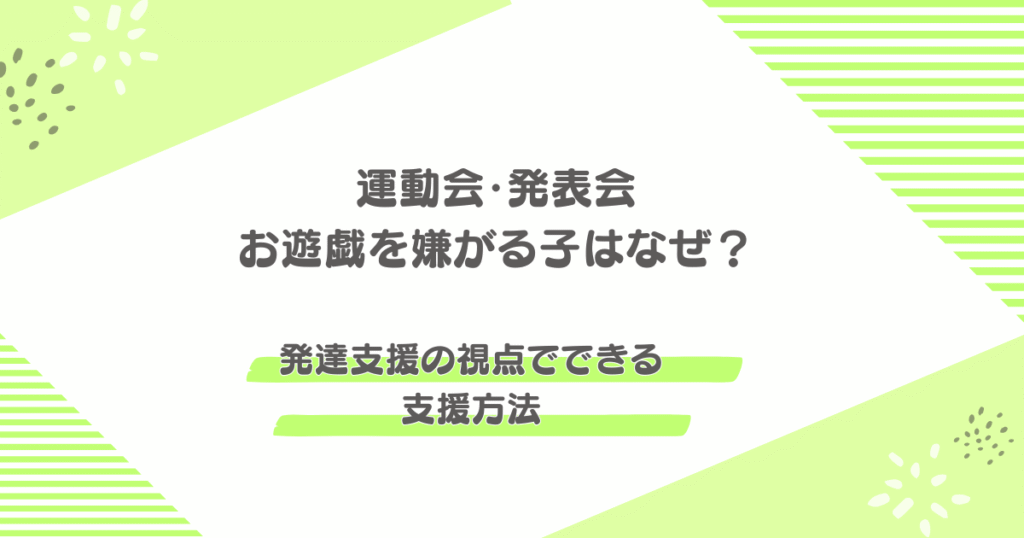

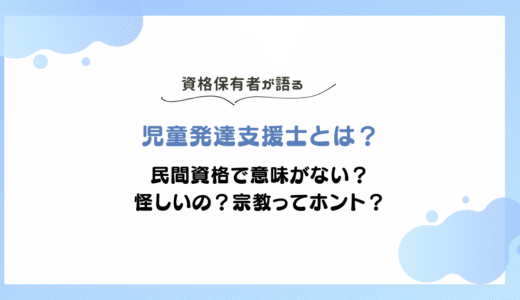
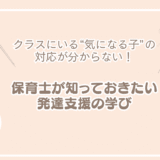
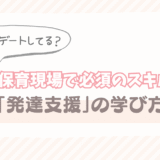
Hey there I am so glad I found your site, I really found you by accident, while I was researching on Aol for something else, Anyways I am here now and would just like to say thanks a lot for a marvelous post and a all round interesting blog (I also love the theme/design), I don’t have time to go through it all at the minute but I have bookmarked it and also added your RSS feeds, so when I have time I will be back to read a great deal more, Please do keep up the awesome job.
It is really a nice and helpful piece of info. I am satisfied that you just shared this helpful info with us. Please stay us informed like this. Thanks for sharing.