※本記事にはプロモーションが含まれています
「みんなー!片付けてー!」って言っても、動かない子が半分以上。
もしかして聞いてない?わざと?それとも理解できてないの?
そんなモヤモヤを抱えながら、毎日保育をしている先生も多いのではないでしょうか。
特に、2歳児クラスから3歳児クラスに上がったタイミングや、初めて年少クラスを担任したときに、「あれ?一斉活動ってこんなに通らないもの?」と戸惑うこと、ありますよね。

「一斉指示は何歳から通るんだろう?」そんな疑問を感じたことはありませんか?
実は、「一斉指示が通る」ようになるには、言葉の理解だけでなく、注意を向ける力・状況を読む力・記憶して行動する力など、いくつもの発達ステップが関係しています。
だから、「まだ通らない」は決して“できない”ではなく、「これから育っていく途中」のサインなんです。焦らなくて大丈夫です。

今回は、「一斉指示は何歳から通るのか?」を、発達段階と環境の視点から整理しながら、子どもが“聞ける環境”をどう作るかを一緒に考えていきましょう。
目次
一斉指示が通るようになるまでの発達段階
一斉指示が通るようになるのは、実はかなり高度な認知能力が育ってからです。年齢ごとに、どんな段階を踏むのか見ていきましょう。
| 年齢 | 理解・行動の特徴 | 指示の通し方のポイント |
|---|---|---|
| 2〜3歳前半 | 名前を呼ばれて初めて「自分のこと」と認識できる | 個別で・視線を合わせて・短く伝える |
| 3歳後半〜4歳 | 模倣で学ぶ/小集団なら通りやすい | 4〜5人単位で伝える/視覚支援を加える |
| 5歳〜就学前 | ワーキングメモリ・抑制機能が育つ | 全体指示が理解しやすくなる/状況判断も発達 |
① 2歳〜3歳前半:個別指示の段階

まずは2~3歳前半(一般的に満3歳クラスの子)の場合。
この時期の子どもは、「〇〇してね」という個別の声かけなら理解できても、「みんな、〇〇してね」という一斉指示はまだ自分のことだと認識しづらい段階です。
言語理解としては2語文レベル。
「ごはん、食べる」「くつ、はく」といったシンプルな指示は通りますが、それも目を合わせて、名前を呼ばれて初めて「自分への指示」だと気づくことがほとんどです。
一斉に伝えるより、まずは「Aちゃん、見て」と視線を合わせてから伝えることが何より大切な時期です。
この段階では、共同注意(大人と同じものを見る力)や言語理解の基盤がゆっくり育っている最中なのです。

私は現場でよく「Tくん、席につくよ」など、個人の名前を呼びこちらを向いたことを確認してから指示を出すようにしています。
② 3歳後半〜4歳:少人数での一斉指示が入り始める

次は3歳後半~4歳(年少~年中クラス)の場合。
3歳後半になると、他の子と一緒に動く経験が増え、模倣で学ぶ力がぐっと伸びてきます。「お友達が片付けてるから、ぼくも」という動きが出てくるのもこの頃です。
ただし、まだ集団内で「自分への指示なのか、他の子への指示なのか」の切り分けは難しい段階。全体に向けて言われても、「自分に言われている」とピンと来ないことがよくあります。
この時期は、4〜5人くらいの小集団での活動なら比較的通りやすく、全体への一斉指示は「聞き逃す」「他のことに注意が向いてしまう」ことがまだ多い時期です。

少しずつ、できる子とできない子の差が出てきますが、それもすべて、発達の段階によるものと捉えるといいですよ。
③ 5歳頃〜就学前:状況全体を見て動けるようになる

最後は5歳以降(年中から年長クラス)の場合。
5歳を過ぎると、ワーキングメモリ(短期記憶)と抑制機能(衝動を抑える力)がぐんと発達します。「聞く→覚える→行動する」という一連の流れが安定してきて、ようやく「一斉指示」が成立しやすくなります。
また、周りの様子を見ながら「あ、今は静かにする場面だな」「先生が前にいるときは座る時間かも」といった状況判断もできるようになっていきます。
この頃から、いわゆる「集団での指示が通る」状態に近づいていくのです。

現場にいると学年によって話を聞く姿勢がどんどん育っていっていることを感じますよね。
発達段階の捉え方
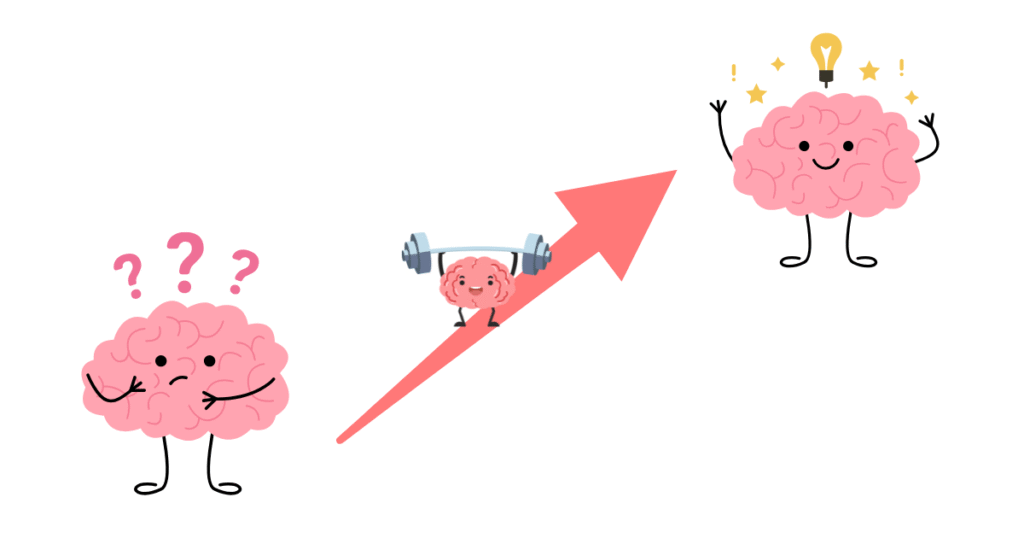
「一斉指示が通らない」という姿には、年齢や発達段階による大きな差があります。2歳児が話を聞けないのは“やる気”の問題ではなく、まだ集団の中で「自分への言葉」として受け取る力が育っていないからです。
発達には順序があります。理解する力・覚える力・他人と気持ちを共有する力が、少しずつ積み重なっていく過程の中で、初めて「一斉指示」が通るようになります。
だからこそ、保育者がその順序を理解しておくことが大切です。「まだ通らない=できない」ではなく、「今はその段階を育てている途中」。その視点を持つだけで、子どもを見る目がぐっと優しく、具体的になります。
発達段階だということは分かっているけど、一斉指示が通らない子をどうしたらいいのかも教えてほしい・・・と感じますよね。

次の章では、「なぜ一斉指示は難しいのか?」という背景をもう少し掘り下げながら、保育現場でできる環境づくりのポイントを紹介していきます。
なぜ一斉指示は難しいの?3つの背景
「言葉はわかってるはずなのに、なんで通らないの?」と感じることもあるかもしれません。でも実は、一斉指示には言葉の理解以外にも、たくさんのハードルがあるんです。
①情報量が多すぎる(同時に複数処理が必要)
一斉指示は「みんなに向けて」言われるので、子ども側としては以下の処理を同時に行う必要があります。
- 先生の声を聞く
- その内容を理解する
- 自分に向けられているか判断する
- 何をするか思い出す
- 行動に移す
こうして見ると、たった一つの指示の裏側で、これだけ多くの処理が同時に行われていることが分かります。

全員に向けて話しているだけのように見えても、脳の中では複雑な“マルチタスク”が起きているのです。

これは大人が思う以上に高度な処理です。特に、注意が逸れやすい子や、情報処理に時間がかかる子にとっては、「途中で止まってしまう」ことがよくあります。
②聴覚刺激より視覚刺激に注意が向きやすい
子どもの脳は、視覚情報のほうが処理しやすい特性があります。つまり、「耳で聞く」よりも「目で見る」ほうが圧倒的に理解しやすいのです。
教室の中にはおもちゃ、友達の動き、窓の外の景色など、視覚的な刺激がたくさんあります。
そんな中で「声だけ」で指示を出しても、注意がそちらに向かないことは自然なことなのです。
③集団内で「自分に向けられている」と気づきにくい
「みんな」と言われたとき、大人は「自分も含まれている」と自然に理解しますが、子どもにとってこれは意外と難しいことです。
特に、まだ自己と他者の境界が曖昧な段階や、自分の名前を呼ばれないと「自分のこと」と認識しにくい段階では、一斉指示は届いているようで届いていないことがよくあります。


分かりやすく図にまとめましたが、このように、各行動の裏で起きる躓きポイントによって、一斉指示が通らない子がいるということを理解しておきましょう。
一斉指示が”通る”ようになるための環境づくり
一斉指示が通らないのは、子どものせいでも保育士のせいでもありません。環境と伝え方の工夫次第で、ぐっと通りやすくなるのです。
① 合図をする
まず大切なのは、「これから先生の話を聞くよ」という“切り替えスイッチ”を明確にすること。手拍子や音など、耳と目の両方で分かる合図を作りましょう。
- 「パンパンパン」と手拍子をして注意を引く
- 「ピンポンパンポーン♪」など、気持ちがこちらに向くきっかけを作る
音と動作をセットにすることで、脳が“これから聞く時間だ”と切り替わりやすくなります。

学校の授業や音楽の授業で、始まりの「起立、礼、着席」などの声をかけるのも理にかなっているということですね。園での“合図の経験”が積み重なることで、就学後の集団生活でも落ち着いて動けるようになります。
② 情報を分けて伝える
「片付けて、手を洗って、座ってね」と一気に言われると、子どもの頭の中は「???」になってしまいます。
★ポイントは、1文に1行動だけ伝えること。
- 「まず、片付けよう」
- 「終わったら、手を洗おうね」
- 「洗えたら、ここに座ってね」
段階的に伝えると、子どもが自分で整理できる余白が生まれます。

発達支援の現場では、ホワイトボードに写真カード貼り「今はこれ」と指さすという方法も利用されています。視覚+聴覚の両方から理解を深めることでより指示が通りやすくなるんです。
③ 聴覚より“見える化”を意識する
子どもは視覚優位です。つまり、言葉だけで説明されるよりも、見て分かる・真似できる形の方が理解が早いのです。
- 「座ろうね」→ 実際に座って見せる
- 「片付けるよ」→ 写真カードを見せる
- 「静かにね」→ 指を口に当ててジェスチャー
言葉+動きで伝えることで、脳が「あ、こういうことか」と整理しやすくなります。先生が見本を見せながら一緒に行動をすることも、支持を通りやすくする人的環境設定になりますよ。

「指示が通らない子」ではなく「まだ通りにくい環境」なのかもしれません。伝え方を変えるだけで、ぐっと届く瞬間があります。
「できない=やる気がない」ではない
一斉指示が通らないと、つい「聞いてないのかな」「わざとやってるのかな」と感じてしまうこともあるかもしれません。
でも、“通らない”のは、理解力や注意力の発達段階の違いであることがほとんどです。やる気がないわけでも、ふざけているわけでもないのです。
発達のステップを知らないと、つい「なんでできないの?」と叱ってしまいがちですが、それでは子どもも混乱してしまいます。

大切なのは、他の子と比べるのではなく、「今この子はどの段階かな?」と見極める目を持つこと。そして、その段階に合った伝え方を工夫していくことです。
まとめ “指示が通らない”は育っている途中のサイン
一斉指示が通らないことは、決して「困ったこと」ではなく、「これから育つ力」のサインです。
2〜3歳なら個別で、3〜4歳なら小集団で、5歳以降は全体への指示が通りやすくなる。そんな発達の流れを知っておくだけでも、日々の保育がぐっとラクになります。
焦らず、子どもの発達ペースに寄り添いながら、“指示が通る環境”を一緒に作っていきましょう。
子どもの行動の背景を知ることで、保育はもっと楽になります。
次は「クラスにいる“気になる子”への関わり方」も、ぜひ読んでみてください。
また、「発達支援の学び方」を知っておくと、現場での声かけや対応に自信が持てるようになります。
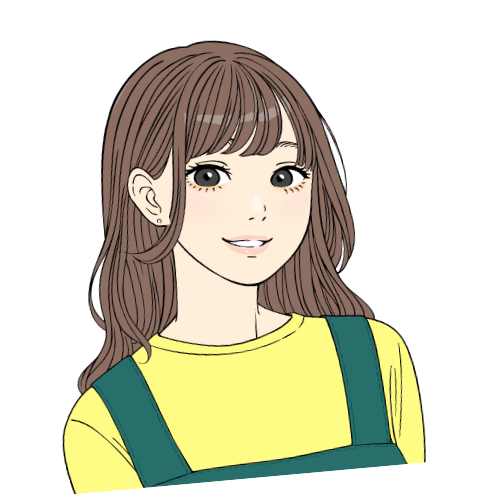
下記の関連する記事も参考にしてくださいね。

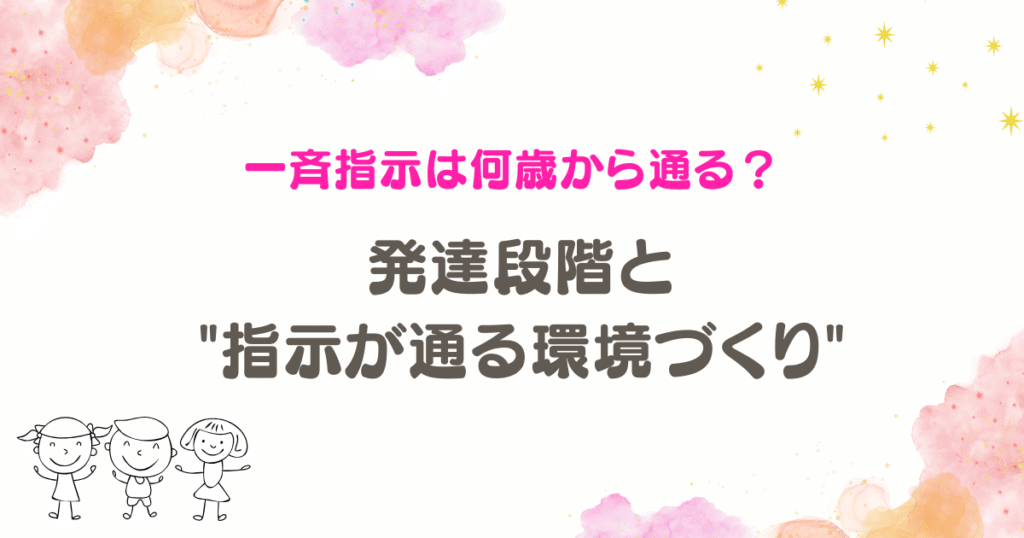

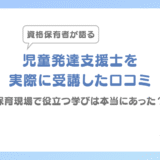
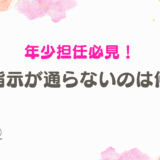
Very interesting topic, thankyou for posting.
We’re a group of volunteers and starting a new scheme in our community. Your web site offered us with valuable information to work on. You have done a formidable job and our whole community will be grateful to you.