※本記事にはプロモーションが含まれています
「うちの子、ちょっと落ち着きがないかも…」
「言葉が周りの子より遅れてる気がする…」
「かんしゃくが激しくて、対応に困ってしまう…」
1歳半〜3歳ごろの子育て中、そんなふうに感じる瞬間はありませんか?日々の育児に一生懸命な中で、「これって大丈夫なのかな?」と不安になるのは、どの保護者にもあることです。
目次
不安でも大丈夫
SNSや育児サイトには「発達の目安」や「〇歳でできることリスト」があふれていて、知らず知らずのうちに他の子と比べてしまう…そんな経験、ありませんか?
でも、子どもの成長は本当にひとりひとり違います。ちょっと気になることがあっても、発達の個性として自然に育っていくケースもたくさんあります。
とはいえ、「少し気になる」と感じた今のあなたの気持ちは、とても大切なもの。

だからこそ、今回は「不安なときこそ家庭でできる関わり方」をテーマに、今日から試せるシンプルなヒントをお伝えします。
子どもの発達に「なんとなく不安」を感じるとき
親の直感は案外正確
「なんとなく気になる…」という親の感覚は、実はとても大切なものです。毎日子どもと過ごす中で感じる「ちょっとした違和感」は、見逃してはいけないサインかもしれません。
よくある心配事としては、
- 同じ年齢の子に比べて言葉の発達が遅い
- 落ち着きがなく、じっとしていられない
- 指示が通りにくい、言葉が入りにくい
- 他の子とうまく遊べない
- かんしゃくが強く、なかなか収まらない
- 特定の音や感覚に過敏に反応する
このような違和感を感じている、という保護者の方とたくさん出会ってきました。
過剰な心配は負担になることも
一方で、「発達障害かも?」と早い段階から不安を抱えすぎるのも、親子にとって負担になることがあります。
インターネットで検索すると、症状のチェックリストなどが出てきて、「うちの子もこれに当てはまる…」と不安が増幅することも。
大切なのは、不安を感じたら「どうしよう」と悩むだけでなく、「今、家庭でできること」を前向きに考えること。そして必要なら専門家に相談する勇気を持つということです。
不安なときこそ、まず家庭でできる5つの関わり方
発達に不安を感じたとき、まず家庭でできることがたくさんあります。以下の5つのポイントは、お子さんの発達特性に関わらず、すべての子どもの成長を支える基本になるものです。
1. 声かけは短く、ゆっくり、目を見て
お子さんに何かを伝えるとき、長い説明や複雑な言葉は避けましょう。特に言葉の理解や処理が苦手なお子さんの場合は、シンプルな言葉かけが効果的です。
実践例
- ✕「走らないで」⇒ 〇「歩いてね」
- ✕「そっちは危ないから、登らないで」⇒ 〇「ここは危ないよ。降りてね」(近くに行って)
ポイント
- 伝えたいことを短い言葉(1〜3語程度)に絞る
- 視線を合わせてから話しかける
- 必要なら言葉と一緒にジェスチャーを使う
- 穏やかでゆっくりとした口調で話す
言葉より先に体が動いてしまうお子さんには、言葉だけでなく、視覚的な手がかり(絵カードや実物を見せる)も効果的です。
また「〇〇しないで!」という否定的な声かけより、「△△してね」というしてほしい行動をつたえることも効果的です。
2. スキンシップと遊びの時間を意識して取る
発達が気になる時期こそ、親子の触れ合いが大切です。
特に脳の発達が著しいこの時期、スキンシップを通じた安心感は、子どもの情緒の安定につながります。
実践例
- 抱っこやおんぶで体の感覚を整える
- 「いないいないばあ」などの顔を見合う遊び
- 体を使った遊び(くすぐり、追いかけっこ)
- 手遊び歌で一緒に楽しむ
ポイント
- スマホやテレビから離れて、子どもと向き合う時間を作る(1日15分でも効果的)
- 子どもの好きな遊びを観察して、それを発展させる
- 遊びの中で「待つ→反応する」のやりとりを意識する
落ち着きがないように見えるお子さんも、好きな遊びには集中できることが多いもの。その興味を大切にしながら、少しずつ遊びの幅を広げていきましょう。
忙しい毎日かもしれませんが、スマホやテレビを消し、お子さんだけと向き合う時間、触れ合う時間をできる限り取ってあげるようにして下さい。

子どもの心が満たされることで、落ち着きのなさや、攻撃的な態度が消失していった事例もたくさん見てきたました。すぐに効果は感じないかもしれませんが、根気よく子どもに向き合う時間を作ってもらえたらなと思います。
3. 気になる行動も「叱るより理解」を心がける
「どうしてじっとしていられないの?」「どうして言うことを聞かないの?」と感じる場面は多いかもしれません。
しかし、その行動には子どもなりの理由があることが多いのです。
例えば
- すぐどこかへ行ってしまう
→ 新しい刺激を求める好奇心の表れかも - 同じ遊びを繰り返す
→ 予測できる安心感を求めているのかも - 特定の食感が苦手
→ 感覚の過敏さがあるのかも
ポイント
- 「困った子」ではなく「困っている子」という視点で見る
- 叱る前に「なぜそうするのか」を考えてみる
- 問題行動を減らすより、良い行動を増やす関わりを意識する
子どもの行動を理解しようとする姿勢は、親子の信頼関係を深め、子どもの自己肯定感を育みます。

これは少し難しいかもしれませんが、「子どもの理解を深めるための方法」について、この後紹介していきますので、最後まで読み進めていってもらえればと思います。
4. 比較しすぎない・情報に振り回されない
「同じ月齢の子はもうこんなことができている」「発達の目安ではこの時期にはこうあるべき」…そんな情報に悩まされることはありませんか?
心がけたいこと
- SNSや育児書の「平均値」や「目安」は参考程度に
- 他の子との違いよりも、その子自身の成長に目を向ける
- 「できないこと」より「できるようになったこと」に注目する
ポイント
- 子どもの「得意なこと」「好きなこと」をリストアップしてみる
- 1ヶ月前と比べて「できるようになったこと」を記録する
- 気になることがあっても、まずは見守る期間を持つ
子育ては長い道のりです。一時的な遅れや心配事も、ゆっくりと成長とともに解消していくことが多いものです。

まずは目の前の子どものいいところをたくさん見つけていきましょう。
5. 相談してもいい、という気持ちを持つ
「様子を見よう」と思いつつも、心配が続くなら、専門家に相談してみることも選択肢の一つです。早めの相談は早めの安心につながります。
相談先の例
- 市区町村の保健センター(保健師さん)
- 子育て支援センター
- かかりつけの小児科医
- 市区町村の発達相談窓口
ポイント
- 相談は「診断を受ける」ことではなく「プロの目で見てもらう」こと
- メモを用意して、具体的な様子や心配事を伝えられるようにする
- パートナーや家族と一緒に相談に行くとよい
「相談するほどのことかな」と迷ったら、それは相談するタイミングかもしれません。プロの視点からのアドバイスが、家庭での関わり方のヒントになることも多いのです。
悩んでいるのであれば、通っている園があるのであれば保育士さんに。未入園なのであれば市の保健センターなどの保健師さんに相談してみるといいですよ。
心配なまま抱え込まないで。必要なら支援の手も
少し不安を煽ってしまうかもしれませんが、もし専門家への相談を経て「発達の特性がある可能性」や「発達を促す支援が有効」と言われたとしても、それは決して悪いことではありません。
むしろ、お子さんの特性を理解し、適切な関わり方を知ることで、親子の毎日がぐっと楽になることがあります。
「療育」や「発達支援」は特別なことではなく、お子さんの成長を後押しするための一つの選択肢。早期からの適切な支援は、お子さんの可能性を広げることにつながります。
最初の一歩として、市役所や保健センターに「子どもの発達について相談できる場所はありますか?」と尋ねてみるとよいでしょう。多くの自治体では、無料で相談できる窓口が用意されています。
子どもの発達をもっと理解したい方へ
「子どもの発達について、もっと体系的に学びたい」 「子どもの特性に合った関わり方を知りたい」
そんな方には、子どもの発達について専門的に学べる講座がおすすめです。
最近では、保育士だけでなく、保護者の方が受講されることも増えている「子ども発達障がい支援アドバイザー」の資格講座(ユーキャン)もあります。
「うちの子のために、ちゃんと学びたい」と思う親御さんからも、選ばれているんですよ。
この講座では
- 子どもの発達の道筋を体系的に学べる
- 発達障がいの特性や支援方法を知ることができる
- 子どもの行動の理由を理解するヒントが得られる
- 日常生活での具体的な関わり方が分かる
専門的な知識を身につけることで、お子さんへの理解が深まり、日々の関わり方に自信が持てるようになります。
また、周囲の子どもたちへの理解も広がり、地域や社会での支援の輪を広げることにもつながるでしょう。
まとめ:心配なのは、愛している証拠
子どもの発達を心配するのは、親として自然な気持ちです。その心配は、お子さんへの深い愛情の表れでもあります。
どんなお子さんにも、その子なりの成長のペースがあります。早い子もいれば、ゆっくりな子もいる。そして、どの子にも必ず「得意なこと」と「苦手なこと」があるものです。
大切なのは、お子さんの個性を尊重しながら、必要な支援や関わりを模索していくこと。そして、親自身も一人で抱え込まず、周囲の理解や専門家の知恵を借りながら歩んでいくことです。
今日からできることを、少しずつ実践してみてください。小さな変化の積み重ねが、お子さんの成長を支え、親子の笑顔を増やしていくはずです。
関連記事
子ども発達障がい支援アドバイザーってどんな資格?
実際の内容・受講方法をわかりやすく解説しています。

「うちの子、これでいいのかな?」と不安になったとき、この記事が少しでもあなたの心の支えになれば幸いです。

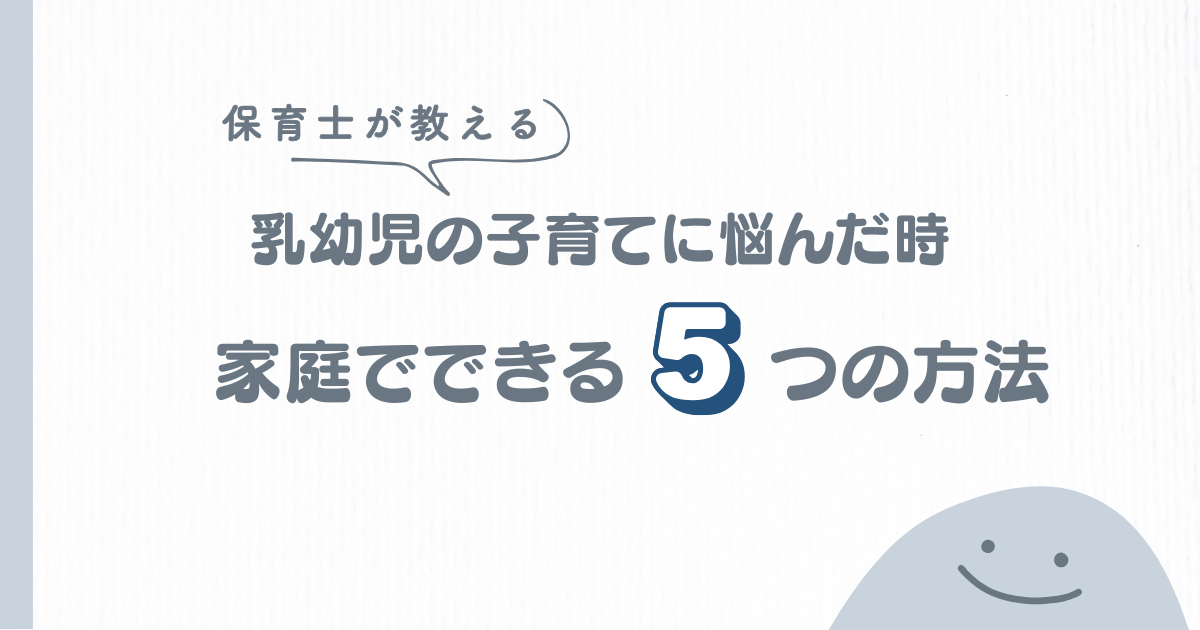

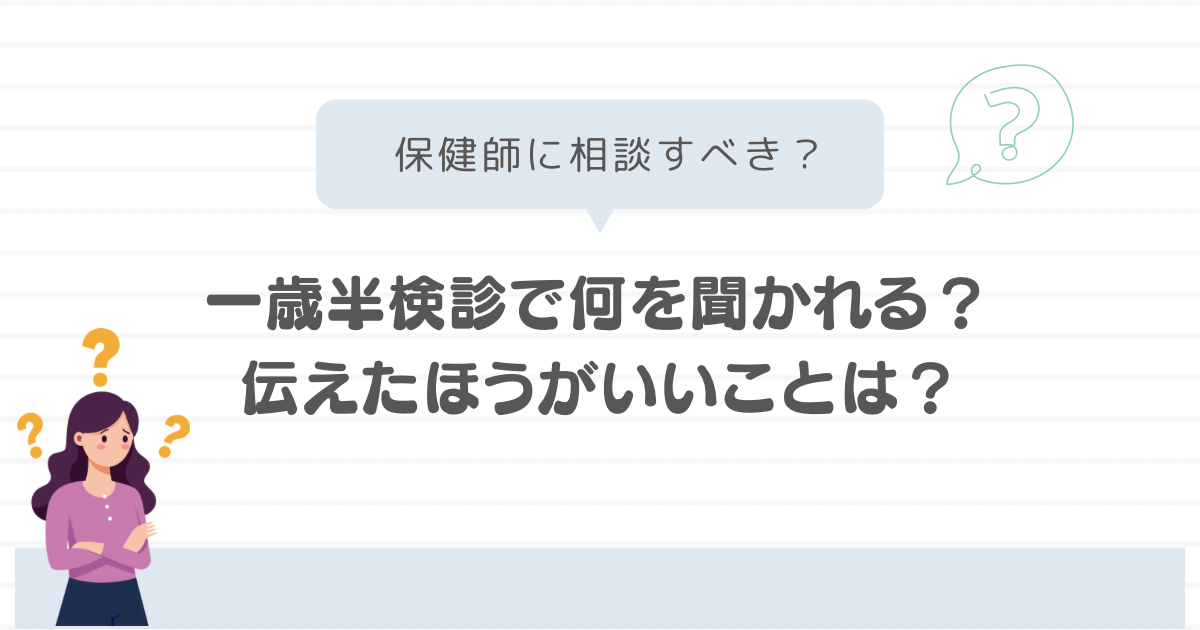
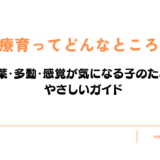
Keep up the good work, I read few posts on this site and I conceive that your site is very interesting and holds bands of fantastic information.