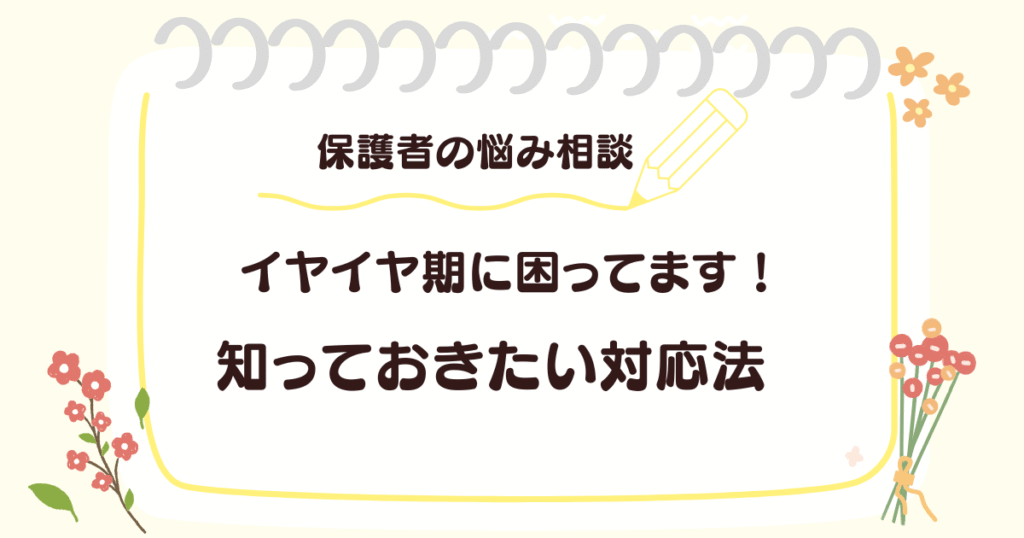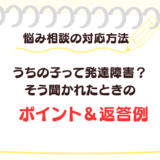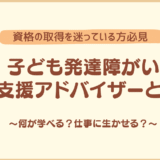※本記事にはプロモーションが含まれています
「先生、うちの子のイヤイヤがひどすぎて…」
保護者からこんな相談を受けたことはありませんか?
先生ならどのように答えますか?

今回は「イヤイヤ期に困っている保護者対応」について学んでいきましょう。
目次
保護者の悩みに寄り添う第一歩
保育園での送迎時、保護者からちょっとした相談を受けることは少なくありませんよね。
イヤイヤ期の子どもたちに手を焼き、保護者の表情には疲労と不安が見え隠れしているかもしれませんね。
毎日のイヤイヤ攻撃に、多くの保護者が「このままでいいのか」「自分の対応が間違っているのでは」と自信を失いがちです。
そんな保護者の心に響く言葉をかけられるかどうかが、プロの保育士としての腕の見せどころ。この記事では、保護者が「ああ、相談してよかった」と感じる対応術と、明日からすぐに実践できるアドバイス例をご紹介します。
イヤイヤ期の保護者が抱える5つの悩み

イヤイヤ期の子どもを持つ保護者の多くは、こんな悩みを抱えています。
- 朝の準備が地獄絵図に
「着替えも、歯磨きも、靴下一つ履くのにも『イヤ!』と言われ、毎朝時間との戦いです…」 - 公共の場での大泣き
「スーパーでおもちゃを買ってほしくて大泣き。周りの目が痛くて…」 - 食事拒否の連続
「昨日まで好きだったメニューも突然『イヤ!』。栄養が心配です」 - 他の子と比較して不安に
「お友達のお子さんはもっと素直なのに、うちの子だけこんなに手がかかるのでしょうか」 - 自分の育児に自信喪失
「私の接し方が悪いのかもしれません。どうしたらいいか分からなくて…」
保育士として大切なのは、これらの悩みをしっかり受け止め、保護者が自分を責めないよう支えることです。
保護者が安心する!イヤイヤ期の本質を伝える4つのポイント
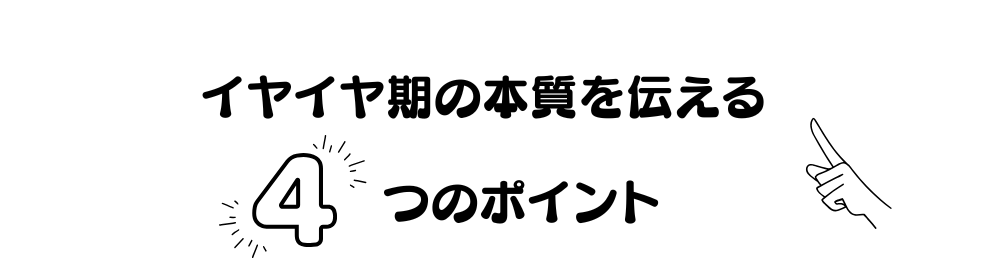
では早速、そんな保護者への声のかけ方のポイントを紹介していきましょう。
まず、「イヤイヤ期」の本質を保護者に伝えましょう。これだけで多くの保護者が「そうだったのか」と安心します。
① 「イヤイヤは成長の証」と伝える

保護者の方は「イヤイヤ期=大変な時期」と感じていることが多いですが、実はこの「イヤ!」という自己主張こそ、成長の証です。ここで大切なのは、保護者が「イヤイヤすること=悪いこと」と捉えないように伝えてあげること。まずはその点を心掛けてくださいね。
- 「『イヤ!』と言えるようになったのは、お子さんの中に『自分の意志』が芽生えた証拠です。自我が育っている、素晴らしい成長のサインなんですよ。」
- 「今までは受け入れていたことに対して『イヤ!』と言えるようになったのは、それだけお子さんの世界が広がってきたということですね。自分の気持ちを表現できるようになったのは、とても大切な成長の一歩ですよ。」
- 「『イヤ!』としっかり主張できるのは、お子さんが安心している証拠でもあります。自分の気持ちを出せるのは、それだけご家庭の中で信頼関係が築けているからですね。とても素敵なことですよ。」
② 「全ての子どもが通る道」と安心させる

次は、イヤイヤ期が一時的なものであり、成長の一環であることを保護者に理解してもらえるような声掛けをしていきたいですね。
- 「2歳前後のイヤイヤ期は発達の正常なステップです。個人差はありますが、程度の差こそあれ、ほとんどの子どもが通る道なんですよ。」
- 「2歳前後のイヤイヤ期は、発達の中で自然に出てくるものです。もちろん個人差はありますが、ほとんどの子どもが通る道なので、あまり心配しすぎなくても大丈夫ですよ。」
- 「『うちの子だけ?』と不安になるかもしれませんが、実はほぼ全ての子どもがイヤイヤ期を経験します。この時期にたくさん自己主張することで、少しずつ自分の気持ちを伝える力を育んでいくんですよ。」
③ 「イヤイヤの裏側」を読み解く視点を提供

保護者は「ただイヤと言っている」と感じがちですが、その裏には理由があることを伝えましょう。この視点を伝えることで、子どもの気持ちを探りながら対応できるようになり、少しずつ余裕を持てるようになりますよ。
- 「『イヤ!』の裏には、『自分でやりたい』『もっと遊びたい』『疲れている』などの気持ちが隠れています。『なぜイヤなのか』を考えると対応のヒントが見つかりますよ。」
- 「『イヤ!』と言うのは単なるわがままではなく、『こうしたい』『まだ遊びたい』『助けてほしい』など、何かしらの気持ちの表れです。その背景を探ることで、適切な対応が見えてきますよ。」
- 「『イヤ!』の裏側には、『自分の思い通りにしたい』『まだ準備ができていない』『気持ちをわかってほしい』などの理由があります。子どもが伝えたいことに気づけると、関わり方のヒントになりますよ。」
④ 「全てに対応する必要はない」と負担を軽減

イヤイヤ言っている我が子に全力で向き合い疲れてしまっている保護者もいることでしょう。そこで、保護者の“ちゃんと向き合わなきゃ”というプレッシャーを和らげることを意識した声掛けもいいですね。
- 「イヤイヤ全てに丁寧に対応する必要はありません。安全面に問題なければ、時には『そっか、イヤなんだね』と受け止めてスルーするのも大切な対応ですよ。」
- 「毎回イヤイヤに向き合うのは大変ですよね。命やケガの危険がない場面なら、無理に正そうとせず、受け流すことで親子のストレスが減ることもあるんです。」
- 「子どものイヤイヤすべてに反応しようとすると、保護者が疲れ切ってしまいます。『今は無理だな』と思ったら、ひと呼吸置いてスルーするのも立派な対応ですよ。」
明日から試せる!イヤイヤ対策グッズ&テクニック5選
保護者が明日から実践できる具体的な対応策を紹介します。保育園での実践例も交えると、より説得力が増しますよ。
① 選択肢を与える方法
「着替えるのイヤ!」→「青いTシャツと赤いTシャツ、どっちにする?」
このように子どもに選択肢を与えることで、イヤイヤを軽減させ、自分で決めて行動するという流れに持っていけるとスムーズにいくこともあります。
② タイマーで見通しを持たせる
「まだ遊びたい!」→「このタイマーが鳴ったら片付けようね」
時間を見える化するタイマーは、見通しを持つことを苦手とするお子さん用に、保育現場や教育現場でもよく使われています。‟あとこれくらい” と先の見通しを持てることで、イヤイヤから気持ちを切り替えることができます。
↑ このタイマーは保育現場や、発達支援の現場などでも本当に良く利用されていて、子育てママにも人気が出ているんですよ!
目に見える形で伝えることで、より明確に伝えることができ、イヤイヤ期の子どもたちも気持ちが切り替えわる可能性が高いことを伝えてあげましょう。
③ 気持ちを言葉にしてあげる
「イヤイヤ大泣き」→「まだ公園で遊びたかったんだね。楽しかったもんね」
このようにその都度、気持ちを代弁すると気持ちを切り替えることができますよ。
そんな時期におすすめの絵本もあるので、たまに読んであげていいですね。
④ 褒める場面を増やす
「いつもイヤイヤで…」→「服を自分で選べたね!すごいね!」
「服を着替えることができたらご褒美シールね♡」など、褒められたりご褒美をもらえたりすることで気持ちが切り替わることもあります。
今後トイトレなどでもことができるので、お気に入りのシールを用意してみるのもいいですね。台紙にどんどんと貼っていくことで、たくさん頑張ったが可視化できるの良いアイディアです。
⑤ ルーティンを作る
「毎朝バタバタで…」→やるべきことを可視化する
登園前にやって欲しいことを一緒に絵カードなどにして壁に貼っておくなど、ルーティン化することで、イヤイヤにならず当たり前にできるようにすることも一つの方法です。
ただ、イヤイヤ期はそんなルーティンがイヤイヤということもあるので、効果があるときだけ活用するといいかもしれないですね。
実践!保護者の心に響く5つの答え方

具体的な会話例をご紹介します。保護者との会話で、ぜひ参考にしてみてください。
パターン① 共感から入り、成長の証だと伝える
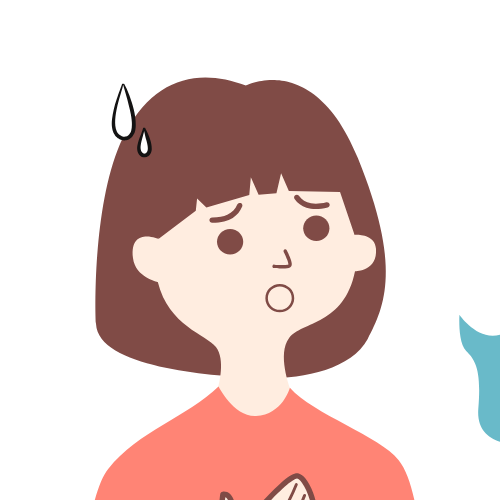
朝から晩までイヤイヤで、疲れ果ててしまって…

本当に大変な時期ですよね。毎日のことだと、精神的にも体力的にも消耗しますよね。でも、これはお子さんの中に『自分の意志』が育ってきた証拠なんです。今は『自己主張の練習期間』と思って、長い目で見守ってあげると少し楽になるかもしれませんね
パターン② 園での様子を伝えて安心させる

うちの子だけこんなにひどいのでは…と不安になります

〇〇ちゃんは、園でもお着替えの時やお片付けの時に少し『イヤイヤ』することがあります。でも、同じクラスの子も半数以上が似たような状況です。この時期の特徴なので、お母さんの育て方の問題ではありませんよ。もちろん個人差もありますが、どの子も通る道なので、心配する必要はないですよ。でももし、困っている場面があれば具体的にお話いただければ園でどのようにしているか、お伝えさせていただくこともできるので、いつでも言って下さいね。
パターン③ 具体的な対応策を提案する
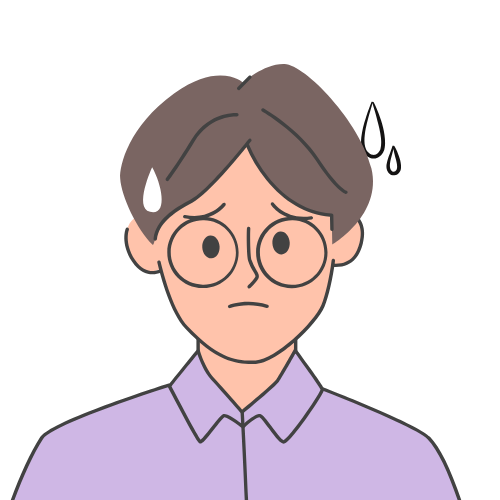
食事の時間が本当に大変で…特に野菜はいつもイヤイヤ・・全く食べてくれないんです

食事の拒否、大変ですよね。園では『青いお皿と黄色いお皿、どっちがいい?』と選んでもらったり、『1つだけ食べてみようか』と少し減らしたりすると食べ始めてくれることがあります。その他にも好きなキャラクター名を挙げて「プリキュアみたいにかわいく食べる?」「仮面ライダーみたいにかっこよく食べる?」「わ~恐竜みたい!」「お口の中に新幹線が入りまーす」など、気持ちを切り替える声かけも効果的ですよ。
全部食べなくても、少しでも食べられたら大成功!と考えて、ハードルを下げてみるのはいかがでしょうか
パターン④ スルーテクニックを伝授する

何をしてもイヤイヤが止まらなくて・・・

分かります!もういい加減にして!と思ってしまうことありますよね。
時には、わざと聞こえないふりをしてスルーするのも有効ですよ。
危険なことでなければ、『そうなんだね』『そっか、嫌だったんだね』と一言受け止めて、さらっと流す。そうすると、意外とすぐに気持ちが切り替わることも多いんです。毎日イヤイヤと付き合っていると疲れてしまうので、「まあいいか」という妥協も取り入れてみてください。
パターン⑤ イヤイヤ期の終わりを見せる

この状態がずっと続くのかと思うと絶望的で・・・

大変な時期ですが、必ず終わりが来ますよ。3歳半から4歳頃には、言葉も増え、自分の気持ちを表現できるようになり、格段にコミュニケーションが取りやすくなります。
今この瞬間が大変!絶望的!と感じ気持ちも暗闇の中かもしれませんが、必ず抜けられます。一緒に焦らず見守っていきましょうね。
まとめ:保護者の心に寄り添う保育のプロとして
イヤイヤ期の相談は、保育のプロとしての真価が問われる場面です。単なる対処法を伝えるだけでなく、保護者の気持ちに寄り添い、「一人じゃない」と感じてもらえる言葉かけを心がけましょう。
今日から実践したい3つのポイント
- まずは「大変ですね」と共感から始める
- 具体的なエピソードを交えて「成長の証」だと伝える
- すぐに試せる対応策と役立つグッズなどを1〜2つ紹介する

保育士の一言で、保護者の肩の荷が下りることもあります。今日からの保護者対応に、この記事のアイデアをぜひ活かしてみてください。
保護者対応力を高めたい保育士さんへ
保護者対応は、保育の中でも特に「正解がわからない」と感じやすい場面です。
対応に迷ったり、自分の言葉に自信が持てなかったり…。そんなふうに感じている保育士さんは、決して少なくありません。
だからこそ、知識や考え方の引き出しを増やすことで、自分の中に「対応の軸」ができ、安心して保護者と関われるようになります。少しでも自信を持ちたいと感じたときは、学びの機会を活用してみてください。
おすすめの本
もっと保護者対応に自信を持ちたい方へ
イヤイヤ期は、子どもにとっても保護者にとっても試練の時期。
保育士として寄り添いたい気持ちはあっても、
「どう声をかければよかったんだろう」と悩む場面もありますよね。
そんなときに役立つのが、
ユーキャンの「心理カウンセリング講座」
この講座では、
- 不安を抱える人への“聴き方”
- 気持ちに寄り添いながら伝える“共感の言葉”
など、保護者対応にそのまま活かせるスキルが学べます。
難しい専門知識ではなく、日々の関わりの中で使える内容ばかり。
「もっと安心感のある関わりがしたい」と思ったとき、きっと自信につながる学びになりますよ。
「もっと力になってあげたい」そう思ったときが学びのチャンスです。焦らず、できることから一歩ずつ。これからも、保護者と子どもにとって頼れる存在であり続けてくださいね。