※本記事にはプロモーションが含まれています
保護者から「うちの子って発達障害なんですかね?」と聞かれたとき、先生ならどう答えますか?
急に質問をされると、「え~と・・・」と困ってしまうことでしょう。
そこで今回は、保護者の悩み相談対応シリーズ
「うちの子って、発達障害なんですか?」と聞かれたときの対応法について学んでいきましょう。

この記事を読んでおけば、いざとなったときに慌てることなく対応できますよ!
目次
【結論】容易な返答はNG

結論からお話します。
そのような発達障害に関する質問などに対し、容易な言葉を使って返答をすることは絶対に避けましょう!
これは保育士さん全員、しっかりと学んで欲しい内容です。では今からその理由を解説していきますね。
絶代にタブーな返答
- 「発達障害かもしれないですね・・・」
- 「実は私も思っていました」
- 「大丈夫ですよ」
これだけは声を大にして伝えます!絶対にこのような返答はしないでください。
まず大前提として ‟私たち保育士は、医者ではありません。”
なので、「発達障害かどうか」を尋ねられても、YES・NO とはっきり返事をすることは絶対にしないでください。
タブーな理由は?
- 診断権限がない → 保育士は医師ではないため、断定することはできない
- 保護者の不安を助長することもある → 「かもしれない」と言われると、逆に必要以上に不安になる
- 誤解を招く可能性 → 「大丈夫」と言った後に診断がついたら信頼を失う
ピックアップした項目について詳しく解説していきますね。
発達障害に関する質問に対して、軽々しく返答することがタブーである理由はいくつかあります。
まず、保育士には診断権限がない という点が大前提です。
保育士は子どもの発達に関して専門的な知識を持っていますが、それはあくまで「成長の見守り」と「支援」に関する知識です。医学的な診断は医師や専門機関でなければできません。保護者が「うちの子、発達障害でしょうか?」と聞いてきたとしても、「はい」「いいえ」と断言することは、専門的な立場として適切ではありません。
さらに、保護者の不安を助長する可能性もあります。もともと不安を感じている保護者に対し、「かもしれないですね」と曖昧な表現をすると、「やっぱりそうなのかも…」と、確証がないまま悩みが深まってしまうことがあります。発達には個人差があり、一時的な成長の遅れが後に追いつくこともあるため、焦って断定することは避けるべきです。
誤解を招く可能性がある ことも大きな理由です。例えば、「大丈夫ですよ」と軽く伝えてしまった場合、保護者は安心して専門機関に相談しないかもしれません。しかし、後になって医師から正式に発達障害の診断が下された場合、「先生は大丈夫って言ったのに…」と、園や保育士への信頼が揺らぐ可能性があります。
このように、安易な返答をしてしまうことで、保護者の不安を必要以上に強めたり、保育士の信頼を損なったりするリスクがあるため、慎重に対応することが大切です。では、実際にどのように対応すればよいのか、具体的な方法を見ていきましょう。
実践!保護者との会話テクニック
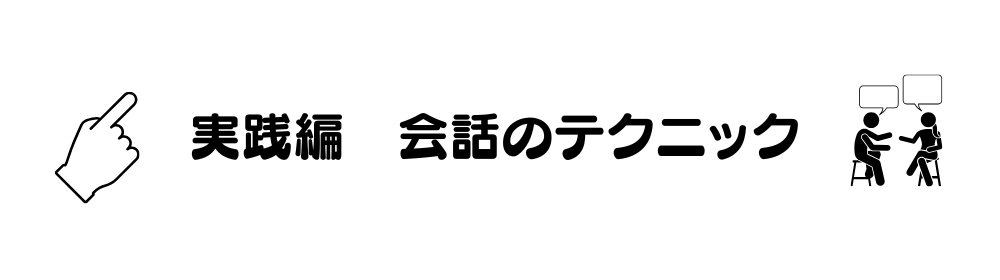
では実際に保護者から「うちの子って発達障害?」と聞かれたときの返答法について学んでいきましょう。まず大前提として、以下の3つのことを心掛けてください。
- 保護者の気持ちに寄り添うこと
- お子さんの成長を一緒に見守る視点
- 園での様子を具体的に伝えること
シーン1:最初の相談を受けたとき
「先生ちょっと相談なんですけど・・・うちの子、ちょっと他の子と違うような気がするんです・・・。」
こんな風に聞かれたらまずは保護者の気持を受け止めていきましょう。

「いつもお子さんのことをよく見ていらっしゃいますもんね。どんな点が気になっていますか?ゆっくり聞かせてください」
ここで、気を付けたいのが、保護者のお話を最後まで聞くことに徹してください。もし、先生自身が ‟その子の行動が気になる” と思っていても、まずはじっくり耳を傾けましょう。
それ以外にも
- 「どうしてそう感じていらっしゃるのですか?」
- 「どういうときにそう感じられるのですか?」
- 「朝や帰宅後の様子はどうですか?」
- 「食事のときはどんな姿勢で食べていますか?」
- 「お家ではどんなことを話してくれますか?」
- 「興味を持つものや好きなことに変化はありましたか?」
- 「寝る前やお風呂の時間はどんな様子ですか?」
- 「お家と園で違いを感じることがあれば教えてください。」
など、基本的に傾聴の姿勢から入りましょう。
その後、保護者が具体的な子どもの姿や、気になる行動などをお話ししてくださったら、優しく相槌を打ちながら耳を傾けてくださいね。
- 批判せず、まずは話を聞く
- 保護者の不安な気持ちを否定しない
- 具体的な状況を優しく聞き出す
シーン2:具体的な行動について話すとき
次に保護者が具体的に気になる姿をお話ししてくれた際のイメージもしておきましょう。
- 「いつも集中力が続かないんです」
- 「お友達とうまく遊べないんです」
- 「こだわりが強く、よく癇癪を起すんです」
- 「言葉がすごく遅くって・・・」
きっと、家での困りごとを保護者の方はお話してくれることでしょう。

「確かに製作活動のときは少し難しそうな時もありますが、お絵かきの時間にはすごく集中して活動に取り組んでくれていますよ。」
こんな風に、確かにそうかもと思う点に関してはあまり強く言わず、そうでない時もあるということも伝えてあげましょう。発達障害なのかも・・・と心配になって相談してきているという時点で、我が子のマイナス面ばかりが目についてしまっている可能性があります。
そのため、園生活における良いエピソードも添えてお伝えしてあげるといいでしょう
- 「先日の外あそびの時間に、泣いている年少さんの頭をヨシヨシとしてあげていて、G君の優しさを感じましたよ」
- 「お片付けがとても上手で、しっかりと決まった場所に片付けてくれるので助かっています!」
- 「○○の場面では戸惑うこともありますが、サポートするとすぐに取り組めることが多いですよ。」
- 「おもちゃの貸し借りは少し苦手なこともありますが、お友だちに興味を持っている様子もあります。」
他にも、素敵だなと感じたエピソードがあればたくさんお話してあげてくださいね。
- 欠点だけじゃなく、長所も必ず伝える
- ネガティブな言葉は使わない
- 成長の可能性を感じさせる
発達には個人差があることを伝える
子どもの成長は一人ひとり違います。つい周りと比べてしまいがちですが、以下のような違いはよくあることということもお伝えするといいですね。
- 「言葉が早く出る子もいれば、じっくり考えてから話し始める子もいますよ」
- 「運動が得意な子もいれば、手先を使う遊びが好きな子もいます」
- 「家庭ではできることが、園では難しく感じることもあるんです」(その逆も)
- 「お子さんそれぞれに得意なこと、苦手なことがありますよ。」
- 「一人ひとり、興味を持つタイミングが違いますね。」
- 「言葉が増える時期も、お子さんによってさまざまですよ。」
「周りと違う=発達障害」とすぐに結びつけるのではなく、お子さんのペースを大切に見守ることが大切です。発達的目線でも保育士としてお伝えできるといいですね。

「お子さんの言葉が遅いことを心配されているんですね。確かに心配ですよね。でも最近は、ちょうちょを指さして「ちょ!ちょ!」と教えてくれたり、少しづつお話しようとしてくれるようになっていますよ。S君が発達障害かどうかは私たち保育士には判断できませんが、おうちでの困りごとや、園での関わり方など、一緒に共有していけたらと思います」
こんな風に、おうちの方の気持も受け止めつつ、一緒に進んで行きましょうという声をかけてみるのはいかがでしょうか?
NGな返答例

ここでNG返答例も紹介します。もし心当たりがあるようでしたら、今後は気を付けていきましょう。
「そうですね、○○くんは集中力がないですね。」
→ 否定的な表現になり、保護者の不安を強めてしまう。
「お友達とうまく遊べないのは、その子の性格かもしれませんね。」
→ 個性と決めつけてしまうと、保護者が適切な支援を受ける機会を逃してしまう可能性がある。
「こだわりが強い子は、なかなか直らないことも多いですよね。」
→ 「変わらない」と言われると、保護者が希望を失ってしまう。
「年齢が上がれば自然に落ち着くと思いますよ。」
→ 「様子を見ましょう」と言われるだけでは、保護者の不安が解消されない。
「園ではみんなそんなものですよ。」
→ 個別の困りごとを軽く扱うと、保護者が「ちゃんと聞いてもらえなかった」と感じる。
「一人っ子だからかもしれませんね。」
→ 環境や家庭背景のせいにされると、保護者が「どうすればいいの?」と悩みが深まることも。
「〇〇が原因かもしれませんね。」(理由を決めつける)
→ 「もしかしたら…」という軽い気持ちでも、保護者にとっては重大な指摘に聞こえてしまうことがある。
「確かに園でもこだわりが強いですね。」
→ 事実を伝えているつもりでも、「やっぱりうちの子は問題があるんだ…」と保護者が不安を強めてしまう可能性がある。
シーン3:専門機関への相談を勧めるとき
最初からいきなり「専門機関に相談しましょう」と言うのは避けたほうが良いですが、保護者が強い不安を感じている場合、そっと提案することも大切です。
決めつけず、選択肢として伝える
→「一度相談してみるのもいいかもしれませんね。」
不安をあおらず、前向きな視点を持たせる
→「専門家に話を聞くことで、お子さんに合った関わり方が見つかることもありますよ。」
相談することを特別視しない
→「発達のことに詳しい方に話してみると、新しい気づきがあるかもしれませんね。」
保護者の判断を尊重する
→「気になるようなら、一度相談してみるのも一つの方法ですね。どうされるかは、おうちの方の考えを大切にしていいと思います。」
ポジティブな雰囲気を大切に
→「お子さんの良いところをもっと伸ばすヒントが得られることもありますよ。」
専門機関に行くこと=特別なこと、ではなく「お子さんに合った関わり方を知るための手段のひとつ」として伝えられると、保護者も前向きに受け止めやすくなります。

もし興味があれば、専門家に相談すると、お子さんの素敵な部分をもっと引き出す方法が見つかるかもしれませんよ。
専門機関を進めたほうがいいかなと感じているお子さんだった場合、このような言い回しで、お伝えできるといいですね。
最終的な返答例(保護者への対応)

では最後にもう一度、「うちの子って発達障害なのでしょうか?」という類の悩み相談に対する返答方法を振り返っていきましょう。
① 保護者の気持ちに寄り添う
「お子さんのことをよく見て、心配されているんですね。」
→ まずは保護者の気持ちを受け止め、安心感を与える。
② 園での様子を客観的に伝える
「園では、○○のときに集中が続かないこともありますが、△△の場面では楽しそうに取り組んでいますよ。」
→ 良い面と気になる面をバランスよく伝える。
③ 家庭での様子を確認する
「ご家庭ではどのようなときに気になりますか?」
→ 保護者の話をしっかり聞くことで、必要以上に不安になっていないかを見極める。
④ 発達には個人差があることを伝える
「子どもによって成長のペースは違いますし、その子の個性として表れることもありますよ。」
→ すぐに「発達障害かもしれない」と結びつけないよう配慮する。
⑤ 必要に応じて専門機関を案内する
「もし心配が続くようでしたら、専門の先生に相談してみるのもひとつの方法ですね。」
→ 保護者が納得しやすいよう、選択肢を提案する。
まとめ
「うちの子、発達障害でしょうか?」と相談されたとき、保育士として大切なのは 保護者の気持ちに寄り添いながら、お子さんの成長を一緒に見守る姿勢を伝えること です。
- まずは じっくり話を聞く
- お子さんの 良いところも伝える
- 発達の個人差について 安心できる言葉をかける
- 専門機関の相談は あくまで選択肢として提案
「発達障害かどうか」は保育士が判断することではありませんが、 保護者の不安を受け止め、前向きな関わり方を一緒に考えることはできます。
ぜひこれをきっかけに、保護者対応についての理解を深め子どもにとっても、保護者にとっても信頼できる保育士さんになっていって欲しいと思います。
発達支援について理解を深めたい先生へ
お子さんの特性を理解し、適切な支援をするための知識を深めたい方には、発達支援に関する資格 を学ぶのもおすすめです。
民間資格ではありますが、私自身も発達支援の学びを深めるために資格の取得をしています。
発達支援に関する知識がまだあまりない先生へのおすすめは
→【ユーキャンの「子ども発達障がい支援アドバイザー」】
少し知識があり、更に対応力を高めていきたい先生は
→【ユーキャンの「子ども発達障がい支援実務士」】がおすすめです。
何その資格?と思った時は一度公式サイトで詳細をチェックしてみましょう。知らなかった世界を見ることができ、知識の幅がグンと広がります。
気になると思った今がチャンス!

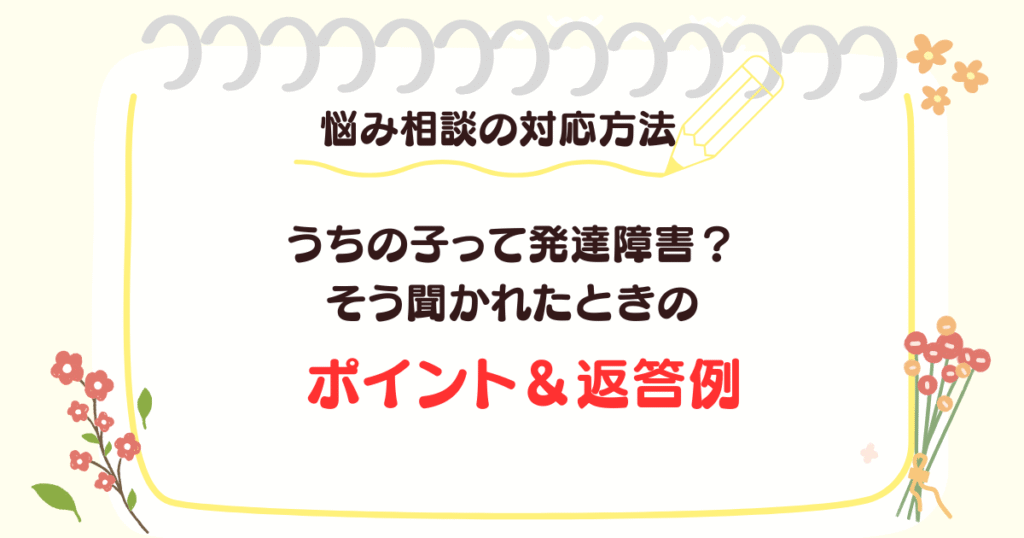

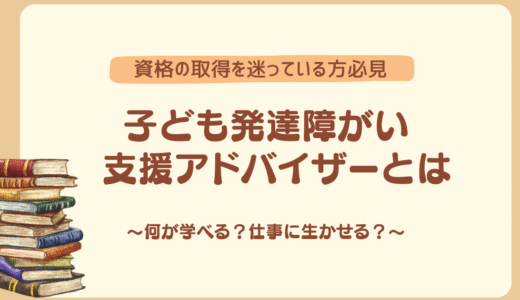
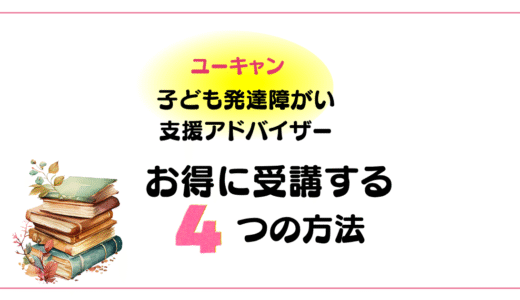
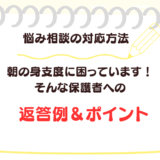
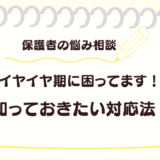
This web site is really a walk-through for all of the info you wanted about this and didn’t know who to ask. Glimpse here, and you’ll definitely discover it.
obviously like your web-site but you need to test the spelling on several of your posts. A number of them are rife with spelling problems and I in finding it very troublesome to inform the reality nevertheless I?¦ll surely come again again.