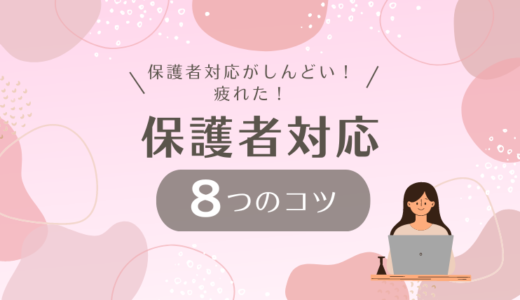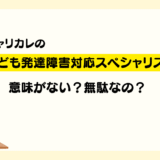※本記事にはプロモーションが含まれています
目次
はじめに
新年度が始まるこの時期、子どもたちだけでなく、保護者も不安や期待でいっぱいです。
不安を抱えている保護者との関係がスムーズに築くことができれば、子どもも安心して園生活を楽しめますよね。
特に、最初の関わり方がその後の信頼関係を大きく左右するため、新年度の保護者対応はとても重要なんです!
この記事では、発達心理学や教育社会学の視点を取り入れながら、保護者と良好な関係を築くための具体的なコツを、実際の保育現場のエピソードとともにご紹介します!

保護者対応のコツをつかみ、良い人間関係を築いていきましょう!
新年度の保護者対応のポイント
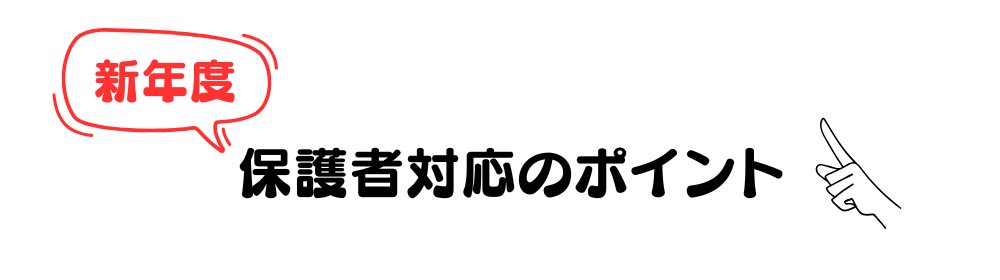
① 初対面での対応方法
「この先生はどんな先生かな?」
保護者は最初のやり取りから、「どんな先生なのか?」を感じ取ります。
心理学では「初頭効果」と言い、最初の印象が後の関係性構築に大きく影響すると言われています。
そこで、良い印象を与えるために、以下のポイントを意識しましょう。
- 笑顔で挨拶をする
無表情や機械的な挨拶ではなく、明るい表情で迎えます。これにより、ミラーニューロンという模倣に特化した神経細胞が活性化し、保護者側も笑顔になりやすくなります。
目の前に笑顔の先生がいたら、保護者もなんだか笑顔になるということを覚えておきましょう。
- 名前を覚えて呼ぶ
子どもだけでなく、保護者の名前もできるだけ覚えて呼ぶようにすると親しみやすくなります。「人の名前を覚えることが最も効果的な人間関係構築法」と言われています。
保護者の場合は、「田中さん」などの苗字呼びでも、「サクちゃんのママ」などと子どものママという呼び方でもどちらでもいいと思います!
- 名前を覚えて呼ぶ
子どもだけでなく、保護者の名前もできるだけ覚えて呼ぶようにすると親しみやすくなります。「人の名前を覚えることが最も効果的な人間関係構築法」と言われています。
保護者の場合は、「田中さん」などの苗字呼びでも、「サクちゃんのママ」などと子どものママという呼び方でもどちらでもい いと思います!
- 第一声をポジティブにする
「おはようございます!」と明るく声をかけるだけでも印象が違います。声のトーンは非言語コミュニケーションの4割近くを占めるとされています。
コミュニケーションの4割が声のトーンってすごくないですか?いつもの言葉でも声のトーンを変えるだけで効果が出るのであれば実践あるのみだと思います!
② 初回面談や懇談での一場面
新年度の面談では、保護者が抱える不安を少しでも解消できるよう意識しましょう。
- まずは保護者の話をしっかり聞く
「おうちでの様子はいかがですか?」と質問し、話しやすい雰囲気を作ります。話を聞いているときは、相槌や共感の言葉を適宜挟むことで、保護者は「話を聞いてもらえている」と感じてくれますよ。
- 肯定的な言葉を使う
「○○ちゃんは活発で話していると私まで元気になります!」など、前向きな表現を心がけましょう。
ポジティブ心理学の研究によると、肯定的なフィードバックは否定的なものより5倍以上の効果があるとされています。
- 園のルールは「なぜ」から説明する
もしまだ園の決まりなどを理解していないようであれば、最初に伝えておく必要も出てきますよね。そういう時は「こういう理由でこのルールがあります」と伝えることで、納得してもらいやすくなります。
「なぜ」から始めることで相手の共感を得やすくなると言われています。
③ 毎日の送迎時のコミュニケーション
送迎時に保護者とお話する時間はあまり取れないかもしれませんが、日々の積み重ねが信頼関係につながります。
- 子どもの様子を具体的に伝える
「今日は○○で楽しそうに遊んでいましたよ」など、小さなエピソードを伝えます。具体的なエピソードをお伝えすることで、保護者も「我が子を見てくれていたんだな」と安心感を抱いてくれるようになります。
- 話しかける時の非言語コミュニケーションを意識する
保護者の方へしっかりと姿勢を向け、落ち着いた優しい声で話すと、保護者も安心しやすくなります。
- ネガティブな報告はサンドイッチ法を活用する
もしネガティブなことをお伝えしなくてはいけないときがあれば、「○○ちゃんは今日もとても元気でしたよ。実は少しトラブルがあったのですが、その後は自分から謝ることができました」と肯定→課題→肯定の順で伝えると、保護者の方にも受け入れてもらいやすくなります。
④連絡帳でのやりとり
日頃面と向かってやり取りができていない保護者にとっては、連絡帳は貴重なコミュニケーションのツールです。以下のようなコツを取り入れながら、連絡帳でのやり取りも心掛けていきましょう。
- 子どもの様子を具体的に伝える
「今日は○○で楽しそうに遊んでいましたよ」など、小さなエピソードを伝えます。具体的なエピソードをお伝えすることで、保護者も「我が子を見てくれていたんだな」と安心感を抱いてくれるようになります。
- ポジティブな視点を取り入れる
「よかったこと → 具体的なエピソード → よかったこと」の順番で書くと、保護者も前向きな気持ちになれます。例: 「今日は○○をして、とても楽しそうでした!特に△△の場面では、◇◇のように成長を感じました。これからも一緒に見守っていきますね!
- 気になることがある場合も伝え方に工夫を
課題がある場合は、否定的な表現を避け、「こんなふうに頑張っています」と前向きに伝えるようにしましょう。
ちょっとした工夫で、保護者に「先生はうちの子をよく見てくれているな」と感じてもらえますよ。最初は時間がかかってしまうかもしれませんが、連絡帳を書くコツも身に付けていけるようにしていってくださいね。
保護者対応が苦手でも大丈夫!
保護者を目の前にすると咄嗟に話すことが分からなくなってしまう!ということもありますよね。苦手な先生もいて当然です。
そんなときは、一度落ち着いて振り返ることが大事。
「次はこう話してみよう」「こう言えば伝わりやすかったかな?」と振り返るだけで、次の対応がぐっとスムーズになります。
うまく話せなかったときも、経験を重ねればどんどん慣れていくので大丈夫です!
たったこれだけ「8つのコツ」
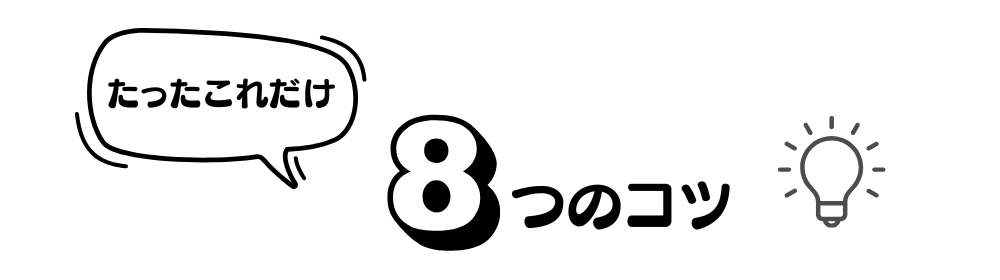
最後に保護者との関係づくりのコツを、覚えやすくまとめました。
- にっこり笑顔で
- 目を見て話す
- 名前を呼ぶ
- しっかり話を聞く
- いいところを伝える
- その日の出来事を伝える
- うまくいかなかったら振り返る
- 保護者の気持ちに寄り添う
ズラっと一覧にすると、わ・・やることがいっぱい・・・と感じるかもしれませんが、どれもすぐにできることばかりです!
「ちょっと苦手かも…」と思うことがあっても、一つずつ取り入れていけばOK。
大切なのは、「保護者も同じように子どもを想っているんだな」と意識すること。 お互いの気持ちを大事にしながら、少しずつ関係を築いていきましょう!
保護者対応の事例から学ぶ
事例1:転園してきた保護者への対応
新しい環境に不安を抱える保護者に対して、「前の園では〇〇だったけど、ここでは違うんですね」と比較される場合があります。
対応のポイント
- 前の園の方針を否定せず、「それぞれの園には特色がある」と肯定的に受け止める
- 自園の方針の理由を明確に説明する(「私たちは〇〇という理由で△△を大切にしています」)
- 子どもの様子を具体的に伝え、安心感を与える(「お子さんは新しい環境にもすぐに慣れていますよ」)
- 保護者の意見や家庭での様子を聞き、連携を深める
具体的な声かけ例
「そうですね、園によって方針が異なるので戸惑ってしまいますよね。この園では〇〇という理由でこのようにしています。T君は徐々に新しい環境に慣れてきているようで、今日はS君と楽しそうに遊んでいましたよ。お家での様子もぜひ教えていただけると、より良いサポートができますので、気になることがあればいつでもお話しください。お子さんが安心して過ごせるよう一緒に考えていきましょう」

このように保護者の意見をまずは受け入れ、理解を示すことから心掛けていきましょう。そのうえで、少しずつ距離を縮めていけるといいですね。
お話する際は、子どもが新しい園生活にも慣れてきていることなど、安心していただけるエピソードも加えてあげるといいですよ。
事例2:過度に心配する保護者への対応
「うちの子、みんなと仲良くできてますか?」「お友達とケンカしませんか?」と毎日のように心配する保護者には、具体的なエピソードと成長の様子を伝えることで安心感を与えられます。
対応のポイント
- 具体的な遊びの様子や友達との関わりを時系列で伝える
- 子どもの社会性の発達段階を専門的に説明する
- 小さな成長を見逃さず伝える(「今日は自分から「かして」と言えましたよ」)
- 写真や動画で園での様子を共有する工夫をする
具体的な声かけ例
「今日はAちゃんと一緒に砂場で遊んでいましたよ。最初は隣で遊ぶだけという並行遊びでしたが、途中から「バケツ貸して」と自分の気持ちを言葉で伝えようとする姿が見られました。3歳児の発達段階では、並行遊びから少しずつ協同遊びへと移行していくのが自然な流れなので、ゆっくりと見守っていきたいと思っています。
週に1回のクラス便りでお子さんの園での様子をお伝えしていますが、連絡帳アプリを通じて日々の様子も写真付きでお知らせしていきますのでまた気になることがありましたら、お声掛けくださね」

保護者にとっては「友達と仲良く遊ぶ」ということをどの年齢にも求めていらっしゃる方がみえます。そこで3歳児さんだとしたら、まだ友達と仲良く遊ぶという発達段階にはないことも伝えてあげることも必要です。
「そうなんですね~安心しました」と発達段階を聞いて納得される保護者の方もいらっしゃるので、そういった専門的な視点からの声かけもしていきたいですね。
事例3:多忙な保護者への対応
仕事で忙しく、コミュニケーションが取りにくい保護者にはどのようにアプローチすべきでしょうか。
対応のポイント
- 短時間でも効果的に情報交換できる方法を提案する
- デジタルツールを活用した情報共有を行う
- 保護者の状況に合わせた連絡方法を選択する
- 何かあったときだけでなく、良い出来事も共有する
具体的な声かけ例
「お忙しいところ恐縮ですが、お子さんの今日の素敵な出来事をお伝えしたくて。今日は初めて自分から片付けを手伝ってくれました。連絡帳アプリにその時の写真をアップしましたので、お時間あるときにご覧いただければ幸いです。何かご質問やご要望があれば、アプリのメッセージ機能やお電話など、ご都合の良い方法でお知らせくださいね」

保育園に来ている子の大半が、忙しく働いているご家庭なので、時間がない中でも見ていただけるツールを検討していくのも一つの手ですね。まずはプラスの出来事から伝え、信頼関係を築いていくことに重きを置いて下さい。
まとめ:保護者対応は日々の積み重ね
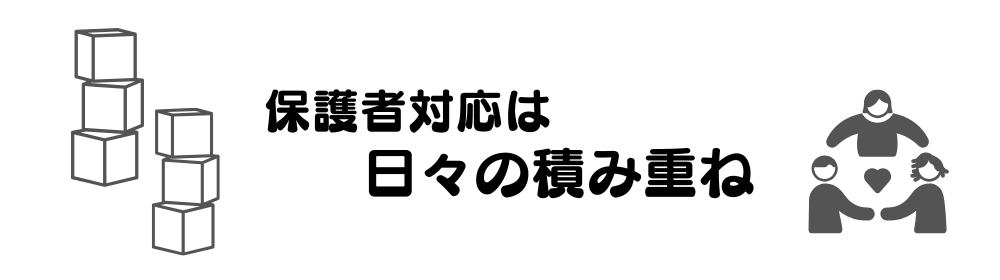
新年度の保護者対応は、最初の印象がその後の関係に大きく影響するということを念頭におき十分な理解のもと行っていきたいですね。
心理学的知見に基づいた丁寧なコミュニケーションを心がけることで、保護者との信頼関係を築き、子どもにとっても安心できる環境を作ることができます。
日々の積み重ねが信頼につながるので、7つのポイントを意識しながら、少しずつ実践していきましょう。
保護者との良好な関係は、子どもの発達と成長を支える重要な基盤となります。もし困ったことがあればコメントはSNSでいつでも相談を受け付けていますのでお気軽に♡
保護者対応のおすすめ本
ちょっと相談するのはハードルが高い・・・と感じる先生に、おすすめの本を紹介しますね。
「思いが伝わる&気持ちがわかる!保護者対応のコツ」
現場でよくある困ったケースを厳選して55本掲載。読みやすいまんが形式なので、具体的なシーンをイメージしながら考えることができます!
その対応がなぜOKなのか・なぜNGなのかを丁寧に解説しているので、対応のポイントがわかりやすいところも高ポイント。「保護者との接し方の基本」などの各種コラム・コーナーも充実しており、保護者対応のお悩みを解決するノウハウが満載です。
今こうしてこの記事を読んでくださっているということは、「悩んでいる、困ってる!」ということに気づいた証です。
ちょっとした心がけ一つで、保護者対応のスキルはどんどんアップしていくので、今日からの保育にぜひ活かしていってくださいね。