※本記事にはプロモーションが含まれています
「この子なんだか落ち着きがない・・・」
「ほかの子より活発すぎるかも・・・」
「じっと座っていられないのはなんで?」
そんな不安や悩みを抱えていませんか?
2歳頃のお子さんは活発に動き回るのが自然な姿ですが、時々「これは普通の活発さなのかな?」と心配になることもありますよね。
今日はそんな悩みを抱える保護者の方や保育者の方に向けて、2歳児の多動について、気になる行動のチェックリストや家庭でできる対応方法をお伝えします。

一人で悩まずに、まずは知識を得ることから始めましょう。
目次
2歳児の発達の特徴は?

2歳児は”探索期”の真っ最中
2歳児は歩く・走るといった運動能力が急速に発達し、「自分でやりたい!」という自我も芽生え始める時期です。
何にでも興味を示し、手当たり次第に触れたり動かしたりしながら世界を理解しようとしています。これは脳の発達にとても重要な活動なんです。
「普通の活発さ」と「気になる多動性」の違い
2歳児が元気いっぱいに動き回るのは、まったく自然なこと。
では、「普通の活発さ」と「気になる多動性」はどう違うのでしょうか?
普通の活発さの場合は、声をかければ一時的に動きを止められたり、興味のあるおもちゃで10分程度は遊べたりします。
一方、気になる多動性がある場合は、常に動き続けていて、危険な場面でも止まれなかったり、何をするにも集中が続かなかったりする傾向があります。

ただ、どちらにしても個人差が大きい時期なので、一つの行動だけで判断するのではなく、総合的に見ていくことが大切です。
多動の可能性がある具体的な行動チェックリスト
では具体的にどのような行動が気になるのかチェック項目を参考に子どもの姿を振り返ってみましょう。
- 食事中に座っていられず、すぐに立ち歩いてしまう
- おもちゃや遊びを3分以上続けることが難しい
- 注意されても繰り返し高いところや危険な場所に登る
- 「待ってね」と伝えてもすぐに動き出してしまう
- 話しかけても目が合わず、すぐに他のものに気を取られる
- 友達との遊びで順番を待つのが苦手で、割り込んでしまうことが多い
- 他の子と比べて明らかに走る・飛ぶ・動き回ることが多い
- 思い通りにならないと大声で泣いたり怒ったりし、気持ちを切り替えにくい
このチェックリストはあくまで参考ですが、いかがだったでしょうか?
いくつかチェックがついたからといって、必ずしも発達に課題があるというわけではありません。
しかし、多くの項目に当てはまる場合や、家庭生活に支障が出るほど激しい場合は、専門家に相談してみる目安になります。
多動と発達障害の関係性
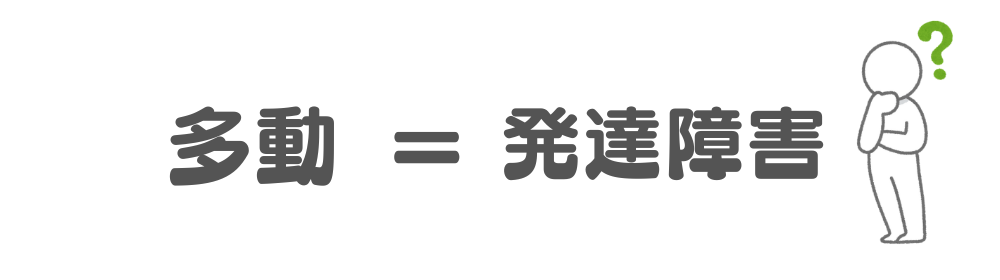
多動性(多動)は発達障害そのものではなく、あくまで一つの特徴や症状として現れるものです。発達障害の診断基準の中に「多動」が含まれることはありますが、多動=発達障害とは限りません。
必ずしもイコールではない
例えば、多動の傾向は環境的な要因によっても現れることがあります。
睡眠不足やストレスなどが影響し、一時的に落ち着きがなくなることもあります。また、年齢によっては発達の過程として自然に見られる行動の一つであることも少なくありません。
一方で、多動が日常生活や対人関係に大きく影響している場合や、その他の特性(不注意、衝動性、こだわりの強さなど)とあわせて見られる場合には、発達特性の一つとして考えられることがあります。

多動の背景はさまざまであり、一人ひとりの特性や状況に応じた理解と関わりが大切ということです。
以下に、多動性が見られる主な要因とその特徴を整理したので参考にしてください。
多動が見られる主な要因とその特徴
| 要因 | 特徴 | 多動との関係性 |
|---|---|---|
| ADHD (注意欠如・多動症) | じっとしていられない、話し続ける、衝動的に動く | 生活の中で目立つことがある |
| ASD (自閉スペクトラム症) | 感覚過敏やこだわりの強さにより動き回ることがある | 状況に応じて現れることがある |
| 知的発達症 (知的障がい) | 自己制御が難しく、落ち着いて行動することが苦手 自己制御が難しく、落ち着いて行動することが苦手 | 周囲のサポートが必要な場合がある |
| 年齢による発達の特徴 | 幼児期はもともと活動量が多く、落ち着きがないことが普通 | 成長とともに変化することが多い |
| 環境要因 | ストレス・睡眠不足・興奮状態などで一時的に多動が見られることがある | 環境が整うと落ち着くことが多い |
| 個人の気質(性格) | 活発でエネルギッシュなタイプの子どもは動きが多い | 遊び方や環境を工夫するとよい |
このように多動が見られる子どもには様々な背景や要因が考えられます。
多動性が見られるからといって、すぐに発達障害と結びつけるのではなく、「いつから」「どの場面で」「どのくらい」多動が見られるのかを丁寧に観察することが大切です。また、本人が困っているかどうか、周囲との関わりにどのような影響があるのかを見極めながら、適切なサポートを考えていけるといいです。
早期発見と支援の重要性
「みんなとは少し違うかも・・」と考えこんでしまうママ、クラスに気になる子がいて悩んでいる保育士さん。
考えすぎて気を落としてしまうこともあるかもしれません。
でも、もし発達に特性があるとしたら、早く気づいて適切な支援をすることで、お子さんの将来の可能性は大きく広がります。
重要なのは「障害かどうか」ではなく、「この子にとってどんな環境や関わり方が合っているか」を見つけることです。そのためにも、気になることがあれば、まずは小児科医や専門機関に相談してみるといいでしょう。
現役保育士としてのアドバイス
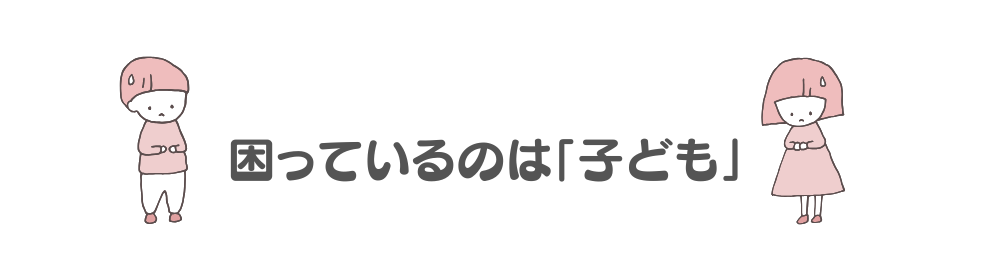
保育現場で10年以上勤務している現役保育士として一つだけ言わせえてください。
ママや先生も困っていると思いますが、実は一番困っているのは「子ども」なんです。きっと彼らは好きで動き回っているわけではありません。
発達上、そうせざるを得なくなってしまっている可能性が高いんです。
その原因や背景に気づいてあげられるのは、今この記事を読んでっくださっているあなた自身です!
私が日頃参考にしている書籍を2冊紹介しておきます。きっと何かの役に立つと思うので、是非手に取ってみて欲しいと思います。
赤ちゃんの発達障害に気づいて・育てる完全ガイド
発達が気になる赤ちゃんにやってあげたいこと
発達障害は3~4歳以上にならないと診断をしてもらえない、と言われていますが、個人的な意見としては気になる姿があるのであれば、できるだけ早くその子にとって最適な関わり方や環境を整えてあげることが大切だと思っています。
よくある質問(FAQ)
Q: 多動と診断されたら、その後どうなりますか?
A: 診断は「レッテル貼り」ではなく、お子さんに合った支援を受けるためのスタートです。必要に応じて児童発達支援サービスを利用したり、適切な関わり方のアドバイスを受けたりできます。早期からの適切な支援で、多くのお子さんが自分の特性に合った対処法を身につけ、持ち前の長所を生かして成長していきます。
Q: 兄姉と比べて活発ですが、心配する必要はありますか?
A: きょうだい間での比較は難しいところです。それぞれに個性があり、発達のペースも異なります。日常生活に大きな支障がなく、危険な行動もないようであれば、経過観察でよいでしょう。ただ、心配が続くようでしたら、健診などで相談してみることをおすすめします。
Q: 保育園の先生に相談するときのポイントは?
A: 具体的な場面や行動について伝え、家庭での様子も共有しましょう。「困っている」と素直に伝えることが大切です。また、園での様子や対応法について聞いてみると、家庭でも取り入れられるヒントが得られるかもしれません。
Q: 多動の特徴がある子の長所は?
A: エネルギッシュで行動力があり、好奇心旺盛なことが多いです。創造性や発想力が豊かで、直感的な理解力に優れていることもあります。こうした長所を伸ばすことで、将来さまざまな分野で活躍できる可能性を秘めています。
背景を見極めてよく観察&早めの対応が大切
最後にもう一度、2歳児の多動について、以下のポイントを覚えておきましょう
- 2歳児が活発に動き回るのは自然な発達の姿
- 常に動き続け、危険でも止まれない、集中が極端に短いなどの場合は注意が必要
- 環境調整や関わり方の工夫で落ち着いて過ごせるようになることも多い
- 気になる場合は早めに専門家に相談を
何より大切なのは、お子さんの個性を尊重し、「困った子」ではなく「困っている子」として理解することです。多動傾向のあるお子さんは、好奇心旺盛でエネルギッシュ、創造性豊かという素晴らしい特性を持っていることが多いです。

子どもが成長していく過程は、とても長い道のりです。一人で抱え込まず、周りの力も借りながら、お子さんの成長を温かく見守っていきましょう。
どんな関わり方が良いのかな?改善する方法はあるのかな?と悩んでいる方は現役保育士mozせんせいが関わり方のちょっとしたアドバイスをお伝えすることもできますよ。
当ブログのコメント欄や問合せ、SNSへのメッセージなどでもお返事させていただいておりますのでお気軽に♪
さらに詳しく発達支援について学びたい方へ
最近よく耳にするようになった発達障害とはそもそも何なのか・・?
気になる行動は発達障害が原因なのか・・
適切な関わり方はどんな方法があるのか・・・
そんな疑問や悩みがある方のためにおすすめの資格があります。それは資格大手サイトユーキャンの「子ども発達障がい支援アドバイザー」。

「子ども発達障がい支援アドバイザー」という資格では、発達に課題のある子どもへの適切な関わり方を学ぶことができるので、保育士さんはもちろん、子育て中にパパママにもピッタリ!
このような資格取得を通じて専門的な知識を学ぶことで、より自信を持って目の前の子どもと関わることができるようになるため、近年とても人気を集めている資格です。
「発達支援について理解を深めたい!我が子の気になる行動を少しでも落ち着きのある状態にしてあげたい」
そう感じていらっしゃる保護者の方にもピッタリの資格になっているので、ユーキャンで専門的な知識を得て、子どもとのより良い関わり方、向き合い方を学んでいきましょう。無料資料請求もおススメです!!
詳しくはこちら 子ども発達障がい支援アドバイザーの詳細をチェック



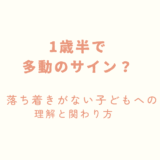
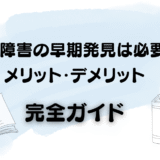
You need to take part in a contest for among the best blogs on the web. I’ll recommend this site!
Visit Back – I didn’t expect to find such helpful content. Thanks a lot!
This post shows why your blog stands out from the rest.
create an experience that feels both educational and inspiring. Every
how effectively you communicate your ideas, and this piece genuinely
Comment 36: This blog post is truly outstanding and provides such a
Absolutely stellar writing — I’m blown away!
You continually raise the standard for great content.
You write with so much intention and clarity.