※本記事にはプロモーションが含まれています
「1歳なのに落ち着きがない」「いつも動き回っている」
——そんなお子さんを見て「もしかして多動?」と不安になる方が増えています。
実はこの時期の多動傾向には、成長の一部として自然な場合と、発達特性が関係する場合があります。このページでは、保育士の視点で多動の特徴とチェックリストを解説します。
目次
「うちの子、もしかして…?」その気持ち、よく分かります
「うちの子、落ち着きがないけど、もしかして多動?ADHD?」

保育士として働いていると、このような不安の声をよく耳にします。特に一歳前後のお子様を持つ保護者の方から、こういったご相談をいただくことが多いんです。
しかし、まずは深呼吸をしましょう。
一歳児の発達には大きな個人差があり、「落ち着きのなさ」は必ずしも問題ではなく、むしろ健やかな発達の証であることが多いのです。
本記事では、一歳児の発達の特徴とADHDの違いを分かりやすく解説し、気になる行動があった場合の対応方法について紹介します。
※本記事は、1歳のお子さんを持つ保護者の方や、1歳児と関わる機会の多い保育士さん向けの内容になっています。
多動や落ち着きのなさの背景とADHDの特徴

ADHD(注意欠如・多動性障害)は、不注意・多動・衝動性の3つの特徴を持つ発達特性です。
ADHDの主な特徴
- 不注意:集中力が続かない、気が散りやすい
- 多動:じっとしているのが苦手、常に動き回る
- 衝動性:順番を待つのが苦手、思ったことをすぐに行動に移す
しかし、一歳児はそもそも「じっとしていられない」「興味のあるものに飛びつく」といった行動が普通です。そのため、この時期に見られる行動がADHDによるものなのか、それとも年齢相応の発達の特徴なのかを区別することは非常に難しいのです。
一歳児の発達の特徴と「多動」との違い

一般的な一歳児の発達の特徴
まずは一般的な一歳児の発達の特徴についてお話します。
以下のような行動は一歳児の発達段階として日常的に見られる行動です。
✅ いろいろなことに興味を持ち、短時間で次々と遊びを変える
✅ 大人の話しかけに反応するが、すぐに他のものに注意が移る
✅ 気になるものに向かって一直線に進む
✅ 自己主張が強く、思い通りにならないとぐずる
✅ まだ感情のコントロールが苦手で、切り替えが難しい
例えばこんな行動
- おもちゃで遊んでいたかと思うと、すぐに違うものに手を伸ばす。
- 気になるものを見つけると、迷わず一直線に向かっていく。
これは一歳児に限らず小さいお子さんにはよくある話です。この時期は、まだ集中力が長くは続きません。そのため一つのおもちゃでじっくりと遊ぶというよりは、少し遊んでは次のおもちゃ・・・と遊びがどんどん変わっていくもの。
また、目の前にあるおもちゃ以上に素敵なものが視野に入ってい来たら、そちらが欲しくなってしまいます。お友達のおもちゃは特に魅力的で、勝手に取ってしまうという行動も自然な行動だと言えます。

これらは一歳児の成長過程として、ごく自然なことです。
ADHD・多動の可能性がある場合(年齢が進んでから)
✅ 2歳以降になっても、極端に落ち着きがない
✅ 名前を呼ばれてもほとんど反応しない
✅ 物を投げたり、たたいたりする行動が頻繁で、収まる気配がない
✅ 同じ行動を繰り返し、切り替えが難しい
✅ 5分以上、何かに集中することがほぼない
このような特徴が成長とともに強くなり、日常生活に影響が出てくる場合、ADHDの可能性を考慮し始めることもあります。

ただ、一つの気になる行動が見られるだけで、「この子はADHDだ」と決めつけてしまうことはやめてくださいね。
1歳児の多動チェックリストと気をつけたい行動
今現在、ADHDの兆候なのかも?と気になっている行動はどんな行動ですか?
考えられる姿や行動は以下の通りです。あてはなる項目がいくつあるかチェックしてみてください。
じっとしていられない・落ち着きがない
- ベビーカーやチャイルドシートに座るのを極端に嫌がる
- 「読んであげるね」と言っても、絵本を最後まで見ない
- おもちゃを次々に出すが、興味が移りやすく長続きしない
- 食事中に席を立ちたがる、食べ物で遊んでしまうことが多い
- 常に落ち着きがなく動き回っている
目が合いにくい、呼びかけに反応しにくい
- 名前を呼んでも、こちらを見ないことが多い・視線が合わない
- 「わんわんはどこ?」と聞いても指差ししない
何度も同じ行動を繰り返す
- 手をひらひらさせる、くるくる回るなどの気になる行動がある
- 特定のおもちゃや動作(ドアの開け閉め、物を並べるなど)に強いこだわりがある
- 遊びの幅が狭く、特定のことばかり繰り返す
- 何度止めても、同じ行動を繰り返す(机に登る、物を投げるなど)
衝動的な行動が目立つ
- 興味のあるものを見つけると、親が止める前に突進する
- 友達や兄弟を押したり、たたいたりすることが頻繁にある
感情のコントロールが難しそうに見える
- 片付けの時間等、気持ちの切り替えが苦手で、嫌なことがあると長時間泣き続ける
- 予想外の出来事に強く反応し、パニックになりやすい
- 欲しいものが手に入らないと、大きな声で泣き叫ぶことが多い
チェックリストの見方
いかがでしたでしょうか?
チェックのついた項目の数によって判断の目安としてください。
- 1〜2個当てはまる → 年齢相応の行動かも?(一歳児はもともと注意が散漫になりがち)
- 3〜5個当てはまる → 気になる行動が増えてきたら、様子を見守るのが大切
- 6個以上当てはまる → 成長の様子を記録し、気になる場合は専門家に相談も
いくつも当てはまるからと言って、多動やADHD確定というわけではありませんが、もし気になるようであれば市の保健センターやかかりつけ医などのに相談してみるのも一つの方法だと思います。
こんな視点で発達を見守ろう
いくつもチェック項目が当てはまっている・・・と落ち込んでしまう方もいたかもしれませんね。
保育士として働いていると、気になる行動をしている子が園内にチラホラいると感じるのが現状です。しかし私たちは保育士なので、決定的な判断をできるわけではありません。
そこで、そのような子たちと関わるうえで大切にしていることをお伝えしていきますね。
子どもの「好き」を大切に
気になる行動もあるかもしれませんが、まずは楽しそうにしていること、興味を持っているものに注目してみましょう。それが発達を促す大切な要素になります。
「好き」なことに夢中になる時間が増えると、集中力や自己表現の幅も広がります。
安心できる環境づくり
子どもが落ち着いて過ごせる環境を整えることで、不安を減らし、成長をサポートできます。
・集中できる環境を作る
例えば、食事中やおもちゃで遊んでいるときに落ち着きがないという場合は、周りの環境を整えます。注意が散漫になりやすい子の場合、食事中にテレビが付いていたり、風でひらひらと動く壁面があったりすると途中で意識がそちらに向き、集中が切れてしまいます。
おもちゃ遊びでも同様で、たくさんのおもちゃが床に落ちていたり、手に取りやすい環境だったりすると気が散りやすくなってしまいます。
そのため、視野に入る物をできる限り少なくしてあげるよう環境を整えてあげましょう。気が散ってしまう物を事前に取り除いておくことで、集中が続くようになりますよ。
・見通しが持てるように声をかける
片付けの時間になってもなかなか片付けられず、パニックになってしまう・癇癪を起してしまうという場合は、見通しが持てるような声掛けをしましょう。
「あと10分でお片付けにしようね」「お片付けをしたらお昼ご飯だよ」など見通しが持てるように声をかけることで、おしまいが分かるようになったり、次の活動への見通しが持てるようになります。
タイマー等を使って、これがなったらおしまいだよ。という方法もおすすめです。
・原因を取り除く
この時期の子どもにはよくあることですが、不快を感じる原因があることで機嫌が悪くなることも。
そのため、その原因となるものを見つけ取り除いてあげるようにしましょう。
原因となる物の一例として
- 疲れ
- 体調不良
- 睡眠不足
- 空腹
- 温度
- 他の子どもの声
- 光
どんな時に癇癪やパニックを起こしてしまうのかよく観察し、その原因となる環境を整えてあげることがとても大切です。
発達の記録をつける
もう一つおすすめなのが、日々の成長を記録すること。記録を通して、子どもの発達のペースを客観的に見守ることができるようになりますよ。
新しくできるようになったこと:言葉や動き、行動の変化を記録
興味を持ったもの:何に夢中になっているかを知ることで、こどもの個性を理解できます。
困っている様子:特定の場面での困りごとが繰り返される場合、環境の調整や専門家の意見が役立つこともあります。

子どもの日頃の姿を記録することは、私自身も保育の現場でとても大切にしています。
まとめ:一番大切なのは、ゆっくり見守ること
一歳児の発達は本当に個人差が大きく、みんな違って当たり前です。この記事のチェックリストは、あくまでも「発達を見守るためのヒント」として使ってくださいね。
「もしかして発達障害?ADHD?多動?」と不安に感じることがあれば、一人で抱え込まず、保健センターや小児科などの専門機関に相談してみることもおすすめします。

何より、子どもの「今」を温かく見守り、一緒に成長を楽しむことが大切です。
さらに理解を深めたい方へ
子どもの発達についてもっと学びたいという方にお勧めの資格があります。
それはユーキャンの「子ども発達障がい支援アドバイザー」という資格。

この「子ども発達障がい支援アドバイザー」という資格は、発達障がいの基本的な知識や具体的な支援方法を学ぶことができ、発達障がいについて初めて学ぶ人にはピッタリ!!
ADHDかどうかに関わらず、子ども成長をより深く理解し、適切な関わり方を知ることができるので、安心して子どもと向き合っていくことができますよ。
詳しくはこちらからご覧ください:ユーキャンの子ども発達障がい支援アドバイザー

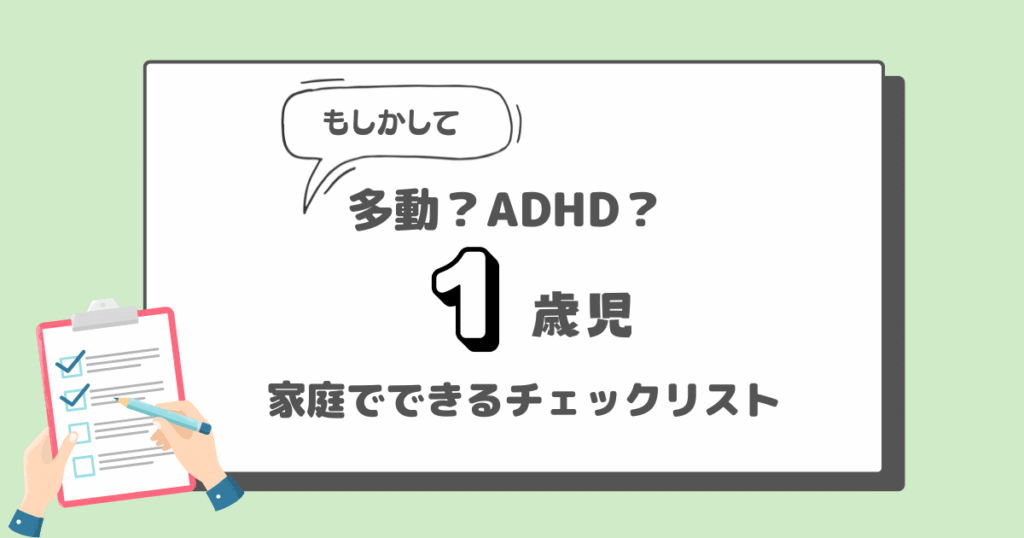

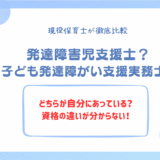
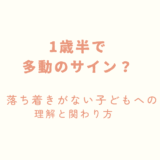
Thanks for sharing excellent informations. Your web-site is very cool. I’m impressed by the details that you¦ve on this web site. It reveals how nicely you perceive this subject. Bookmarked this website page, will come back for extra articles. You, my friend, ROCK! I found just the information I already searched everywhere and just couldn’t come across. What a great web-site.
Hey there would you mind letting me know which hosting company you’re working with? I’ve loaded your blog in 3 different web browsers and I must say this blog loads a lot quicker then most. Can you suggest a good hosting provider at a fair price? Thanks a lot, I appreciate it!
Do you have a spam problem on this website; I also am a blogger, and I was wanting to know your situation; we have created some nice practices and we are looking to trade strategies with others, please shoot me an e-mail if interested.
Usually I don’t read article on blogs, but I would like to say that this write-up very forced me to try and do so! Your writing style has been amazed me. Thanks, very nice article.