※本記事にはプロモーションが含まれています
「1歳半の子どもがじっとしていられなくて…」
「動き回ってばかりで、何か問題があるのかな?」
そんなお悩みを抱えている保護者の方も多いのではないでしょうか?
保育士として現場にいると、「この時期の子どは、みんな元気いっぱいで動き回るもの!」と発達段階に応じた捉え方をすることができますが、保護者の方にとっては「落ち着きがないのでは?」「多動のサイン?」と心配になることもあるかもしれません。
今回は、1歳半の発達の特徴を知りながら、「多動かな?」と感じる子どもへの適切な関わり方についてお話ししていきます。
※本記事は1歳半のお子様を持つ保護者の方、1歳半の子と関わる機会の多い保育士さん向けの内容になっています。
目次
一歳半の発達のポイント
まずは、一歳半の発達についての理解を深めていきましょう。
この時期は、心も体も大きく成長する時期。活発に動き回るのは、この成長の一環とも言えます。
身体的発達
- しっかり歩けるようになり、走る・登るなどの動きが活発になる
- 指先が器用になり、小さなものをつまんだり、積み木を重ねたりできる
この頃は特に、動くのが楽しくて仕方ない時期です。
多少落ち着きがなくても、「元気いっぱい!」とまずはポジティブに捉えてみましょう。
言葉の発達
- 10~20語程度の単語を話しはじめる(個人差が大きい)
- 指差しやジェスチャーで自分の意思を伝えようとする
- 周りの言葉を理解し、「ちょうだい」「ダメ」などの簡単な指示に反応できる
言葉がまだ少ない分、「動き」で表現することが多い時期です。
動き回ることで、気持ちを伝えようとしているのかもしれませんね。
心の発達(自己主張が増える)
- 「イヤ!」と自分の意思をはっきり示す(第一次反抗期の始まり)
- 好きなことに夢中になりやすいが、飽きるのも早い
- 友達と一緒に遊ぶより、一人遊びや大人との関わりを好む
「イヤ!」が増えるのは、自分の意思が出てきた証拠です。関わり方を工夫すると、少しずつやりとりがスムーズになります。

1歳半頃の子どもの成長発達についてザっと説明してきましたが、このように1歳半は「とにかく動きたい!」「なんでも試したい!」という気持ちが強くなる時期ということを理解しておいてください。
では、どんな行動が「多動かな?」と気になるポイントになるのか、具体的に見ていきましょう。
一歳半で見られる「多動のサイン」
「多動かも?」と思われる行動には、いくつかのタイプがあります。保育士目線で、気になる行動と言われる主な行動をピックアップしていきますね。
探索が止まらないタイプ
まずは探索が止まらないタイプについて。
- 部屋の中を常に歩き回り、一つの遊びに集中する時間が極端に短い
→例えば、おもちゃを手に取ってもすぐに放し、次々と別のものに興味を示す - どんなところでも登る・走る・触ろうとする
→ソファや棚によじ登ったり、机の上に乗ろうとしたりしてしまう - 危険な場所でも迷わず進んでしまう
→道路や階段などの危ない場所でも躊躇なく向かってしまうことがある
この時期の子どもは、新しいものに興味を持ちやすく、短時間でさまざまな遊びに手を出すことがよくあります。
しかし、一つの遊びに全く関心を持てなかったり、環境に関係なく常に動き回ってしまう場合は、多動の特徴が表れている可能性もあります。
興味の対象があまりにも次々と移り変わる場合や、注意を向けること自体が難しい場合は、注意深く様子を観察してみましょう。
もう一つ気になることは、危険な場所でも迷わず進んでしまうところ。
大人から見たら危ないだろう場所にもかかわらず迷わず突き進んでいったり、大きな犬に迷わず近づいて行ったり・・・
1歳半頃だと、段差などに気づかず進んで行ってしまうという姿もたまに見られますが、どんな行動においても危ないかもしれないという察知能力が低い場合も注意して観察するといいでしょう。

私の勤務する園にも、危険を察知する能力が極めて低く、何度言っても段差に気づかず走って転んでしまう子や、けがをしてもあまり痛がらない子がいます。プラスな言葉で言えば「怖いもの知らず」かもしれませんが、ただ単に「怖いもの知らず」で済ませてしまわないよう気を付けて見るようにしています。
衝動的な行動が多いタイプ
次は衝動的な行動が多いタイプについてです。
- すぐに手が出る(おもちゃを投げる・友達を叩く)
→遊びの中で興奮すると、思わず友達を押したり叩いたりしてしまうことが多い - 「ダメ」と言われてもやめられない
→何度注意しても同じ行動を繰り返し、危険なことも繰り返しやってしまう - 順番を待つのが苦手
→大人が介したやり取りの際でも、おもちゃの順番や滑り台の列を待てず、割り込んでしまうことがある
すぐに手が出てしまうことや、順番を待つ事なども一般的な発達段階としてよくある行動です。
しかし衝動的な行動が目立つ場合、単なる年齢相応の発達ではなく、注意の切り替えが極端に苦手な可能性があります。
例えば、言葉で言えず手が出てしまうということはよくあることですが、それが継続的に続いたり、そのやり取りがきっかけでひどく泣き続けてしまう場合などは少し気になる行動になってきます。
本人の中では、このおもちゃで遊ぶ予定だった!など「こうする!」と決めたことが途中で遮られてしまい、急な予定変更に対応しきれずパニックになってしまい手が出たり、癇癪を起している場合もあります。

こうした行動が日常生活に支障をきたしているかどうかを見極めることが重要です!
感覚刺激を求めるタイプ・刺激が苦手なタイプ
最後は感覚刺激を求めるタイプと、刺激が苦手なタイプについて。
- 何かをずっと触っていたい、口に入れる
→ぬいぐるみや布、服の裾などを常時握りしめ、手を動かしている
→爪を噛む、食べ物以外のものを口に入れようとする - 走る・回る・ジャンプを繰り返す
→じっと座っていることが難しく、止まることなく走り回ったり、くるくる回り続けたりする - 大きな声を出し続ける
→普通の遊びの中でも、特に理由がなく大声を出し続けることがある
→声の大小を求めても大きな声を出す
感覚刺激を求める行動が極端に強い場合、それが単なる遊びではなく、自分を落ち着かせるための手段になっている場合があります。
例えば、特定の物を常に触っていないと不安になったり、何かに触れ続けることでしか気持ちを落ち着かせられない場合は、感覚処理の特性が関係している可能性もあります。
単なる好奇心の範囲を超えて、日常生活に影響を与えているかどうかを見極めることが大切です。
保育士ができる関わり方
「多動かも?」と感じる子どもには、環境や関わり方を工夫することで、落ち着いて過ごせる時間が増えていきます。
環境の工夫
- 余計な刺激を減らす(おもちゃの数を減らす、スペースを区切る)
- 移動の多い活動と静の時間をバランスよく取り入れる
- 「ここなら動いてもいい」エリアを決める
周りに視線が移りやすい傾向にあるので、できる限り気が散りにくい環境を整えてあげるようにしてみましょう。また、「自由に動いていい場所」を作ることで、メリハリがつきやすくなります。

ただし、動いていい場所と、そうでない場所を決めた場合は、子どもの混乱を避けるためにも、必ずいつも同じ対応をするようにしてくださいね。
声かけの工夫
- 「ダメ!」ではなく「~しようね」とやって欲しい行動を伝える(例:「走らないで!」→「おててつないで歩こうね」)
- 短く具体的に伝える(例:「片付けてね」ではなく「ブロックを箱に入れてね」)
- 一緒に動きながら声をかける
指示はシンプルに。「これならできる!」と感じられるように伝えてみましょう。
発達に凸凹がある無いにかかわらず、否定的な言葉は子どもにとって伝わりにくいため、基本的にやって欲しいことを言葉にしたり、肯定的な言葉で伝えるようにしましょう。
まとめ
1歳半の「落ち着きのなさ」は、発達の一環であることが多いため、見極めが非常にむずかしい時期です。
無理に発達障害かも、多動かも・・と決めつけることはせず、子どもの姿をしっかりと捉え、冷静に判断してください。
ポイントまとめ
- 一歳半は好奇心が旺盛で動き回るのが普通
- 「探索が止まらない」「衝動的」「感覚刺激を求める」などタイプがある
- 環境調整や声かけを工夫することで落ち着きが生まれる
- 生活リズムや興味のあることを見直すと変化が見られることも
「もしかして?」と感じた時こそ、その子に合った環境や関わり方を工夫していくことが大切です。
1歳半検診への心配がある方向けの記事も参考にしてください。
▶【保健師に相談すべき?】一歳半健診でよく聞かれること&伝えるべきこと
さらに詳しく発達支援について学びたい方へ
最近よく耳にするようになった発達障害とはそもそも何なのか・・?
気になる行動は発達障害が原因なのか・・
適切な関わり方はどんな方法があるのか・・・
そんな疑問や悩みがある方のためにおすすめの資格があります。それは資格大手サイトユーキャンの「子ども発達障がい支援アドバイザー」。

「子ども発達障がい支援アドバイザー」という資格では、発達に課題のある子どもへの適切な関わり方を学ぶことができるので、保育士さんはもちろん、子育て中にパパママにもピッタリ!
このような資格取得を通じて専門的な知識を学ぶことで、より自信を持って目の前の子どもと関わることができるようになるため、近年とても人気を集めている資格です。
「発達支援について理解を深めたい!我が子の気になる行動を少しでも落ち着きのある状態にしてあげたい」
そう感じていらっしゃる保護者の方にもピッタリの資格になっているので、ユーキャンで専門的な知識を得て、子どもとのより良い関わり方、向き合い方を学んでいきましょう。無料資料請求もおススメです!!
詳しくはこちら 子ども発達障がい支援アドバイザーの詳細をチェック
なお、ユーキャンのほかにも「四谷学院」など発達支援系の資格は複数あります。
それぞれの違いや選び方については以下の記事でくわしくまとめていますので、ぜひ参考にしてください。

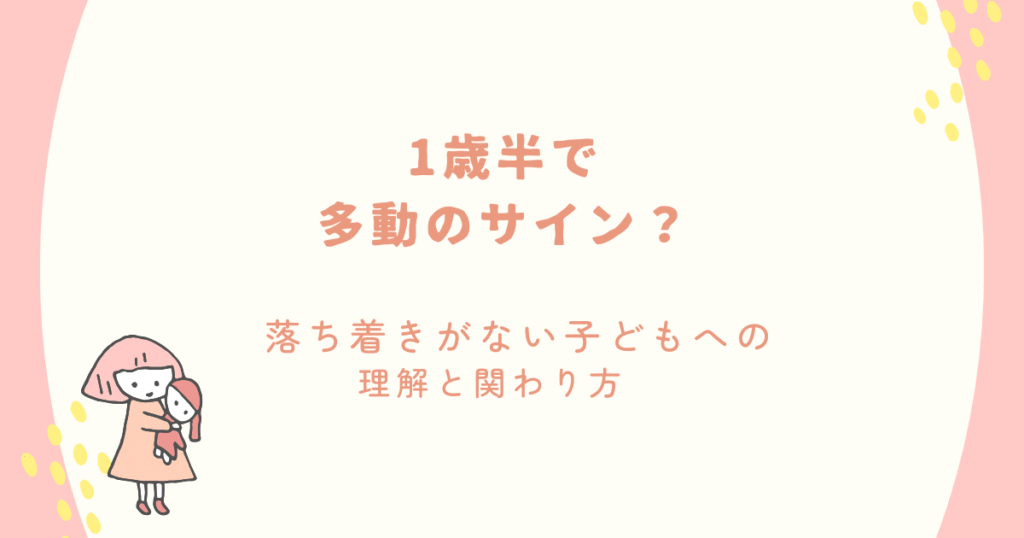

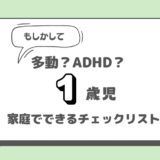

I like this post, enjoyed this one thanks for putting up. “Money is a poor man’s credit card.” by Herbert Marshall McLuhan.
krdquc
hh4rda
I really like your writing style, fantastic information, thankyou for putting up : D.
Some genuinely interesting details you have written.Aided me a lot, just what I was searching for : D.